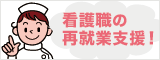特別児童扶養手当制度
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、中程度以上の障害のあるお子様を監護する親、もしくは親に代わり養育する方に対して、児童福祉の増進を目的に、一定額の手当を支給する制度です。申請は、お住まいの市町村役場が窓口になります。
特別児童扶養手当のしおり(R7)PDF形式 6,055キロバイト)(外部リンク)
【目次】
特別児童扶養手当を受けることができる方
手当の受けることができる方は、概ね、下記の要件(1)、(2)を満たす方です。
要件(1)20歳未満で障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、 主として対象児童の生計を維持している方であること
障害のある方のお世話をする親等を対象にした制度です。
(注意)ただし、次の場合は手当が支給されません。
- 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
- 児童が障害を事由とする公的年金(障害年金など)を受けることができるとき。
- 児童が児童福祉施設など(通園施設や保育所は除く)に入所しているとき。
要件(2)障害のある児童の障害程度が中程度以上であること
ここでいう中程度以上の障害とは、政令で定める程度の障害をいいます。
特別児童扶養手当では、障害の状態の程度を判定しますが、ここでいう「障害の状態」とは、「傷病がなおった」もしくは「症状が固定した」状態をいいます。
- 傷病がなおった
器質的欠損若しくは変形又は後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとみなします。 - 症状が固定した
症状が安定するかもしくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいいます。
- 1級
日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度の障害がある方。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない方、又は行ってはいけない方。
すなわち病院内または家庭内ともに、おおむね就床されている方になります。
知的障害でいえば重度・最重度の方、内部障害(呼吸器障害、心疾患等)でいえば一般状態区分表のVに該当する方になります。 - 2級
他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難である程度の障害がある方。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけない方。
すなわち、病院内の生活でいえば、ほぼ病棟内で日常生活を送っている方であり、家庭内の生活でいえば、ほぼ家屋内で日常生活を送っている方になります。
知的障害でいえば中等度の方、内部障害(呼吸器障害、心疾患等)でいえば一般状態区分表のIII・IVに該当する方になります。
所得による支給制限
また、受給中であっても、前年中の所得が一定以上の場合は支給停止となります。
障害の認定基準について
障害の程度は、障害別によって政令で定められています。
認定基準の詳細は、 認定要領(PDF形式 92キロバイト)、
認定要領(PDF形式 92キロバイト)、 認定基準(R4.4.1~)(PDF形式 413キロバイト) をご参照ください。
認定基準(R4.4.1~)(PDF形式 413キロバイト) をご参照ください。
(注意)令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が改正されています。
診断書の様式について
特別児童扶養手当認定診断書の様式は下記のとおりです。
- 眼の障害用(様式第1号)
 様式(エクセル形式 60キロバイト)
様式(エクセル形式 60キロバイト) 様式(PDF形式 165キロバイト)
様式(PDF形式 165キロバイト)
- 聴力・平衡機能・そしゃく機能・音声言語機能障害用(様式第2号)
 様式(エクセル形式 77キロバイト)
様式(エクセル形式 77キロバイト) 様式(PDF形式 96キロバイト)
様式(PDF形式 96キロバイト)
- 肢体不自由用(様式第3号)
 様式(エクセル形式 494キロバイト)
様式(エクセル形式 494キロバイト) 様式(PDF形式 550キロバイト)
様式(PDF形式 550キロバイト) - 知的障害・精神の障害用(様式第4号)
 様式(エクセル形式 53キロバイト)
様式(エクセル形式 53キロバイト) 様式(PDF形式 98キロバイト)
様式(PDF形式 98キロバイト) - 呼吸機能障害用(様式第5号)
 様式(エクセル形式 89キロバイト)
様式(エクセル形式 89キロバイト) 様式(PDF形式 118キロバイト)
様式(PDF形式 118キロバイト) - 循環器疾患の障害用(様式第6号)
 様式(エクセル形式 85キロバイト)
様式(エクセル形式 85キロバイト) 様式(PDF形式 115キロバイト)
様式(PDF形式 115キロバイト) - 腎、肝疾患、糖尿病の障害用(様式第7号)
 様式(エクセル形式 93キロバイト)
様式(エクセル形式 93キロバイト) 様式(PDF形式 121キロバイト)
様式(PDF形式 121キロバイト) - 血液・造血器、その他の障害用(様式第8号)
 様式(エクセル形式 79キロバイト)
様式(エクセル形式 79キロバイト) 様式(PDF形式 102キロバイト)
様式(PDF形式 102キロバイト)
(注意)令和4年4月1日から「眼の障害」の診断書様式が一部改正されています。
※申請をお考えの場合は、まずはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。
障害福祉課所管事務における特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価書の公表
- 特別児童扶養手当の支給に関する事務
 基礎項目評価書(特別児童扶養手当)(PDF形式 474キロバイト) <令和7年8月21日公表>
基礎項目評価書(特別児童扶養手当)(PDF形式 474キロバイト) <令和7年8月21日公表>