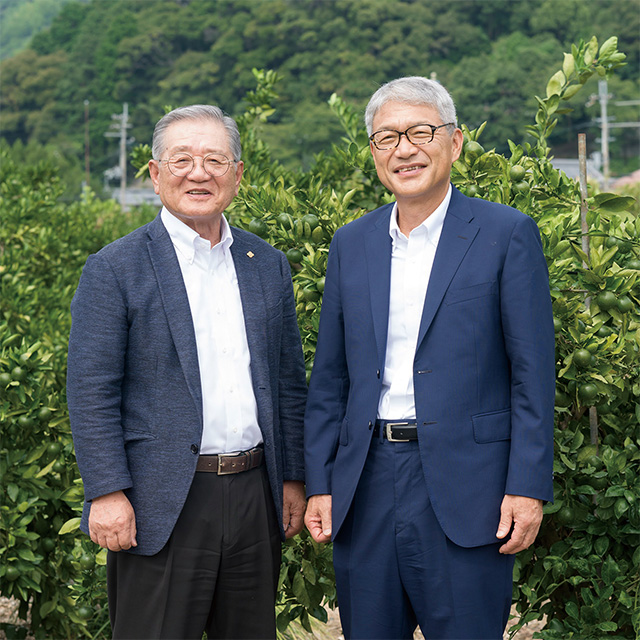
知事対談
株式会社早和果樹園会長
秋竹新吾
和歌山県知事
宮﨑泉
有田みかんから広がる
地域と人を繋ぐ力が
和歌山県の発展を
支えていく
和歌山県農業のブランド力強化や若者の就農促進、こどもと地域の関わりづくりなど、地域の未来を見据えた活動を続ける地域づくりの第一線で活躍する実践者に展望を聞いた。
PROFILE

- 秋竹 新吾Akitake Shingo
-
1944年和歌山県有田市生まれ。県立吉備高校(現有田中央高校)柑橘園芸科を卒業後、実家の果樹園を継承して就農。1979年、7戸のみかん農家が集まり早和共撰を創業。2000年に法人化。2005年に株式会社早和果樹園へと改組して社長に就任。2014年、6次産業化優良事例で農林水産大臣賞を受賞。2017年、会長に就任。旭日単光章受章。
宮﨑知事(以下宮﨑)◆ 秋竹さんはグローバルとローカルを合わせた、グローカルな視点が大切だとおっしゃられていますね。
秋竹新吾(以下秋竹)● 自動車産業のようなグローバル産業と、観光・交通などローカル産業を比較すると、日本を含めた多くの先進国ではローカル産業の方が高い割合を占めています。一方で、経済・産業の発展に向けた議論では、規模が大きくて派手なグローバル産業に焦点を当てることが圧倒的に多く、ローカル産業は割と見落とされます。大きな流れでみると、実際にはグローバリゼーション(国境を越えたつな繋がり)が進むほど立地が海外に進出していき、ますます先進国の国内におけるグローバル産業の比率が小さくなっていくと考えられます。日本全体の生活を豊かにするためには、むしろローカル産業が大事になるという構造に、ある時気づいたわけです。同時にグローバルな産業とローカルな産業は格差があって、どう埋めていくかということを考えました。ひとつはローカルの産業は頑張ること、もうひとつは両者がうまく繋がっていくこと。観光業などはグローバルの豊かさがローカルに持ち込まれる典型です。このメカニズムに気づいた15年ほど前から、私は自分の立ち位置を、グローバルな世界からローカルに移して、グローカルな視点を追いかけていこうと思い始めました。

糖度12度ある「味こいしぼり」は濃厚なみかんの味わい。
宮﨑◆ 秋竹さんが会長を務める早和果樹園は2000年に設立され、有田地域特産の温州みかん「有田みかん」を栽培していらっしゃいます。私自身も長くそのご活躍を拝見してまいりました。
秋竹● みかん栽培に携わり60年余りになりますが、これまでみかん一筋に生きてきました。まさに「みかん色」の人生でしたね(笑)。振り返ると、2000年に法人化したことが大きなターニングポイントでした。それまでは生産一筋でしたが、加工や販売にも挑戦するようになったんです。現在は生産(一次産業)だけでなく、加工(二次産業)から販売(三次産業)の全てに携わる「六次産業化」に取り組んでいます。当時はまだそんな言葉も広まっていなくて、まさに手探りの状態でした。世の中では濃縮還元のジュースが主流でしたが、どうしてもストレートジュースにこだわりたいと考えていました。美味しいみかんを育てることには自信があったので、その強みをジュースにも活かしたいと考え、思い切って糖度12度以上の有田みかんだけを厳選して搾ってみようとなったんです。試飲していただいた百貨店のバイヤーさんや有名ホテルの料理長さんから「こんなジュースは初めてだ」と絶賛していただきました。その一方で、今度はこの商品をどうやって売っていくかという壁にぶつかることになりました。
宮﨑◆ これまでにない新しい商品を販売する際には、最初はなかなか受け入れられないこともありますよね。どのように商品の魅力を伝えていかれたのでしょうか。
秋竹● どうしても値段が高いことがネックでしたが、ある時、観光地で販売したら本当にたくさんの人が手に取ってくださって。販売するターゲットはここだ!と感じました。また、とにかく一度飲んでもらおうと年間65万人のお客様と向き合い続けてきました。PR効果もそうですが、そこでお客様との結びつきも生まれ、自信にも繋がったんだと思います。

和歌山県知事 宮﨑泉
人が産地へ訪れる
工夫を凝らす
宮﨑◆ 新しくオープンしたカフェ「果汁と果実」ですが、とても明るい雰囲気で、若い方が本当にたくさんいらっしゃってましたね。秋竹さんはこのお店にどのような思いを込められているのですか。
秋竹● やはり一番の思いは、みかんを直接販売できる場所が欲しいということでした。京阪神から来られるお客様も多く、「生のみかんが欲しい」という声に応えることができて本当に良かったと思っています。今は若い社員がSNSでの発信を積極的に行ってくれているので、現地まで直接お越しくださる方が多く、私自身も驚いています。夏場はみかんがないため、パフェなどのスイーツや加工品を中心に販売しています。実際にみかんの産地を訪れていただき、現場で手に取ってもらえる、そんな場所を目指しているところです。

早和果樹園本社内にある店舗ではジュースの販売や試飲を行う。
食をきっかけに
自然な交流を
宮﨑◆ 新しく社員食堂「なでしこ食堂」をオープンされました。どのような思いで始められましたか。
秋竹● なでしこ食堂は、創業時から支えてくれている女性たち7名が中心となり、「株式会社早和なでしこ」を立ち上げて運営してくれています。早和果樹園には100名ほどの従業員がいますが、そのうち約4割が20代で、地元出身者だけでなく県外から来てくれている人も多いんです。一人暮らしをしている従業員の食生活を見ていると、この地域は飲食店が多くないこともあり、どうしてもコンビニ弁当やインスタント食品中心になりがちなことが気になりましてね。せめて1日3食のうち1食だけでも健康的なごはんを食べてもらいたいという思いから始めました。従業員にはやはり健康で元気に働いてもらいたいですからね。また、食堂は普段顔を合わせない社員同士のコミュニケーションの場にもなっているんですよ。
宮﨑◆ 社員の皆さんにとっては、本当にありがたいことだと思います。さらに今年からは社員専用食堂の調理場を利用して、こども食堂「みんなのなでしこ食堂」を始められました。
秋竹● 以前から会社として地域貢献に取り組みたいと考えており、具体的なアイデアを検討していく中で、こども食堂をやってみようと準備をしてきました。スタッフは自ら志望してくれたボランティアだけで構成されていて、今は15人ほどが活動してくれています。また、社会福祉協議会の方々にも協力していただけることになり、地域の方々と力を合わせながら、運営を続けていきたいと考えています。こども食堂の開催をSNSで告知をすると、先着50名があっという間に満員になって、その盛況ぶりがとても嬉しく、やりがいを感じています。
宮﨑◆ 本当に素晴らしい取り組みだと思います。和歌山県としても、全ての小学校区にこども食堂を設置することを目標に掲げており、今年7月末の時点で131ヶ所が開設されています。地元のこども食堂を応援する企業は着実に増えてきていますが、企業自らが主体となって運営するケースはまだ少ないのが現状です。そうした中で、秋竹さんの取り組みは大変心強く、ありがたく思っています。今後は「みんなのなでしこ食堂」をどのような形に発展させていきたいとお考えでしょうか。
秋竹● 若い世代の人たちがボランティアで積極的に活動してくれている姿を見ると、本当に嬉しく思います。地域の皆さんがこの食堂に来てくだされば、食事をきっかけに自然と交流が深まり、仲良くなれるのではないかと感じています。“地元の方々が集い、みかんとともに良い形で広がっていってくれたら”そんな思いを持っています。
宮﨑◆ こども食堂の活動は単に食事を提供するだけでなく、こどもたちが地域の方々と交流できる居場所づくりにも繋がっていると考えています。和歌山のこどもたちが地域で健やかに成長し、一人ひとりの個性を生かして活躍できる社会を、県全体でつくりあげていきたいと強く思っています。その意味でも、秋竹さんにはぜひ今後も活動を続けていただければと願っています。
秋竹● 農業の会社にこれほど多くの若い人たちが集まってくれるとは思っていなかったので、本当に嬉しく感じています。人材なくして組織の成長はありません。これからも人を大切にしながら組織全体の成長に繋げ、より一層、有田地域をみかんで盛り上げていけたらいいなと思います。

まだ青いみかんは、これから冬にかけて色づいてゆく。
