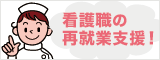46~58ページ(料金の割引制度・サービス等、公的機関の各種制度・取り組み)
(11)料金の割引制度、サービスとう
■各種運賃割引
鉄道運賃割引
各鉄道を利用する場合、対象者は身体障害者手帳又は療育手帳を提示することにより運賃が割引されます。
対象者・割引内容等
事業者により、対象者、割引内容、手続きとう、取り扱いが異なりますので、ご利用前に事業者へご確認ください。
お問い合わせ 鉄道会社、各駅の窓口
バス運賃割引
バスを利用する場合、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が、単独又は介護者とともに、バスを利用する場合、手帳を提示することにより運賃が割引されます。
対象者・割引内容等
事業者により、対象者、割引内容、手続きとう、取り扱いが異なりますので、ご利用前に事業者へご確認ください。
お問い合わせ バス会社
タクシー運賃割引
タクシーを利用する場合、対象者は身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を提示することにより運賃が割引されます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者
(事業者により対象者が異なる場合があります)
割引内容
運賃の10パーセント割引(10円未満の端数は切り上げ)
お問い合わせ タクシー会社
航空運賃割引
航空を利用する場合、搭乗時の年齢がマン3歳以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちのかた、及び同一便に搭乗されるマン12歳以上の介護者のかた(ひとりまで)が利用できます。
対象者・割引内容等
事業者により、対象者、割引内容、手続きとう、取り扱いが異なりますので、ご利用前に事業者へご確認ください。
お問い合わせ 航空会社、旅行会社
■有料道路通行料金割引
身体障害者のかたが自ら運転する場合又は重度の身体障害者のかたもしくは重度の知的障害者のかたが同乗し、障害者ご本人以外のかたが運転する場合に、通勤、通学、通院等に利用する際の有料道路通行料金が割引になります。
制度の利用には、市町村の障害福祉担当課又はオンラインにて事前登録が必要です。
ETCが利用できる道路においては、事前に登録手続きを行うことにより、ETCノンストップ通行においても同様の割引が適用されます。
令和5年より法律が一部改正され、タクシー、福祉有償車両、レンタカー、知人の車や車検時の代車とう、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールがテンプされた障害者手帳等を提示することで割引が適用されます。
対象者
有料道路通行料金割引申請登録済みのかた
タクシー、福祉有償車両は、手帳に道路介護と印字したシールがテンプされている場合のみ対象です。
お問い合わせ 市町村の障害福祉担当課 2ページから3ページ参照
■NHK放送じゅしんりょうの免除
身体障害者、知的障害者、精神障害者のかたがいる世帯で、世帯構成員全員が市町村みん税非課税の世帯は全額免除
視覚・聴覚障害者、重度の身体障害者1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級所持者のかたが世帯主で受信契約者の場合は半額免除
お住まいの市町村の障害福祉担当課に申請書を提出し、免除事由の証明を受ける必要があります。
証明を受けた申請書をNHKに提出することにより、受信料が減免されます。
お問い合わせ 市町村の障害福祉担当課 2ページから3ページ参照、NHK放送局
■携帯電話基本使用料とうの割引
NTTドコモ、au、ソフトバンクにおいて、携帯電話の料金の割引があります。
対象者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者しょう、特定疾患登録者しょうまたは特定医療費(指定難病)受給者しょうの所持者
割引内容
割引額はカクカイシャにより異なります。
お問い合わせ 各携帯電話事業者
■NTTの無料番号案内(ふれあい案内)
電話帳の利用が困難な障害のあるかたを対象に、無料で電話番号を案内します。
利用には事前に登録が必要です。
登録方法はNTT電話番号へ
対象者
身体障害者手帳所持者のうち次のかた
・視覚障害1級から6級
・肢体不自由(上肢、たいかん、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1・2級
・聴覚障害2級、3級、4級、6級
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害3級、4級
戦傷病者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
りよう料金 無料(通信料は別途かかります)
お問い合わせ NTTふれあい案内事務局
tel0120-104174 (全国共通) fax0120-104134 (全国共通)
■郵便に関する割引とう
点字郵便物・特定録音物等郵便物 (第ヨン種郵便物)
点字郵便物
点字のみを掲げたものを内容とする郵便物。
郵便物の名あて面上部に「点字郵便物」であることを明示。
料金は3キログラム以内、無料 郵便物は一部開封
特定録音とう郵便物
視覚障害者用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、日本郵便株式会社から指定を受けた施設からハツジュするものに限ります。
料金は3キログラム以内、無料 郵便物は一部開封
ゆうパック
聴覚障害者用ゆうパック
日本郵便株式会社が指定する聴覚障害者の福祉を増進するための施設と聴覚障害者との間で、聴覚障害者用のビデオテープその他の録画物(DVDなど)の貸し出し又は返却のためにハツジュされるゆうパック。
荷物には「聴覚障害者用ゆうパック」と明示すること。
料金はサイズにより異なる
郵便物は一部開封とし、包装するものについては、内用品が容易に透視できるよう包装すること。
点字ゆうパック
大型の点字図書等を内容とするゆうパック。
荷物には点字ゆうパックと明示すること。
料金はサイズにより異なる
郵便物は一部開封とし、包装するものについては、内用品が容易に透視できるよう包装すること。
心身障害者用ゆうメール
日本郵便株式会社に届け出た図書館と重度の身体障害者又は重度の知的障害者との間で、図書の閲覧のためにハツジュされるゆうメール。
料金はゆうメール料金の半額
図書館用ゆうメールと明示すること。
定期刊行物の低料第三種郵便物
心身障害者団体が心身障害者の福祉を図ることを目的として発行する定期刊行物
料金は発行回数等により異なる
第三種郵便物の承認を受けることに加えて、定められた公共機関が発行した証明書などの資料が必要
郵便に関するサービスについては、郵便局にお問い合わせください。
(12)公的機関の各種制度・取り組み
■ヘルプマーク
内部障害や難病のかた、義足や人工関節を使用しているかた、妊娠初期のかたなど、外見では障害とうがあることが分からないかたが、周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。
証明書類とうの提示は不要ですが「ヘルプマークもうしこみしょ」の記入が必要です。
配付は1人につき1個のみの配付となります。
配付場所
県庁障害福祉課
各振興局健康福祉部(串本支所も含む)
県障害児者サポートセンター
県難病・こども保健相談支援センター
一部の市町村障害福祉窓口(レイワ6年4月1日現在)
和歌山市(障害者支援課・保健対策課)、海南市、ありだし、御坊市、田辺市、紀の川市、いわでし、きみのちょう、かつらぎ町、こうやちょう、湯浅町、広川ちょう、ありだがわちょう、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべちょう、ひだかがわちょう、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町
■ヘルプカード
援助や配慮を必要としている具体的な情報を伝えることができるカードです。ヘルプマークと併用していただくと、周囲のかたに必要な情報が伝わりやすくなります。災害や事故などの緊急時に、ヘルプカードがあれば周囲の人が必要な情報を知ることができます。
県のホームページからダウンロードができます。ページ左下あたりのQRコードから、ホームページにアクセスできます。
カードは名刺サイズに折りたためます
■郵便とうによる不在者投票
身体障害者手帳をお持ちのかた又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「よう介護5」のかたが対象です。
投票を行うには、「郵便等投票証明書」の事前の交付申請が必要です。
なお、身体障害者手帳所持者で、郵便とうによる不在者投票の対象者は次のとおりです。
身体障害者手帳所持者(次の区分のかた)
両下肢、たいかん、移動機能の障害 1級、2級のかた
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の障害 1級、3級のかた
免疫、肝臓の障害 1級から3級のかた
介護保険のよう介護区分状態が「よう介護5」のかた
なお、郵便とうによる不在者投票の対象者で、かつ、上肢、視覚の障害により身体障害者手帳1級をお持ちのかたは、代理記載の方法による投票が認められています。
お問い合わせ 市町村選挙管理委員会
■自動車事故対策機構による介護料支給
自動車事故を原因として脳、脊髄又はキョウフクブ臓器に重度のコウイ障害があり、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要となったかたに、「独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)」から介護料が支給されます。
支給内容とう
介護料支給額 月額36,500円から211,530円
介護料の支給対象となる費用は、介護用品の購入とう
支給の制限
(1) 次のような支援を受けているかたは、支給の対象になりません。
1 ナスバリョウゴ施設とうに入院しているかた
2 た法令に基づく施設に入所しているかた
3 た法令による介護料相当の給付を受けているかた
(2) 主たる生計維持者の年間の合計所得金額が1000万円を超えると認められるとき
お問い合わせ
支給対象となるかた及び詳しい支給要件とうは、お問い合わせください。
独立行政法人自動車事故対策機構 和歌山支所
tel073-431-7337
■県立施設使用 料減免制度
障害のあるかたの社会参加を促進することを目的に、県の施設を利用する場合、下記対象者は施設使用料の減免を受けることができます。
制度の利用には、障害者手帳または障害者手帳アプリの提示が必要です。また、制度の対象施設かどうか事前に確認してください。
次の対象者は、5割引きから10割引きです。
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者
・障害者、発達障害者またはその介護にんを主な構成員とする団体(県に事前登録が必要です)
次の対象者は、障害者ひとりにつきイチメイ 使用料無料
身体障害者手帳(1種)、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者の各介護にん
お問い合わせ 対象施設、県庁障害福祉課 計画調整班
■音声以外の方法によるヒャクトーバン
警察では、聴覚や言語機能に障害のあるかたや音声によるヒャクトーバン通報が困難なかた専用のヒャクトーバンを運用しています。
聴覚や言語機能に障害のあるかたや、音声によるヒャクトーバン通報が困難なかた以外の使用はご遠慮ください。
アプリのダウンロード方法や登録等については、ホームページをご覧ください。
和歌山県警察 ヒャクトーバンアプリシステムで 検索
メールヒャクトーバン
専用メールアドレス police@110wakayama.jp
事件・事故の内容を本文に記載し、送信してください。
専用メールアドレスからのメールを受信できるよう設定してください。
FAXヒャクトーバン
fax073-428-0110
音声以外の方法によるヒャクトーバンへの通報内容は次のとおりです。
1 何がありましたか?(事件なのか、事故なのか。何があったのか)
2 どこでありましたか?(その場所はどこか、目印になる建物や住所)
3 いつのころですか?(今なのか少し前なのか、発生時間)
4 犯人はどうしましたか?(性別は?服装は?何歳ぐらい?ニンソウは?どちらへ逃げたかなど)
5 今、どうなっていますか?(ケガの程度や被害の様子)
6 あなたのお名前・ご住所(あなたの名前・住所)
お問い合わせ 警察本部 地域指導課 通信指令室
■駐車禁止の除外
げんに対象者が使用している車両で、付近に適当な駐車場がないなど、やむを得ない場合は、公安委員会が発行した「駐車禁止除外指定車ひょうしょう」を掲出していれば、駐車することができます。なお、本制度が有効となるのは、公安委員会が道路標識とうで駐車禁止を指定した場所となります。
対象者以外でも、やむを得ない事情により駐車せざるを得ない場合は、その場所を管轄する警察署長の駐車許可制度があります。
対象者
・歩行困難なかたとうで身体障害者手帳の交付を受け、かつ、駐車禁止除外指定車ひょうしょう交付基準(下記参照)に該当するかた
・療育手帳A1、A2所持者
・精神障害者保健福祉手帳1級所持者
・小児慢性特定疾病医療受給者しょうの交付を受けており、色素性カンピ症であるかた
お問い合わせ 警察署
■駐車禁止除外指定しゃひょうしょう身体障害者基準ひょう
視覚障害1級から3級までの各級及び4級の1まで
聴覚障害2級及び3級
平衡機能障害3級
肢体不自由
上肢障害1級、2級の1及び2級の2
下肢障害1級から4級まで
たいかん障害1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合は除く)
移動機能1級から4級まで
機能障害
心臓機能障害1級及び3級
じん臓機能障害1級及び3級
呼吸機能障害1級及び3級
小腸機能障害1級及び3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級まで
肝臓機能障害1級から3級まで
ただし、身体障害者手帳に同一区分の障害(肢体不自由、機能障害については同一部位の障害をさす。)が2つ以上記載されているかたは、上記の基準を満たしていなくても、駐車禁止除外指定しゃひょうしょうの交付を受けることができる場合があります。
お問い合わせ 警察署
■和歌山県障害者等用駐車区画利用証
障害のあるかたや難病患者、高齢者、妊産婦、けが人など移動に配慮を要するカタガタが使いやすい駐車場の仕組みとして、公共施設や商業施設などにおける障害者等用駐車区画をご利用いただくための利用証を交付しています。
利用者を明らかにすることで、当該駐車区画の適正な利用を図る制度です。パーキング・パーミット制度と呼ばれています。
対象となる駐車区画
商業施設やホテルなど、県に登録したゆずりあい駐車区画や車椅子使用者用駐車場でお使いいただけます。
対象者
身体障害者手帳所持者(交付要件は次ページ参照)
・療育手帳(A1、A2)所持者
・精神障害者保健福祉手帳1級所持者
・難病患者
・要介護高齢者(要介護1以上)
・妊産婦(単体児 妊娠7か月から産後3か月)
(多胎児 妊娠6か月から産後18か月)
・けが等により一時的に移動の配慮が必要な者 ほか
車椅子使用者用駐車区画やゆずりあい駐車区画を必要としているかたが安心して利用できるよう、駐車場を空けておく等、ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ 県庁障害福祉課、県振興局健康福祉部
●和歌山県障害者等用駐車区画利用証の交付要件、必要書類および有効期間について
次の障害の区分に該当するかたは、有効期間は5年で必要書類は身体障害者手帳です。
視覚障害4級以上、聴覚障害3級以上、平衡機能障害5級以上
じょうし肢体不自由2級以上、かし肢体不自由6級以上、たいかん肢体不自由5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
じょうし機能2級以上、移動機能6級以上
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸の機能障害4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害4級以上、肝臓機能障害4級以上
療育手帳A1,A2またはAのかたの有効期間は5年で、必要書類は療育手帳です。
精神障害者保健福祉手帳1級のかたの有効期間は5年で、必要書類は精神障害者保健福祉手帳です。
難病患者、特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者のかたの有効期間は5年で、必要書類は各受給者証です。
要介護高齢者、要介護状態区分が要介護1以上のかたの有効期間は5年で、必要書類は介護保険被保険者証です。
妊産婦で、単体児を妊娠されているかたの場合、有効期間は妊娠7か月から産後3か月
妊産婦で、多胎児を妊娠されているかたの場合、有効期間は妊娠6か月から産後18か月がで、必要書類は母子健康手帳です。
けがとうにより一時的に移動の配慮が必要なかたの有効期間は、車いす、杖などの使用期間により1年以内で、必要書類は医師の診断書・意見書等と本人確認書類(自動車運転免許証、保険証等)です。
そのたの歩行困難者で、医師の診断書等で駐車場の利用に配慮が必要と認められるかたの有効期間は、1年以内の必要な期間で、必要書類は医師の診断書・意見書等と本人確認書類(自動車運転免許証、保険証等)です。
■和歌山県アイサポート運動
様々な障害の特性、障害のあるかたが困っていることや必要としている配慮などを理解して、障害のあるかたに対してちょっとした手助けや配慮を実践することによって、障害のあるかたが暮らしやすい地域社会をつくっていく運動です。
アイサポート運動は、平成21年11月28日に鳥取県でスタートしました。
和歌山県では、平成28年8月に鳥取県と協定を結び、アイサポート運動に取り組んでいます。
取組の内容
アイサポーターの養成
様々な障害の特性を理解し、障害のあるかたが困っているときに、必要な配慮ができる人、また、アイサポート運動を周囲に周知していく人が「アイサポーター」です。
アイサポーター養成のための「アイサポーター研修」を、地域や職場等で実施したい場合は、県庁障害福祉課へお気軽にお申し込みください。県庁職員が講師として出向き、研修を実施します。
アイサポート企業・団体の募集
アイサポート運動の趣旨を理解し、運動の推進に取り組んでいただける「アイサポート企業・団体」を募集しています。
お問い合わせ 県庁障害福祉課 計画調整班、県振興局(支所)健康福祉部
和歌山県 アイサポート運動 で検索してください。
■和歌山県手話言語条例
和歌山県では、ろう者の言語である手話の普及のため、「和歌山県手話言語条例」を制定しています。 (平成29年12月26日施行)
誰もが手話に親しみ、ろう者と聞こえる人がお互いを理解し合う共生社会の実現をめざします。
ろう者とは、聴覚障害のある人で、手話を言語として生活をしている人のことです。
手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及び習得の機会の確保に関する必要な事項を定めることにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。
お問い合わせ 県庁障害福祉課 計画調整班
■災害に備えて
災害への備えとして、次のようなものが考えられます。
・ヘルプカードやお薬手帳等、自分の情報を記載したものをいつも持ち歩く。
(障害の状態や服薬状況、かかりつけ医療機関等)
・家族とお互いに連絡方法や避難時の移動方法について決めておく。避難場所までの避難経路を日頃から確認しておく。
・家の倒壊に備えて、家具を固定する、高い場所に重いものや割れものを置かない等の、自宅の安全対策を行う。
・最低3日分の食料品や生活必需品を備蓄しておく。
・服用している薬や補装具とう医療的ケアに必要な物品を可能な範囲で備えておく。
・市町村の避難行動要支援者名簿へ登録をする。
(避難行動要支援者名簿とは、災害が発生した際に、自力で避難することが困難な障害のあるかたなどの「避難行動要支援者」に対して、避難等の手助けや安否確認、避難所での配慮が、地域の中で素早く、安全に行われるようにするための名簿です。詳細は各市町村にお問い合わせください。)
・「和歌山県防災ナビ」アプリ、防災ワカヤマメール配信サービス、防災ワカヤマエックス(旧ツイッター)とう、防災情報等を入手する各種ツールの活用。
以上のツールについては、
ホームページ 防災ワカヤマ 災害に備えて を検索してください。
音声コードはこのページで最後です。
次の59ページ以降、音声コードはついていません。