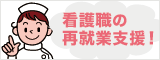20~27ページ(年金・手当、医療)
(2)年金・手当等
■障害基礎年金(こくみん年金保険)
支給要件 次の1から3をすべてみたす必要があります。
1 こくみん年金に加入している間に初診び(障害の原因となった病気やけがについて、初めて診察を受けた日)があること
20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診びがあるときも含みます。
2 初診びの前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
(1)初診びのある月の前々げつまでの公的年金の加入期間の三ぶんの二以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
(2)初診びにおいて65歳未満であり、初診びのある月の前々げつまでの1年間に保険料の未納がないこと(レイワ8年3月31日までに初診びがある場合に限る)
3 障害認定日(初診びから1年6か月経過した日)において、こくみん年金法施行令別表に定める1級、2級の障害に該当している者(身体障害者手帳の障害等級とは異なります。)
年金額 れいわ6年4月現在
1級 1,020,000円(年額) ぷらす コの加算
昭和31年4月1日以前に生まれたかた 1,017,125円
2級 816,000円(年額) ぷらす コの加算
昭和31年4月1日以前に生まれたかた 813,700円
コの加算 第いっし、第にし 各234,800円(年額)
第さんし以降 各78,300円(年額)
コとは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある子
和歌山東年金事務所 和歌山市おおだ3の3の9
tel073-474-1841
和歌山西年金事務所 和歌山市せきど2の1の43
tel073-447-1660
田辺年金事務所 田辺市朝日がおか24の8
tel0739-24-0432
田辺年金事務所 新宮分室 新宮市たに王子町456の1 かめやビル1階
tel0735-22-8441
電話をかけていただき、自動音声案内後、1の次に2を押してください。
お住まいの市町村により、管轄する年金事務所が異なります。事前にお問い合わせください。
■障害厚生年金(厚生年金保険)
支給要件 次の1から3をすべてみたす必要があります。
1 厚生年金に加入している間に初診び(障害の原因となった病気やけがについて、初めて診察を受けた日)があること
2 初診びの前日において、次のいずれかの要件を満たしていること
(1)初診びのある月の前々げつまでの公的年金の加入期間の三ぶんの二以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々げつまでの1年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月31日までに初診日がある場合に限る)
3 障害認定日(初診びから1年6か月経過した日)において、厚生年金法施行令別表に定める1級から3級の障害に該当している者(身体障害者手帳の障害等級とは異なります。)
年金額(れいわ6年4月現在)
1級 報酬ひれいの年金額カケル1.25プラス配偶者の加給年金額(234,800円)
2級 報酬ひれいの年金額プラス配偶者の加給年金額(234,800円)
3級 報酬ひれいの年金額(最低保障額612,000円)
昭和31年4月1日以前に生まれたかた 610,300円
1級及び2級と認定された人には、こくみん年金の障害基礎年金も併せて支払われます
お問い合わせ
日本年金機構年金事務所 20ページ参照
■特別障害給付金
支給対象者(れいわ6年4月現在)
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができない障害のあるかた
1 平成3年3月以前にこくみん年金任意加入対象であった学生で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあるかた
2 昭和61年3月以前にこくみん年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあるかた
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当されたかたに限ります。
支給額 所得による制限あり
障害基礎年金1級相当に該当するかた 基本月額55,350円
障害基礎年金2級相当に該当するかた 基本月額44,280円
お問い合わせ
市福祉事務所又はちょうそん役場
■心身障害者扶養共済制度
障害のあるかたを扶養している保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者にまんいち(死亡・重度障害の状態)のことがあったときに、障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する制度
心身障害児者を扶養する保護者で、次の要件に該当するかたが加入できます。
加入者のかたの住所が県内にあること
加入時の年度の4月1日時点の年齢がマン65歳未満であること
加入時に特別な疾病又は障害がないこと
加入時に告知による審査があり、場合によっては加入をお断りすることがあります。
障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。
対象となる障害者は次の1~3のいずれかにあてはまり、4に該当するかたです
1 身体障害者手帳1級から3級
2 知的障害児者
3 精神またはシンタイに永続的な障害のある者で、上記1・2と同程度の障害があると認められるもの
4 将来独立自活することが困難であると認められるかた(対象となる障害児者の年齢は問いません)
掛金は令和6年4月現在、加入者の加入時の年齢・加入時期に応じた掛金9,300円から23,300円となっており、2口まで加入できます。
加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害のあるかたに毎月2万円(ふた口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
加入者が支払う掛金は所得控除の対象になります。
申請先 市福祉事務所又はちょうそん役場
お問い合わせ 県庁こころの健康推進課
■特別障害者手当
精神又はシンタイに著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とした制度
精神又はシンタイに著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方が対象(施設入所中・長期入院の方は非該当)
支給額は令和6年4月現在、月額28,840円(所得制限あり)
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請先 市福祉事務所又はちょうそん役場
お問い合わせ 市福祉事務所又はちょうそん役場、県振興局健康福祉部
■障害児福祉手当
重度障害児に対して手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的とした制度
精神又はシンタイに重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかたが対象(施設入所中のかたは非該当)
支給額はレイワ6年4月現在 月額15,690円 所得制限あり
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請先 市福祉事務所又はちょうそん役場
お問い合わせ 市福祉事務所又はちょうそん役場、県振興局健康福祉部
■特別児童扶養手当
中程度以上の障害児を養育するフボ、もしくはフボに代わり養育するかたに対して、一定額の手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度
対象となる障害児
精神又はシンタイに障害を有するため、家庭で監護、養育を必要とする状態にある20歳未満のかた(施設入所中のかたは非該当)
1級の障害程度
日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければ、ほとんど自己の用を弁ずることができない程度(重度の障害)
2級の障害程度
他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難である程度(中度の障害)
施設入所中の方は非該当
支給額はレイワ6年4月現在
1級 月額55,350円
2級 月額36,860円
所得制限あり
原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
12月分は11月に受け取ることができます。
申請先 市福祉事務所又はちょうそん役場
お問い合わせ 市福祉事務所又はちょうそん役場、県庁障害福祉課 在宅福祉班
■児童扶養手当
ヒトリオヤ家庭等の生活の安定と自立を促進するための手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度
以下に定める児童を養育している父又は母等に支給されます。
・フボが離婚や死亡等により、ヒトリオヤとなった家庭の親
・フボに代わって当該児童を養育しているかた
・父又は母のシンタイ又は精神に一定の障害の状態にある家庭の親
(児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかた。)
(児童に重い障害がある場合は、支給期間が20歳まで延長される場合があります。)
支給額はレイワ6年4月現在(所得制限あり)
児童1人の場合 月額45,500円~10,740円
児童2人の場合 月額10,750円~5,380円 加算
以下、1人増す毎に 月額6,450円~3,230円 加算
原則として毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月に、それぞれの前月分までが支給されます。
お問い合わせ・申請先 市福祉事務所又はちょうそん役場
コラム ワカヤマ子育て支援ポータルサイト
ワカヤマ子育て支援ポータルサイトでは、子育てに関する相談窓口、ワカヤマ子育て支援パスポート事業等、子育ての参考となる情報が掲載されています。
「ワカヤマ子育て支援パスポート事業」では、子育て中のかた及び妊娠中のかたが、県が配布する「ワカヤマ子育て支援パスポート事業」パスポートを、協賛してくれているお店や施設などで提示すると、料金の割引やプレゼントなどの優待サービスをうけることができます。
詳細は ワカヤマ子育ての広場 を検索してください
(3)医療
■自立支援医療(更生医療)
障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、生活の能力を得るために必要な医療費を一部助成する制度
対象者は18歳以上の身体障害者手帳所持者
自己負担額 原則として、医療費の1割負担
所得に応じて、ひとツキの自己負担上限額が決められています。
お問い合わせ・申請先 市福祉事務所又はちょうそん役場
治療開始前に居住地の市町村にて手続きを行ってください。
■自立支援医療(育成医療)
障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な医療費を一部助成する制度
対象者は満18歳未満で、シンタイじょうの障害を有する児童又は現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められ確実な治療効果が期待できる児童
自己負担額 原則として、医療費の1割負担
所得に応じて、ひとツキの自己負担上限額が決められています。
お問い合わせ・申請先 市福祉事務所又はちょうそん役場
治療開始前に居住地の市町村にて手続きを行ってください。
■自立支援医療 (精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)を有するかたで、通院による精神医療を継続的に必要とする症状にあるかたに対し、その通院医療に係る医療費を一部助成する制度
対象者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状のかた
■重度心身障害児者医療費助成
重度の障害のあるかたが、病院等で診療を受けた際に支払う自己負担金を助成する制度
対象者は次のかたです(所得制限あり)
1 身体障害者手帳1・2・3級所持者
(身体障害者手帳3級所持者のかたは、市町村みん税所得割非課税世帯に限られ、入院医療費のみの助成)
2 療育手帳A1・A2所持者
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
特別児童扶養手当1級該当者
65歳以上で新たに上記障害者となられたかたは除きます。
対象となるかたが病院等で診療を受けた時に支払う自己負担金が助成されます。(本人の自己負担はなしとなります。)
お問い合わせ・申請先 市福祉事務所又はちょうそん役場
和歌山市在住のかたで、対象者1、2、4に該当するかたは和歌山市障害者支援課へ、対象者3に該当するかたは和歌山市保健所保健対策課へお問い合わせください。
■難病医療費助成制度
対象となるかたが、対象疾患に関して受けられた医療費等の一部を公費で負担し、自己負担の軽減を図ります。
対象者は、県内に居住し、原則として「指定難病」と診断され、病状の程度が一定程度以上のかた(指定難病患者のかたが18歳未満の場合、保護者が和歌山県内に居住している場合も対象となります。)
対象疾患 指定難病の341疾病が対象
指定難病一覧は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
難病法に基づく指定難病の患者であって、その病状が厚生労働大臣の定める程度であると認められた場合は、「特定医療費」の支給が認められます。
支給額等の制度の詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせ・申請先 県立保健所・支所
和歌山市在住のかたは和歌山市保健対策課へお問い合わせください。
お問い合わせ
県庁健康推進課 がん・疾病対策班 tel073-441-2640 fax073-428-2325
自己負担額 原則として、医療費の1割負担
所得に応じて、ひとツキの自己負担上限額が決められています。
お問い合わせ・申請先 市福祉事務所(和歌山市は保健対策課)又はちょうそん役場
お問い合わせ 県精神保健福祉センター
■小児慢性特定疾病医療費助成
児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童とうについて、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度
18歳未満の児童で、小児慢性特定疾病の対象疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童とう
18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象
国が定める疾病は、小児慢性特定疾病情報センターをご確認ください。
支給額等
認定を受けると、対象の医療の患者自己負担割合は3割から2割になります。
義務教育就学前でもともと2割負担の場合は変わりません。
所得に応じて自己負担上限月額が定められますので、発行される受給者しょうを医療機関で提示すれば、その金額以上を窓口で負担する必要はありません。
お問い合わせ・申請先 県立保健所・支所
和歌山市在住のかたは和歌山市保健対策課へお問い合わせください。
お問い合わせ 県庁健康推進課 母子保健班 tel073-441-2642 fax073-428-2325
■後期高齢者医療制度の65歳以上からの適用
医療保険である後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方に適用されますが、一定の障害があるかたについては、後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより、65歳からの適用が可能となります。
なお、一度受けられた認定は、申請によりいつでも将来に向かって撤回することができ、撤回した後で再度申請することも可能です。
75歳以上のかたは、障害の有無に関わらず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
対象者は次のかたです。
身体障害者手帳1・2・3級所持者、4級の一部所持者
療育手帳A1・A2所持者
精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
こくみん年金法における障害年金1・2級受給者
自己負担額
所得に応じて、医療費の1割から3割の負担となります。詳しくは、各市町村後期高齢者医療制度担当窓口までお問い合わせください。