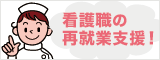過去の地震災害
1 地震の知識
1 過去の地震災害
- 地震災害
和歌山県の太平洋側の沖合には巨大地震を引き起こす南海トラフ(注1)があり、ほぼ100年から150年間隔で繰り返し地震が発生してきました。
また、その直後に津波におそわれることが多く、津波の高さは、高いところでは10メートル以上になることがあります。
昭和21年に発生した南海道地震で、和歌山県では地震により建物がこわれたり、津波、火災の被害により多くの人命と財産が奪われました。
また、県内の主要な活断層としては、中央構造線の一部を構成する根来断層、五条谷断層などがありますが、この活断層で地震が発生したかどうかの記録は残っていません。
(注1)トラフ 船底のような大洋底の細長い凹地
|
西暦(和暦) |
地域(名称) |
マグニチュード |
主な被害 |
|---|---|---|---|
| 宝永4年10月28日 | (宝永地震) | マグニチュード8.4 | 南海トラフ沿いの巨大地震。 死者688人、負傷者222人、家屋全壊681軒、同流失1896軒。 |
|
|
マグニチュード8.4 |
安政東海地震と安政南海地震の被害は区別するのが難しい。 紀伊田辺領で、死者24人、住家倒壊255軒、同流失532軒、同焼失441軒。和歌山領で溺死者699人、家屋全壊約1万件、同流失8496軒、同焼失24軒。広村で死者36人、住家全壊10軒、同流失125軒。沿岸の熊野以西では、津波により村の大半が流出した村が多かった。 |
| 昭和13年1月12日 | 田辺沖 | マグニチュード6.8 | 紀伊水道沿岸で小被害、特に和歌山県日高郡、西牟婁郡の沿岸地方で被害が多かった。 |
| 昭和19年12月7日 | 東南海地震 | マグニチュード7.9 | 東南海沖に起こった巨大地震で、東海地方や紀伊半島東南部に大被害あり。和歌山県では、地震動及び津波による被害あり。 死者51人、 負傷者74人、住家全壊121軒、同流失153軒。 |
| 昭和21年12月21日 | 南海道地震 | マグニチュード8.0 | 南海道沖に起こった巨大地震で紀伊半島や四国地方に大被害あり。和歌山県では地震動、津波、地震後の火災による被害あり。 死者・行方不明者269人、負傷者562人、住家全壊969軒、同流失325軒、同焼失2399軒。 |
| 昭和23年6月15日 | 和歌山県中部 | マグニチュード6.7 | 紀伊半島南西部に発生。和歌山県、奈良県南部に被害あり。特に西牟婁地方で被害が大きかった。 死者1人、負傷者18人、家屋全壊4軒、半壊33軒。 |
| 平成7年1月17日 | 兵庫県南部地震 | マグニチュード7.2 | 和歌山市北部で家屋の損傷など小被害あり。 |
2 地震がもたらす被害
- 建物の倒壊
家の中には危険がいっぱいです。平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、家の中で生命を失った人が5,000人近くいました。
耐震性の低い木造住宅の下敷きになったり、家具、電気製品の下敷きになったりしたためです。 - 津波による被害
和歌山県ではこれまで何度も、地震による津波の発生で大勢の人命が奪われています。昭和21年12月21日に発生した南海道地震では、午前4時19分過ぎに和歌山県全域が地震に襲われ、津波の第一波は地震発生のわずか数分後に県南部の海岸を襲いました。
この地震では、火災が発生して新宮市で市街地の3分の1が焼失したり、津波により多くの溺死者が出るなど、地震の揺れによる被害よりも、津波及び地震に伴う火災による被害の方がはるかに大きかったのです。 - 火災による被害
大正12年に発生した関東大震災では、地震の後に起こった火災によって約10万人が焼死しました。地震時には、普段のように消防自動車も走れませんし、断水すれば消火用水も不足します。
日本のような木造住宅が密集した市街地では、地震の後に起きる火災を絶対に起こしてはいけません。 - 電気、水道が止まる
大きな地震が発生すると、私たちの暮らしを支える電気や水、ガスや電話などが、長時間にわたって使えなくなり、不自由な生活が予想されます。阪神・淡路大震災では、水道が2ヶ月間、都市ガスが3ヶ月間にわたり止まっていた地域もあります。
炊事、洗濯、入浴、トイレなどの日常生活が通常どおり行えなくなる場合もあります。 - 避難所での生活
阪神・淡路大震災では約24万棟の住宅が全半壊しました。災害により住む所を失った人や、水道、都市ガスなどが止まり自宅で生活できない人たちのために、避難所や仮設住宅が提供されます。阪神・淡路大震災では、最も多い時には約32万人の人が1,000箇所以上の避難所で不自由な生活をしました。
また、約48,000戸の仮設住宅が建設され、延べ54,000人の入居者が利用しました。
住宅の再建問題、まちの復興対策は、被災地にとって大変重要な問題であり、災害が起こる前よりもより良い生活を送ることのできる地域づくりを目指した取り組みが、今も続いています。
3 地震の揺れと被害
気象庁は、地震の揺れと被害の関係について「震度階級」を定めています。
震度は、地震の直後に発表され、テレビ、ラジオなどで、速報されます。災害時の行動をとる際の参考にしましょう。
気象庁震度階級
- 震度0
人は揺れを感じない。 - 震度1
屋内にいる人の一部がわずかに揺れを感じる。 - 震度2
屋内にいる人の多くが揺れを感じる。電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。 - 震度3
屋内のほとんどの人が揺れを感じる。
棚の食器類が音を立てることがある。 - 震度4
眠っている人のほとんどが目を覚ます。座りの悪い置物が倒れることもある。歩行中の人も、揺れを感じる。 - 震度5弱
行動に支障を感じる人もいる。戸棚の物が落ち、家具が移動することもある。窓ガラスが割れることがある。補強していないブロック塀が崩れることがある。 - 震度5強
非常な恐怖を感じ、多くの人が行動に支障を感じる。タンスなどの重い家具や据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。自動車の運転は困難となる。 - 震度6弱
立っていることが困難になる。固定していない重い家具の多くが移動、転倒し、開かなくなるドアが多い。建物で壁のタイルや窓ガラスが破損落下する。 - 震度6強
立っておれず、はわないと動けない。固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒し、戸がはずれて飛ぶことがある。補強されていないブロック塀がほとんど崩れる。 - 震度7
揺れにほんろうされる。ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。補強されているブロック塀も破損するものがある。