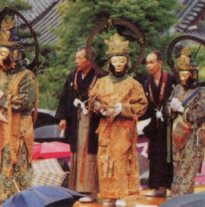|
|
題目立(奈良市)
上深川の氏神八柱神社に伝わる祭礼で、国の重要無形民俗文化財に指定されている能の源流にあたる伝統芸能です。室町時代にはすでに行われていました。
毎年、10月12日、秋祭の奉納行事として、源平合戦を題材にした「厳島」「大仏供養」「石橋山」の謡を、音楽も所作も伴わずに独特の節回しで順番に演じていきます。
|
 |
|
|
土舞台(桜井市)
「日本書紀」推古20年(612年)に百済の人、味摩之(みまし)が呉で「伎楽舞(くれのうたまい)」を学び、これを聖徳太子がご覧になり、この地で少年を集めて習わしめたといわれています。土舞台は、日本初の国立演劇研究所が設置された所であると伝えられています。
|
 |
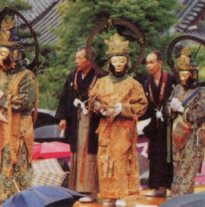 |
|
聖衆来迎練供養会式(葛城市)
恵心僧都が大衆を浄土信仰に導くために始めたものといわれています。二十五菩薩に扮した人たちが、中将姫を蓮台の上に乗せて浄土へ導くという、来迎引接のさまを演劇的にあらわした宗教行事で、毎年5月14日に當麻寺境内で行われています。
|
 |
 |
|
惣谷狂言(五條市)
県の無形民俗文化財に指定されている地狂言で、1月25日に惣谷の天神社で公開されています。昭和33年に約半世紀ぶりに復活し、「鐘引狂言」「鬼狂言」「狐釣狂言」など8曲が伝わる、素朴でおおらかな狂言です。もとは隣村篠原と同様な踊りも伝えられていました。
|
 |
 |
|
面塚(川西町)
能楽観世流発祥伝承地を記念して建造されました。先代宗家二十四世観世左近師の直筆により「観世発祥之地」の文字が刻まれた碑も建っています。
|