県民の友 5月号トップページへ
掲載内容

地域の担い手不足がもたらす、さまざまな課題を解決していくには、住民が主体となって話し合い、自ら取り組んでいくことが重要です。
また、地域外からの人材とも協力して取り組むことで、より良い地域づくりが可能となります。

県では、「過疎集落支援総合対策」として、「ふるさと生活圏」が抱える課題とその対策について、住民が話し合うための場である「寄合会」を設け、その話し合いの中で決まった住民主体の活動を支援しています。これまで40の生活圏(22市町村)で取り組まれています。
自治会・各種団体などで、地域の活性化に取り組んでみたいと考えている場合は、市町村または県振興局企画産業課へご相談ください。

田舎暮らしや地域社会への貢献に関心のある都市住民が、県内市町村に移住して、地域おこしに取り組んでいます。活動内容は、イベントの企画・運営、農林水産業への従事、特産品の開発・PRなどさまざまで、隊員の熱意と行動力が地域に大きな影響を与えています。また、任期終了後も県内で就職や起業する隊員も多く、地域の担い手として活躍しています。

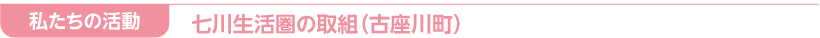
七川生活圏では、65歳以上の高齢者が7割を占める高齢化が進行した地域であり、遠方までの車の運転が困難になるなど、日常生活に不便を感じている住民が増加していました。
そこで、住民同士が支え合い、将来希望を持って暮らし続けることができる地域にするため、閉店した商店を活動交流拠点として蘇(よみがえ)らせ、七川に生育する桜を活用した名所づくりや買い物バスの運用、若者移住者を呼び込む環境整備や情報発信に取り組んでいます。

名所づくりのために桜を植樹

買い物バスの運用で便利に

地域の活動交流拠点が憩いの場に
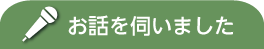

七川ふるさとづくり協議会 会長 下山 隆正 さん
住民の高齢化が進み、集落の維持が難しくなってきました。若者の力で地域を活性化しようと、地域おこし協力隊に来てもらい、3人の隊員が活動し、活気が出てきました。活動交流拠点には住民が集まり、憩いの場として賑(にぎ)わっています。
今後は、より元気な地域になるよう、空き家を確保するなど移住者の受入にも力を入れていきます。