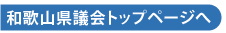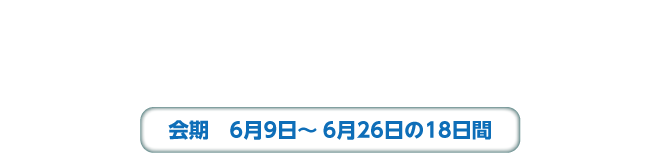

●副議長の選挙…6月10日
●委員及び正副委員長の選任…6月10日(常任委員会、予算特別委員会及び議会運営委員会)
●関西広域連合議会議員の選挙…6月10日
質問議員 16人 |
||||||
6月17日(水)
藤山 将材
秋月 史成 高田 由一 中 拓哉 |
6月18日(木)
坂本 登
長坂 隆司 佐藤 武治 岩井 弘次 |
6月19日(金)
玄素 彰人
林 隆一 杉山 俊雄 鈴木 德久 |
6月22日(月)
北山 慎一
谷口 和樹 玉木 久登 新島 雄 |
|||

| 項目 | 件数 | 概要 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予算案件(知事提出) | 3件 | 令和2年度和歌山県一般会計補正予算 等 | 可決 |
| 条例案件(議員提出) | 1件 | 議会の議員の議員報酬の特例に関する条例 | |
| 条例案件(知事提出) | 7件 | 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 等 | |
| 人事案件( 〃 ) | 10件 | 和歌山県監査委員の選任につき同意を求めるについて 等 | 同意 |
| その他案件( 〃 ) | 3件 | 財産の取得について 等 | 可決 |
| 諮問( 〃 ) | 1件 | 退職手当の支給制限に対する審査請求に関する諮問について | 知事の決定書(案)は適当と認める |
| 請願 | 1件 | 地域住民の医療・福祉を支える医療・介護従事者への支援を国に求める意見書の提出を求める請願書 | 不採択 |
| 意見書 | 4件 | 防災・減災、国土強靱化対策と地域経済復興に向けた社会資本整備の更なる推進を求める意見書 | 可決 |
| 新型コロナウイルス感染症対策の推進を求める意見書 | |||
| インターネットによる誹謗中傷を防止する対策を求める意見書 | |||
| 地方財政の充実・強化を求める意見書 |
主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、次のとおりです。(要約)
| 今後の感染症対策 | |
問 |
第2波、第3波に向けた備えはどうか。 |
答 |
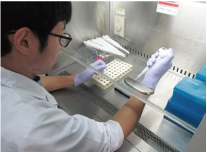  県環境衛生研究センター 保健医療行政の要は、今後も感染者の早期発見・早期隔離・徹底した行動歴調査のいわゆる「和歌山方式」の実行にあると考えます。 早期発見に不可欠な検査体制の強化のため、県環境衛生研究センターにPCR検査機器を増設します。また、地域の中核病院へPCR検査機器を配備することにより、手術前患者や分娩前妊婦に検査を実施できる環境を整備します。 加えて、重症化リスクの高い高齢者等が利用する福祉施設等の環境の整備やマスク・消毒液などの購入等の経費を支援するなど、保健医療体制の装備を強化して、再流行に備えます。 |
| 事業継続支援金の支給条件 | |
問 |
県の事業継続支援金の支給対象を売上げが50%以上減少した事業者に限定した根拠は何か。 |
答 |
速やかな支給と申請書類の簡素化のため、売上げ50%以上減少を支給条件とする国の持続化給付金と同様の扱いにしています。 県としては、減少率が50%以上に至らない事業者に対しても、事業継続推進補助金や、無利子の県融資制度などの活用を、産業別担当者制度などを通じて支援していきます。 |
| 今後の観光振興策 | |
問 |
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた観光事業者への支援と今後の観光振興策についてはどうか。 |
答 |
売上げが減少した事業者に事業を継続するための支援金や補助金の給付をはじめ、5月には新たな融資枠など県独自の包括的支援策を創設し、本定例会では融資枠の拡大や観光客の受入環境設備に対する補助を提案しています。 新型コロナウイルス感染症の流行沈静化の見通しが確認できた段階では、国が予定している「Go To トラベル」事業とも連携し、収束状況に応じて、対象地域を段階的に拡大しながら、さらなる誘客につなげていきます。 |
| バイローカル運動 | |
問 |
急激に売上げが減少している観光業や飲食業に対してバイローカルという視点からどう考えているのか。 |
答 |
地域内で利用できるクーポン券の発行などの支援策により、地域内の消費を活性化させるバイローカル運動が地域に根付くことは、素晴らしい取組です。事業者が、バイローカル運動に取り組むに当たり、事業継続推進補助金や県民リフレッシュ販売促進事業の取組により、地域の消費を喚起し、地域経済の活性化を図っていきたいと考えます。 |
| 今後のスポーツ大会の開催と支援 | |
問 |
県高等学校総合体育大会などの中止に伴う代替大会等の開催と県の支援についてはどうか。 |
答 |
県教育委員会では、感染症予防をはじめ、熱中症防止等への対策のために部活動再開のガイドラインや、今後の感染状況と大会開催についての目安を示しています。 今後、開催が検討されている県独自の大会等において、安全・安心な運営となるよう様々な面で支援をしていきます。 |
| 学校における熱中症対策 | |
問 |
学校では新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、どのような熱中症対策を行うのか。 |
答 |
各学校では、空調設備の小まめな温度調節と、換気の両立を図ります。 また、マスク着用時にも、小まめに水分補給を行うとともに、登下校時や体育の授業などで、熱中症等が危惧される場合には、児童生徒の間隔を十分に確保した上でマスクの着用を求めないといった対策を行います。 さらに、日頃の体温測定や健康観察により、引き続き健康管理を徹底していきます。 |
| 学習の遅れ | |
問 |
臨時休業措置による学習の遅れを取り戻すために、教員OBを活用してはどうか。 |
答 |
本県では、再任用教員、臨時的任用講師、非常勤講師として既に約750名を任用しています。 今後は、臨時休業で生じた学習の遅れを取り戻すため、補充授業等を行う学習指導員等の配置を考えているところです。 こうしたところにも、退職教員をはじめとして多くの方々に協力をいただきながら、子供たちの学習を強力に支援していきたいと考えます。 |
| 県道白浜久木(ひさぎ)線の整備 | |
問 |
整備の進捗状況と今後の取組についてはどうか。 |
答 |
 久木トンネル 白浜町庄川(しゃがわ)から久木間のうち通行不能区間約4.7キロメートルの解消を図るため、先に事業化した久木側は、久木トンネルが完了するなど、橋梁工事や工事用道路の整備を進めています。また、庄川側では、出合橋から山中橋までの間において、工事用車両の進入路を確保するための路側工事を進めています。 現地の地形が急峻で、特に峠の前後区間では急勾配となることから、現道の利用は困難と判断し、新たにトンネルを含めたルートにより安全な走行が可能となるよう検討しており、今後、用地取得や工事を推進していきます。 |
| 緊急浚渫(しゅんせつ)推進事業 | |
問 |
令和元年台風第19号による災害を受けて、国が財政措置をすることとなった河川等の浚渫を行う事業に、県としてどのように取り組むのか。また、田辺市・西牟婁地方では、どのような箇所を対象とするのか。 |
答 |
現時点では、県管理53河川、二川ダム、18箇所の砂防施設で事業を計画し、今年度は人家への影響が大きく土砂の堆積が著しい箇所から取り組んでおり、約10億円の事業執行を予定しています。なお、田辺市・西牟婁郡では、富田川などの8河川や大塔川の砂防堰堤を予定しています。 |
| 熊野川の濁水軽減対策 | |
問 |
熊野川における濁水軽減対策の現状はどうか。 |
答 |
各機関において、発生源対策として崩壊地ののり面対策、河道への土砂流出防止対策及び河道内の堆積土砂の撤去を推進しています。また、ダム貯水池での対策として電源開発㈱が風屋ダム及び二津野ダムで濁水防止フェンスの設置等を行いました。なお、二津野ダムの排砂バイパスについては、貯水池への土砂堆積の抑制や、洪水後の濁水の下流への早期排出のみならず、治水上の効果も期待できる構造にならないか同社に働きかけていきます。 |
| 切目王子の世界遺産追加登録 | |
問 |
切目王子(印南町)の世界遺産追加登録について、知事の所見はどうか。 |
答 |
 切目神社(切目王子) 学術的にも大変価値のあるものと認識しており、まずは、世界遺産登録の前提となる国の史跡指定を目指し、熊野参詣道の紀伊路のほかの候補地とともに、史跡指定の後、機が熟せば、世界遺産の追加登録を目指します。 |
| 歴史物語のアピール | |
問 |
本県の歴史物語をさらに深く追求し、県内外にアピールしてはどうか。 |
答 |
わかやま歴史物語
神話の時代から近代に至るまでの県内各地に点在する歴史、それにまつわる秘話、インスタ映えスポット、人・文化・食・温泉・体験など、和歌山をまるごと楽しめるストーリーを「100の旅モデル」として紹介しています。 わかやま歴史物語のページへリンク 「わかやま歴史物語」の特別企画として、現在、古事記、日本書紀ゆかりの地を旅する「わかやま記紀の旅 周遊スタンプラリー」を実施しています。 また、今後改訂を予定している「わかやま歴史物語」のストーリーの拡充を図り、知的好奇心を満たす和歌山の旅を県内外にアピールしていきたいと考えます。 |
| 高校入試の在り方 | |
問 |
学習状況が各学校で異なることを踏まえ、高校入試の出題範囲等を早期に示すべきではないか。 |
答 |
現中学3年生には、夏季休業期間の短縮により授業時間を確保し、過度の負担なく、学習すべき内容を卒業までにきちんと学べるよう計画するとともに、増員した教員や学習指導員などを指導に充て、きめ細やかな対応をしていきます。 今後、各市町村教育委員会を通じて、各中学校の学習状況等を把握し、よりよい方法を講じていきます。 |
| 田辺・西牟婁地域の県立高校の定員 | |
問 |
昨年度の県立高校入試結果の総括と田辺・西牟婁地域の県立高校の定員についてはどうか。 |
答 |
昨年度の高校入試における全日制課程の本出願倍率は、0.90倍となりました。みなべ、田辺・西牟婁地域においては、志願者が定員を超過した学校があったものの、多くの生徒が行きたい学校に進学したものと考えています。 令和3年度の県立高等学校募集定員については、地域の子供たちの人数や各学校・学科の特徴を踏まえ、10月末に総合的に判断します。 |
| 指定管理者制度 | |
問 |
指定管理者制度について、指定管理期間を5年から3年に変更したのはなぜか。また、今後5年に見直す考えはないのか。 |
答 |
指定管理者制度
民間事業者のノウハウ等を活用することにより、より効率的で効果的な管理運営を行い、住民サービスのさらなる向上と行政コストの縮減を図ることを目的として、公の施設の管理運営を、地方自治体が指定した「指定管理者」が行う制度です。 指定管理期間については、急速な時代の動きの中で、県民ニーズの変化に応じた業務の見直しを行うため、原則3年としてきたところです。現在は、維持管理が主たる業務となる施設は原則3年を維持する一方、創意工夫の余地が大きいソフト事業の業務割合が高く、指定管理者のノウハウ蓄積に時間を要する施設は例外的に5年としていますが、ご指摘を踏まえ、今後よく考えていきます。 |
| 農業後継者の育成 | |
問 |
農業次世代人材投資事業における親元就農への支援と、後継者育成の今後の取組について県はどう考えているのか。 |
答 |
県では、農業次世代人材投資事業の要件を満たし資金の交付が受けられるようサポートしてきた結果、資金の交付を受けた方の約6割が、親元就農した農家の子弟となっています。 今後、後継者育成のため、農林大学校等での人材養成をはじめ、経営力向上のための農業経営塾の開催に加え、所得向上を図るための生産・販売対策に取り組んでいきます。 |