
| 徳島県 |
 |
丈六寺(徳島市) 「阿波の法寺」とも呼ばれる古刹。白雉元年(650)創建と伝えられ、室町時代末期、阿波国守護細川成之が曹洞宗の寺院として再建、今の伽藍の姿になったといわれています。 徳島県内最古の建物である丈六寺山門や聖観音座像など重要文化財も多数所蔵。観音像の大きさは寺の名の由来ともなった1丈6尺、いわゆる丈六仏です。
|
||||||
 |
霊山寺(鳴門市) 天平年間、聖武天皇の勅願により行基が開基。後に弘法大師が四国の八十八の霊場を訪れた際に、釈迦如来が説法されていた霊山を日本に移すという意味でこの名を付けました。 四国霊場の発願の寺、一番さんなどとして人々に親しまれています。
|
||||||
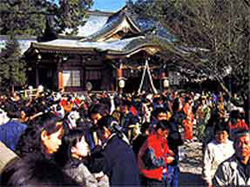 |
大麻比古神社(鳴門市) 「大麻(おわさ)はん」の名で親しまれ、厄除け・交通安全の神様として県内外に知られる年中参拝客が多い県下一の格式高い神社。祭神は農業、産業の守り神である大麻比古命と、交通安全厄除けの神の猿田彦命が祀られています。 厳粛で神聖な雰囲気を漂わす境内には、鳴門市内唯一の異様な風貌をした狛犬が座しています。
|
||||||
 |
津峯神社<延喜式内社>(阿南市) 724年創建された古社。県南の霊峰津峯山上にあり、阿波の松島(橘湾)を臨む絶景の地でもあります。主祭神は、賀志波比賣大神(かしわひめのおおかみ)。延命長寿を司る神様で、危篤の病人といえども、その血縁者、知人等が代参祈願すれば寿命を延ばし、一日に一人はお助け下さるとの御神徳。また、武運の神としても、阿波太守や富岡城主などからも崇敬を集めていたとか。その他、開運招福、交通安全、海上安全の守護神で、境内社の恵美須大神は、阿波七福神の一神。
|
||||||
 |
最明寺(美馬市) 鎌倉時代、執権最明寺入道北条時頼が来訪し住職と談論に日を重ねたという伝説が残る寺。後に、この伝説を元に水戸黄門諸国漫遊伝説がつくられたとされています。不動明王を信仰の中心とする四国三十六不動霊場の札所として、さらには観音さまの霊場・阿波西国三十三観音霊場の札所として今も信仰を集めています。 国指定重要文化財の毘沙門天立像(平安後期)などを所蔵。
|
||||||
 |
法音寺(藍住町) 阿波西国第八番観音霊場で旧吉野川のほとりにある古寺。応永年間(1394年~1427年)に高野山の僧、宥快上人が開基しました。除災招福の御利益があり、広く信仰を集めています。別名、牡丹寺。境内には沢山の牡丹が栽植されており、毎年花の季節には、人々の目を楽しませてくれます。吉野川流域「牡丹の寺」四カ寺巡りで、神宮寺、観音寺、萬福寺と共に知られています。本尊の不動明王橡は、行基菩薩作。
|
||||||
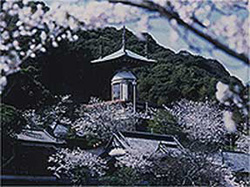 |
薬王寺(美波町) 四国88ヶ所第23番礼所。815年、弘法大師が42斎の厄除け祈願のため、薬師如来座像を刻んで安置したことが起源とされています。仁王門をくぐると厄坂があり、この女厄坂33段、男厄坂42段、男女厄坂61段は、男女の厄年に因んで造られおり、石段の下には薬師本願経を一石一字にしるして埋められています。厄除の寺。
|
||||||
| 古の交流の海|大阪府|兵庫県|奈良県|和歌山県|徳島県|香川県|高知県| |
