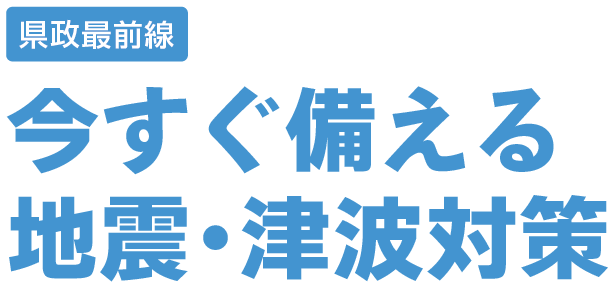
危機管理消防課 電話073-441-2260
防災企画課 電話073-441-2271
災害対策課 電話073-441-2262
(3課共通) ファックス073-422-7652

令和6年1月1日、石川県で最大震度7の揺れを観測した能登半島地震において、多くの死傷者や住家への被害が発生し、今なお避難生活を余儀なくされている方もおられます。
半島という地理的条件や人口規模・構成等が能登半島と類似している和歌山県では、南海トラフ地震が、今後30年以内に70〜80パーセントの確率で発生すると予測されています。
県では、能登半島地震において明らかになった幹線道路の寸断による集落の孤立や避難所の環境改善等の課題解決に加え、地震や津波等の災害から県民の皆さんの命を守るため、防災DXや災害情報の発信、住宅の耐震化など、あらゆる対策を進めていきます。
県民の皆さんも、防災に関する情報を入手し、今後起こるかも知れない災害に備えましょう。
●死者・負傷 死者 281名 負傷者 1,326名(令和6年7月1日14:00 消防庁)
●住家被害 全壊 8,429棟 半壊 21,370棟 床上・床下浸水 25棟
一部破損 97,510棟(令和6年7月1日14:00 消防庁)
●避難者数 最大51,605人(内閣府)
●停電 最大約40,000戸(経済産業省)
●断水 最大約136,440戸(国土交通省)
●死因(石川県内) 約8割が「家屋倒壊」(令和6年7月4日第15報まで 石川県)
●孤立集落(石川県内) 最大24地区 3,345人※(石川県)
※令和6年1月19日14:00第57報で孤立集落の解消を発表
 緊急消防援助隊として被災地で人命救助
緊急消防援助隊として被災地で人命救助和歌山市消防局 警防課
消防司令補 大林 正幹さん
輪島市で家屋の倒壊や地すべりの被害に遭った方の救助活動を行いましたが、要救助者のいる被災地への道路が崖崩れや陥没等で通れず、活動場所に到着するまで多くの日数と時間を要しました。現地に着いても、救助に必要な重機が入れないなど、迅速な救助活動ができず、大変もどかしい状況でした。
本県も能登半島と同じ半島地域であり、道路網が脆弱(ぜいじゃく)な地域もあるため、地震や津波により幹線道路が寸断されることが想定されます。そうなると、救助隊はすぐには駆けつけられませんし、救援物資もすぐには届きません。そのため、まずは自分の命は自分で守ることが大切です。住宅の耐震化や備蓄を進め、避難ルートを確認しておくなど、自分の命を守るために必要な情報を入手して日頃から災害に備えてください。また、助け合いにより困難を乗り越えられることもあります。地域の住民同士のつながりも大事にしてください。


 孤立集落対策を推進
孤立集落対策を推進串本町 総務課 防災・防犯グループ
主任 岡田 真一さん
串本町を含む紀南地域では、地震発生時に海沿いを通る幹線道路が津波や土砂崩れ等で寸断され、孤立集落の発生が予想されます。集落の孤立が長期化すると、傷病者の移送や物資の輸送が大幅に遅れ、命の危険にさらされます。能登半島地震で発生した孤立集落の問題は決して他人事ではなく、対策を進めていかなければなりません。
能登半島地震では、孤立集落の救助・支援にヘリコプターやドローンが活用されましたが、発災直後にすぐに向かうことはできません。集落等の地域の方々が協力して備蓄や訓練を積むなどして、支援が入るまでの孤立状態に備えておく必要があります。備蓄では、水や食料等はもちろん、簡易トイレや蓄電池・発電機も必要です。通信訓練や避難訓練は、一回では身につかないため、継続して行うことが重要です。発災時に少しでも円滑に対応できるよう、地域で話し合い、災害への備えを進めましょう。