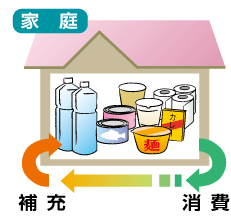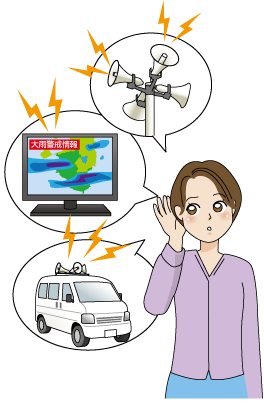| 問い合わせ:県庁建築住宅課 電話073-441-3214 |
|
住宅耐震化
|
平成28年4月に発生した熊本地震では、家屋の倒壊により多くの方が犠牲になりました。南海トラフで起こる地震は、震源地が紀伊半島に近く、非常に強い揺れとなることが予想されるため、被害を軽減するためには住宅の耐震化が重要となります。
県では、補強設計と改修工事をセットにした定額補助などにより、住宅の耐震化を支援しています。
県民の皆さんも、住宅の耐震化や家具の固定など、地震に備えた対策をお願いします。
(対象は昭和56年5月以前に建築された住宅です。市町村によっては、木造住宅は平成12年5月以前に建築されたもの)

熊本地震で倒壊を免れた家屋(左)と倒壊した家屋(右) |
|
| 耐震診断 |
【木造住宅】 住宅耐震診断士による診断が無料
【非木造住宅】 耐震診断費の2/3を補助
補助限度額8万9千円 |
 |
| 設計と改修工事を一体的に支援 |
| 耐震補強設計+耐震改修 最大116万6千円の補助
|
県・市町村 定額補助66万6千円
+
国 耐震改修費の40%を補助 補助限度額50万円 |
※定額補助 補助対象経費(設計費、工事費)の額に
関わらず、一定金額を補助対象経費の範囲で交付 |
 |
補強設計15万円、耐震改修85万円の場合 |
| |
経 費 |
補助金等 |
自己負担 |
補強設計
+
耐震改修 |
100万円 |
100万円 |
0万円 |
|
※補助の内容は市町村によって異なります
詳しくは市町村耐震相談窓口までお問い合わせください |
| 空き家の耐震化について |
普段は人が住んでいない空き家も、地震による倒壊により隣家に被害を与えたり、避難路を塞いだりする恐れがあります。
空き家についても一定の条件を満たせば、耐震改修の補助を受けられます。
県では定期的に無料の相談会を開催していますので、お気軽にご相談ください。
詳しくは県庁建築住宅課まで。 |
|
|
大規模建築物の耐震化
|
耐震改修促進法により耐震診断が義務化された建築物のうち、避難所としての機能を有し、被災後の避難生活者を一定期間受け入れることができる大規模建築物(ホテル・旅館)などを対象に、平成25年に全国に先駆けて耐震改修に対する補助制度を創設しました。
これらの大規模建築物の耐震化は、令和2年3月末までに完成する予定です。
|
|
耐震ベッド・耐震シェルター
|
住宅の耐震より安価で、寝床や居住スペースの安全が確保できる、 耐震ベッドや耐震シェルターの設置費用を補助しています。 耐震ベッドや耐震シェルターの設置費用を補助しています。 |
対 象 ──────────────────────────────
|
●耐震診断の結果、耐震性を有しないと判断された木造住宅
●申請者多数の場合は高齢者、障害者を優先 |
| 補助率と補助額 ───────────────────────── |
| ●設置費用の3分の2 ●補助限度額26万6千円 |
設置費用に係る経費の例
| 経費 |
補助金 |
自己負担 |
| 40.0万円 |
26.6万円 |
13.4万円 |
|
※詳しくは、市町村耐震相談窓口へお問い合わせください。 |
|
|
ブロック塀の安全対策
|
熊本地震や大阪府北部の地震では、ブロック塀が倒壊するなどの被害が発生しています。基準を満たさないブロック塀や老朽化したブロック塀は、倒壊により人的被害や避難路の寸断が発生する恐れがあり大変危険です。
県では、建築士関係団体の皆さんのご協力により、地域毎にブロック塀の安全性に関する相談員を配置していただき、名簿を県庁建築住宅課のWEBサイトに掲載しています。改修方法などに関する相談にご対応いただけますので、ぜひ活用してください。
また、市町村によっては、ブロック塀の撤去や補強に係る費用の補助制度を設けていますので、詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。 |
 |
| 熊本地震で倒壊したブロック塀 |
| |
家具固定
|
|
問い合わせ:県庁防災企画課 電話073-441-2271
|
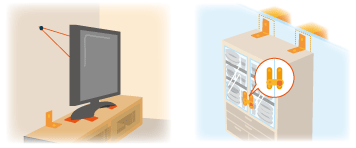 L型金具等による家具の固定や、家具の置き方を工夫することで家具の転倒時の被害を軽減しましょう。
L型金具等による家具の固定や、家具の置き方を工夫することで家具の転倒時の被害を軽減しましょう。
また、県では家具固定施工事業者登録制度を設けています。施工事業者をお探しの際にはご活用ください。 |
「出張!減災教室」 「出張!県政おはなし講座」
問い合わせ:県庁危機管理・消防課 電話073-441-2260
「出張!減災教室」では家庭や地域での防災意識を高めるため、地震体験車による地震体験や、避難所運営を体験できるゲーム、家具固定や住宅耐震化に関する実演・講座を実施しています。
また、「出張!県政おはなし講座」では県職員が直接会場に出向き、防災・減災対策の取組を説明します。
学校の防災・減災教育、自治会や企業の研修などにご利用ください。
|
|
日頃からの備え
|
| 非常持出品 |
|
非常備蓄品 |
| 避難するときにまず最初に持ち出すべきものとして、避難バッグにひとまとめにし、すぐに持ち出せるよう置き場所を決めておきましょう。 |
|
救援活動が受けられるまでの間に必要な1週間分程度の水や食料などを、家屋が被災しても取り出せる場所に保管しておきましょう。 |
 〔非常持出品の例〕 〔非常持出品の例〕
・非常食 ・飲料水 ・救急医療品 ・常備薬 ・ヘルメット・現金
・モバイルバッテリー
・携帯ラジオ ・懐中電灯 など |
|
 〔非常備蓄品の例〕 〔非常備蓄品の例〕
・備蓄食品 ・備蓄飲料
・毛布 ・簡易トイレ
・卓上コンロ など |
|
|
「ところてん方式」で備蓄も楽々!
|
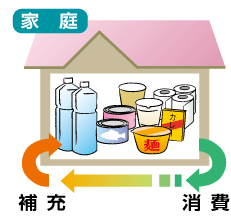 |
| 日頃から使用している消耗品・衛生用品・食材などを多めに買っておき、消費したら補充する「ところてん方式」で家庭での備蓄が簡単にできます。 |
備蓄食品の選び方などについては、農林水産省のWEBサイトも参考にしてください。
家庭備蓄ポータルのページへリンク
|
|
|
 |
|
市町村が発令する避難情報を確認!
|
|
問い合わせ:県庁防災企画課 電話073-441-2284
|
近年、全国的に集中豪雨が頻発し、河川の氾濫や土砂崩れなどの大きな災害が発生しています。本県でも平成23年の紀伊半島大水害など、台風や集中豪雨による土砂災害、浸水被害が発生しています。
県では、このような風水害から命を守るため、市町村が避難勧告などの避難情報を発令する際の判断を早期かつ的確に実施できるよう、平成24年に「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成のモデル基準」を策定しました。この基準は、市町村の避難勧告等の発令に遅れが生じないよう、市町村が判断しやすく実用性の高いものとしており、現在、国が示す避難判断を行うためのガイドラインにも取り入れられています。
また、県では日本気象協会の降水予測情報をもとに、最大51時間先までの降水予測を行う独自の気象予測システムを整備しています。これらをもとに市町村では的確な避難情報の発令判断に役立てていますので、市町村から避難勧告等の避難情報が発令されたときは、適切な避難行動をとってください。
なお、今年の6月から市町村が発令する避難情報は、「警戒レベル」を用いてお伝えすることとなっています。
|
|
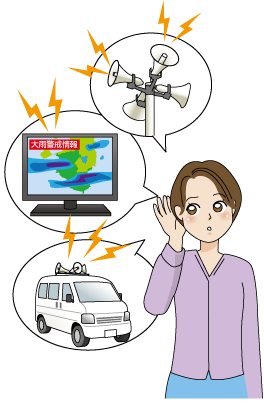 |
気象に関する情報、県が発信する防災情報や市町村が発令する避難勧告等の避難情報などに十分注意して、早めの避難を行い、自ら命を守りましょう。
また、日頃から避難場所等を確認しておきましょう。 |
|
|
早期復旧に関する協定(関西電力、NTT西日本)
|
問い合わせ:県庁災害対策課 電話073-441-2261 県庁情報政策課 電話073-441-2405
県庁道路保全課 電話073-441-3110
|
| 平成30年9月の台風第21号では、倒木や土砂崩れなどにより大規模な停電や通信障害が発生し、長期間にわたって生活に混乱が生じることとなりました。 |
復旧までに時間を要したことを受け、県では、関西電力㈱、西日本電信電話㈱それぞれと停電や通信障害の復旧作業に関する協定を今年4月に締結しました。
今後、大規模な停電・通信障害が発生した場合には、県が両社の要請に基づき復旧作業の支障となる倒木・土砂などの除去作業を支援することで、より迅速な復旧につなげます。 |
関西電力の停電情報がWEBサイトやスマートフォンのアプリで確認できます。
関西停電情報のページへリンク |
|
|
土砂災害から身を守るための3つのポイント
|
|
問い合わせ:県庁砂防課 電話073-441-3171
|
(1)台風が来る前! 土砂災害警戒区域など、地域の土砂災害のおそれのある箇所を普段から確認する。
(2)雨が降り始めたら! 雨雲の動きと土砂災害警戒情報に注意する。
(3)豪雨になる前に! 大雨時や土砂災害警戒情報が発表されたときは、早めに近くの安全な場所に避難する。
また、夜間に大雨が予想されるときは、暗くなる前に避難する。
|
|
土砂災害警戒区域および特別警戒区域などを確認できます。 わかやま土砂災害マップのページへリンク
|

 耐震ベッドや耐震シェルターの設置費用を補助しています。
耐震ベッドや耐震シェルターの設置費用を補助しています。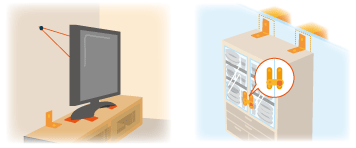 L型金具等による家具の固定や、家具の置き方を工夫することで家具の転倒時の被害を軽減しましょう。
L型金具等による家具の固定や、家具の置き方を工夫することで家具の転倒時の被害を軽減しましょう。