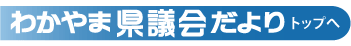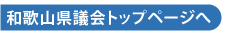現在の位置:トップページ > 県議会からのお知らせ > 県議会だより > 2月定例会号 >平成30年2月定例会概要

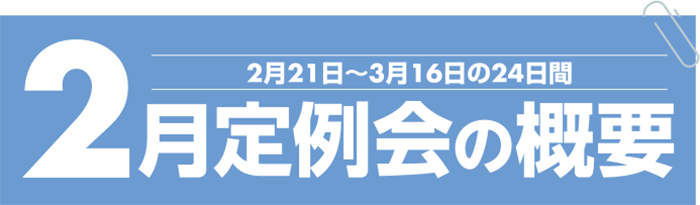
| 一般質問議員(20人) | ||||
| 3月2日(金) | 3月5日(月) | 3月6日(火) | 3月7日(水) | 3月8日(木) |
| 山田 正彦 | 新島 雄 | 濱口 太史 | 森 礼子 | 藤山 将材 |
| 多田 純一 | 岩井 弘次 | 藤本眞利子 | 岩田 弘彦 | 浦口 高典 |
| 雑賀 光夫 | 玉木 久登 | 谷口 和樹 | 山下 直也 | |
| 泉 正徳 | 片桐 章浩 | 中村 裕一 | 井出 益弘 | |
| 川畑 哲哉 | 立谷 誠一 | |||
会期中の主な動き
| ■特別委員会の開催 | ||
| ●防災・国土強靱化対策特別委員会 | ………………………………………… | (3/5) |
| ●人権・少子高齢化問題等対策特別委員会 | ………………………………………… | (3/6) |
| ●行政改革・基本計画等に関する特別委員会 | ………………………………………… | (3/8) |
議案等の議決結果
| 項 目 | 件数 | 件 名 | 結 果 |
| 予算案件(知事提出) | 32件 | 平成30年度和歌山県一般会計予算 等 | 可決 |
| 条例案件( 〃 ) | 42件 | 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例 等 | |
| 人事案件( 〃 ) | 2件 | 和歌山県教育委員会の教育長の任命につき同意を求めるについて 等 | 同意 |
| その他案件( 〃 ) | 21件 | 平成30年度建設事業施行に伴う市町村負担金について 等 | 可決 |
| 意見書 | 2件 | 国民健康保険における子供の均等割に軽減措置の導入を求める意見書 | 否決 |
| 浸水被害の回避等を目的とした断面確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保等を求める意見書 | 可決 |
主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、次のとおりです。(要約)
知事の政治姿勢
| 今秋、知事は3期目の任期満了を迎えるが、引き続き県政を担う強い意志があるのか。 |
| 課題山積の和歌山県ですから、知事たる地位にある私は、新たな県長期総合計画に沿ってこれまで以上に全力で職務に当たらなければなりません。しかしながら、私の任期もあと1年を切りました。県民の皆様がお許しくださるなら、ぜひもう1期、知事として県政を担当させてもらいたいと思います。 |
県都和歌山市の都市づくり
| 知事はコンパクトシティ計画を策定した市町を積極的に応援すると言っているが、和歌山市が進めている都市づくりに対する見解はどうか。 |
| 和歌山市では、市街地再開発事業を活用した「まちなか居住」の誘導や大学の誘致など、にぎわいのあるコンパクトな都市づくりを進めており、非常によい雰囲気になってきています。これからは機能の集積なども行っていけばよいと思っており、県として引き続き応援・協力をしていきます。 |
新六ヶ井堰の全撤去
| 浸水被害のあった地元から新六ヶ井堰の完全撤去と堰上流部の河床掘削の要望があるが、どう考えているのか。 |
| 国の紀の川水系河川整備計画では、下流部において一定の整備が完了していることを受け、岩出狭窄部対策や藤崎狭窄部対策など中上流部の整備が位置づけられており、新六ヶ井堰の完全撤去や堰上流部の河床掘削は次の課題となっています。国に現在実施中の岩出狭窄部対策などの着実な事業進捗を働きかけるとともに、早期撤去等の要望があることも確実に伝えていきます。 |
高齢者の就労支援
| 高齢者の就労支援についてどのように取り組んでいるのか。 |
健康長寿日本一「わかやま」の実現
| 「健康長寿日本一わかやま」の実現に向けた取組と知事の決意はどうか。 |
 「わかやま健康と食のフェスタ」や健康づくり運動ポイント事業、健康推進員に関する施策を一層進めるとともに、毎年度、健康増進計画の達成状況を検証します。県民がいつまでも元気で暮らせるよう、新しい施策も取り入れ、健康づくり県民運動を積極的に展開していきます。 「わかやま健康と食のフェスタ」や健康づくり運動ポイント事業、健康推進員に関する施策を一層進めるとともに、毎年度、健康増進計画の達成状況を検証します。県民がいつまでも元気で暮らせるよう、新しい施策も取り入れ、健康づくり県民運動を積極的に展開していきます。 |
社会的不適応問題
| 社会的不適応行動を起こす個人へのアプローチを丁寧に行った結果、大きな成果を出している佐賀県のNPO法人の取組についての所見を伺いたい。 |
| 本県では、不登校、ひきこもり、ニート対策が、佐賀県のように1つの法人で実施されていないことから、関係機関が連携し、それぞれの対策を切れ目なくつなぐことが重要となっています。このことから相談員のスキルアップや関係機関と協働した訪問支援の強化など若者の自立支援を充実させたいと考えます。 |
学校における指導死の問題
| 全国的に問題になっている指導死という問題についてどう考えているのか。 |
| 教職員の厳しい指導や叱責、体罰等が原因で子供の尊い命が失われることは、絶対にあってはならないことです。児童生徒の人格を尊重し、個性を伸ばしながら寄り添い、指導方法等を工夫・改善することが必要と考えます。 |
企業立地の成果と今後
| 知事就任以降における企業立地の成果と今後について伺いたい。 |
| 就任以来、11年余りで181社の企業を誘致しています。県としては、引き続き、工業団地や交通インフラのさらなる整備を行うとともに、全国最高水準の奨励金制度などをアピールし、企業誘致に全力を挙げていきます。 |
在宅育児支援
| 平成30年度新政策における在宅育児支援をはじめとする子育て支援について伺いたい。 |
 県長期総合計画に掲げた、2026年における合計特殊出生率2・00を達成するため、これまでの事業成果を踏まえ、保育料等の無償化の対象を所得制限を設けたうえで第2子まで拡充します。さらに、国においてもまだ検討されていない0歳児を在宅で育児する世帯への経済的支援にも取り組んでいきます。 県長期総合計画に掲げた、2026年における合計特殊出生率2・00を達成するため、これまでの事業成果を踏まえ、保育料等の無償化の対象を所得制限を設けたうえで第2子まで拡充します。さらに、国においてもまだ検討されていない0歳児を在宅で育児する世帯への経済的支援にも取り組んでいきます。 |
第3次がん対策推進計画の目標
| 平成30年度からの第3次がん対策推進計画では、どのような目標を立てているのか。 |
| この計画では、「がんの75歳未満年齢調整死亡率の低減」、「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」、「患者本位のがん医療の実現」、「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」の4つの大目標を設定しています。この計画に基づいて、総合的ながん対策を推進していきます。 |
社会福祉施設における介護人材の確保
| 県内において、介護従事者の1年以内の離職率が高い現状をどう考えるのか。 |
| 平成27年度に実施した本県の独自調査によると、事業所の全従業員数に占める非正規職員の割合が約4割を超え、その離職率が正規職員よりも高いことが主な原因で全国的にも同様の傾向ですが県では、介護職に対する正しい知識の普及に向け保護者や学校の進路指導担当者に啓発していきます。 |
災害時の人工透析提供体制
| 災害時における人工透析患者の把握と透析治療対策はどうか。 |
| 災害時にかかりつけ透析医療機関で治療が可能かなどを案内する「わかやま透析安心メール」システムを平成20年度から運用しています。今後、新規の透析患者の登録を的確に進めていくとともに、災害時に、透析患者が確実にメールの受信・送信ができるよう、繰り返しメール配信訓練を行い、システムの実効性を高めるなど、災害時の人工透析提供体制の確保を図っていきます。 |
車椅子使用者用駐車区画の屋根の設置
| 和歌山ビッグホエールの車椅子使用者用駐車区画において、乗降時雨に濡れないように屋根を設置できないか。 |
特別支援教育の推進
| 障害のある子供に対する個別の教育支援計画「つなぎ愛シート」の活用推進に向けた今後の方策について伺いたい。 |
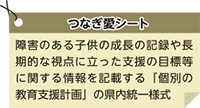 「つなぎ愛シート」については、特別支援学校で既に活用が始まっていますが、市町村教育委員会とも連携を進め、平成30年度からは全ての小中学校の特別支援学級や通級指導教室に在籍する児童生徒に対しても導入される予定です。今後、切れ目のない支援の実現に向け、効果的な活用を進めます。 「つなぎ愛シート」については、特別支援学校で既に活用が始まっていますが、市町村教育委員会とも連携を進め、平成30年度からは全ての小中学校の特別支援学級や通級指導教室に在籍する児童生徒に対しても導入される予定です。今後、切れ目のない支援の実現に向け、効果的な活用を進めます。 |
鯨文化の持続に向けた支援
| 捕鯨の正当性を訴えるための情報発信についてどうか。 |
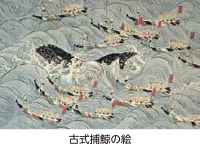 今後も反捕鯨活動は沈静化せず、更なる攻撃も予想されるため、これまで以上に FacebookやTwitterなどの情報媒体やいろいろな機会を活用して、イルカ漁の正当性を発信していきます。 今後も反捕鯨活動は沈静化せず、更なる攻撃も予想されるため、これまで以上に FacebookやTwitterなどの情報媒体やいろいろな機会を活用して、イルカ漁の正当性を発信していきます。 |
第三者行為求償事務の取組強化
| 平成30年度から県も国民健康保険の運営責任者となることを踏まえ、第三者行為求償事務の取組強化に対する意気込みを伺いたい。 |
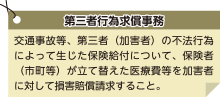 交通事故等により生じた損害の責任は加害者が負うのが当たり前で、市町村は当然、第三者行為求償事務に取り組まねばなりません。これまでも県は市町村の取組に対し財政支援などを行ってきましたが、今後は県が財政運営の責任主体となりますので、より一層積極的に取り組み、国保財政の安定化を図っていきます。 交通事故等により生じた損害の責任は加害者が負うのが当たり前で、市町村は当然、第三者行為求償事務に取り組まねばなりません。これまでも県は市町村の取組に対し財政支援などを行ってきましたが、今後は県が財政運営の責任主体となりますので、より一層積極的に取り組み、国保財政の安定化を図っていきます。 |
水素社会実現に向けた取組
| 関西広域連合では水素エネルギーの利活用の実現化に向けた取組を行っており、県としても取り組む必要があると思うがどうか。 |
| 国や事業者等の動向を注視し、水素社会の環境が整ってきた段階で、遅れが出ないように行動していきたいと思います。 |
木質バイオマス発電
| 木質バイオマス発電は地方創生の一助にもなると期待され、これにより木材需要の拡大が見込まれる中、どのように取り組んでいくのか。 |
| 遠隔操作が可能な油圧式集材機など省力化につながる搬出技術の導入により積み替えコストや運搬コストの低減を図るとともに、燃料原木の運搬経費支援などにより、流通体制の総合的な整備を進めていきます。バイオマス発電所の立地は林業振興の大きなチャンスであり、今後とも供給体制の整備に積極的に取り組んでいきます。 |
住宅宿泊事業法施行条例
| 民泊を特区等により先行実施している他府県では周辺住民とのトラブルが多いようである。責任ある管理運営を求めたいが、問題発生時の迅速な対処について条例案にはどう規定しているのか。 |
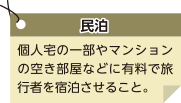 事業者の管理責任を求める規定については、周辺住民が反対していないことの確認や管理者が近くに駐在すること等を義務付けています。 事業者の管理責任を求める規定については、周辺住民が反対していないことの確認や管理者が近くに駐在すること等を義務付けています。 |
キャッシュレス決済の普及促進
| 外国人観光客向けに、QRコードを用いたキャッシュレス決済の普及促進に取り組んではどうか。 |
 キャッシュレス決済は、外国人観光客の利便性向上や消費誘発の観点から有効な手段と考えます。QRコードを活用したシステム等、最新の決済システムの紹介・普及を図り、観光客の消費拡大に努めます。 キャッシュレス決済は、外国人観光客の利便性向上や消費誘発の観点から有効な手段と考えます。QRコードを活用したシステム等、最新の決済システムの紹介・普及を図り、観光客の消費拡大に努めます。 |