| 知事の4年間の総括と今後の抱負 |
 知事は、これまでの4年間の実績をどう総括するか。また、2期県政の目標を「元気な和歌山」の実現とされたが、その抱負は。 知事は、これまでの4年間の実績をどう総括するか。また、2期県政の目標を「元気な和歌山」の実現とされたが、その抱負は。 |
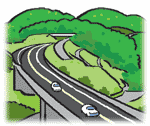 |
 4年前に知事に当選して以来、元気なふるさと和歌山を実現しようとの一心で頑張ってきた。有効求人倍率が近畿でトップになるなど効果も少しあらわれてきたが、県勢浮揚という点では、まだ十分でない。厳しい経済・雇用情勢への対応や公共インフラの整備など、課題が山積しており、今後も、県民の協力のもと、県議会と連携しながら、ふるさと和歌山をさらに元気にするため、粉骨砕身の覚悟で邁進する。 4年前に知事に当選して以来、元気なふるさと和歌山を実現しようとの一心で頑張ってきた。有効求人倍率が近畿でトップになるなど効果も少しあらわれてきたが、県勢浮揚という点では、まだ十分でない。厳しい経済・雇用情勢への対応や公共インフラの整備など、課題が山積しており、今後も、県民の協力のもと、県議会と連携しながら、ふるさと和歌山をさらに元気にするため、粉骨砕身の覚悟で邁進する。 |
|
 |
| 「あたたかい改革」とは |
 依然として厳しい景気・雇用情勢のもと、知事は2期目のスタートとなる予算編成に取り組まれたが、知事の考える「あたたかい改革」とは何か。 依然として厳しい景気・雇用情勢のもと、知事は2期目のスタートとなる予算編成に取り組まれたが、知事の考える「あたたかい改革」とは何か。 |
 行財政改革を進めながら、限られた予算の中で、つらい思いをしている人や地域に配慮しながら、福祉や教育、過疎対策などを後退させることなく、さらに伸ばしていく取組を「あたたかい改革」と位置づけている。厳しい経済環境の中、児童虐待の対応強化などを平成23年度当初予算に反映したところである。 行財政改革を進めながら、限られた予算の中で、つらい思いをしている人や地域に配慮しながら、福祉や教育、過疎対策などを後退させることなく、さらに伸ばしていく取組を「あたたかい改革」と位置づけている。厳しい経済環境の中、児童虐待の対応強化などを平成23年度当初予算に反映したところである。 |
|
 |
| 和歌浦地域の活性化策 |
 名所・景勝地の和歌浦地域の活性化策の一環として、今後、和歌浦漁港を中心とした取組をどう支援するか。 名所・景勝地の和歌浦地域の活性化策の一環として、今後、和歌浦漁港を中心とした取組をどう支援するか。 |
 県では、水産業を核とした地域活性化支援を新政策として掲げ、県、市町村、地元関係者が一体となり、6次産業化の推進など、複合的な地域おこしの支援を考えている。和歌浦漁港でも、交流拠点施設整備による朝市の常設化など、県と地元地域が一体となってさらなる地域の発展に向けて取り組む。 県では、水産業を核とした地域活性化支援を新政策として掲げ、県、市町村、地元関係者が一体となり、6次産業化の推進など、複合的な地域おこしの支援を考えている。和歌浦漁港でも、交流拠点施設整備による朝市の常設化など、県と地元地域が一体となってさらなる地域の発展に向けて取り組む。
| 6次産業 |
| 第1次産業(農業・水産業等)が第2次産業(食品加工)、第3次産業(流通・販売)にもかかわる多角的経営のこと。 |
|
 |
 |
|
|
 |
| 下水道への接続補助 |
 下水道の接続に対する県の補助対象が市町村の生活困窮世帯に対する補助となっているが、もっと効果の上がる県費補助ができないか。 下水道の接続に対する県の補助対象が市町村の生活困窮世帯に対する補助となっているが、もっと効果の上がる県費補助ができないか。 |
 接続費用の負担が困難な生活困窮世帯に対する市町村補助の半分を県が補助しているが、これは法で義務づけられた接続費用の負担が困難な方を支援するものである。それ以外の支援については市町村でお願いしたい。 接続費用の負担が困難な生活困窮世帯に対する市町村補助の半分を県が補助しているが、これは法で義務づけられた接続費用の負担が困難な方を支援するものである。それ以外の支援については市町村でお願いしたい。 |
|
 |
| 官公需の地元中小事業者への発注拡大 |
 21年度の和歌山市を含む官公需総額に占める中小企業向け発注額の割合は77・4%で全国32位である。地元中小事業者への発注機会拡大にどう取り組んでいるか。 21年度の和歌山市を含む官公需総額に占める中小企業向け発注額の割合は77・4%で全国32位である。地元中小事業者への発注機会拡大にどう取り組んでいるか。 |
 国の方針に準じて、中小企業者の受注機会の増大のための措置を徹底するよう周知を図り、一層の契約比率向上に努めていく。国の実績、全国平均とも上回っているので、現在のところ独自に目標を定める予定はないが、発注機会拡大には庁内等への徹底的な周知が欠かせないと考え、引き続き粘り強く取り組む。 国の方針に準じて、中小企業者の受注機会の増大のための措置を徹底するよう周知を図り、一層の契約比率向上に努めていく。国の実績、全国平均とも上回っているので、現在のところ独自に目標を定める予定はないが、発注機会拡大には庁内等への徹底的な周知が欠かせないと考え、引き続き粘り強く取り組む。 |
|
 |
| 地デジ受信困難地域への支援 |
 本年7月から地上デジタル放送へ移行するが、県内受信困難地域への支援はどこまで行われたか。 本年7月から地上デジタル放送へ移行するが、県内受信困難地域への支援はどこまで行われたか。 |
 |
 地デジは、電波の利用という国策から出てきた話であり、国の責任で行うよう強く要求してきたところ、共聴施設新設の補助拡充やCATVに対応するための支援措置など、大きく改善された。県としても、市町と連携して住民への説明会等を開催して制度の活用を進め、住民の負担軽減を図ってきた。 地デジは、電波の利用という国策から出てきた話であり、国の責任で行うよう強く要求してきたところ、共聴施設新設の補助拡充やCATVに対応するための支援措置など、大きく改善された。県としても、市町と連携して住民への説明会等を開催して制度の活用を進め、住民の負担軽減を図ってきた。 |
|
 |
| 高病原性鳥インフルエンザ対策 |
 2月15日に紀の川市で発生し、18日に約12万羽を殺処分したが、終息宣言は法律上、最短でも3月14日である。この間の関係農家、関連業者への対応は。 2月15日に紀の川市で発生し、18日に約12万羽を殺処分したが、終息宣言は法律上、最短でも3月14日である。この間の関係農家、関連業者への対応は。 |
 |
 殺処分となった鶏の評価額の8割は、法に基づく手当金として国から補償される。現在、全額補償に向けた法改正が検討されているが、仮に国で全額対応できない場合、残額を県で補てんする。移動制限区域内の家きん農家の売上減や飼料費増に対しても補てんすることとし、金融支援についても相談窓口を設置して対応している。 殺処分となった鶏の評価額の8割は、法に基づく手当金として国から補償される。現在、全額補償に向けた法改正が検討されているが、仮に国で全額対応できない場合、残額を県で補てんする。移動制限区域内の家きん農家の売上減や飼料費増に対しても補てんすることとし、金融支援についても相談窓口を設置して対応している。 |
|
 |
| 買い物弱者への対応 |
 高齢化社会における買い物弱者への対応として、身近な商店との連携を図るネットワークを構築し、配送業務を担えるNPO等で雇用を生み出す取組を導入しては。 高齢化社会における買い物弱者への対応として、身近な商店との連携を図るネットワークを構築し、配送業務を担えるNPO等で雇用を生み出す取組を導入しては。 |
 買い物弱者対策は喫緊の社会的課題であり、今後、商店街がビジネスチャンスととらえて果敢に取り組むときは、県も積極的に支援する。その際にNPO等と協働を図っていくことは新しい地域活性化モデルが示されることにもなるので、関係機関や他部局と連携して解決に努める。 買い物弱者対策は喫緊の社会的課題であり、今後、商店街がビジネスチャンスととらえて果敢に取り組むときは、県も積極的に支援する。その際にNPO等と協働を図っていくことは新しい地域活性化モデルが示されることにもなるので、関係機関や他部局と連携して解決に努める。 |
|
 |
| ドクターカーの導入 |
 和歌山市内の救命率向上のため、早期にドクターカーを導入する必要があるが、その現状と今後の対応は。 和歌山市内の救命率向上のため、早期にドクターカーを導入する必要があるが、その現状と今後の対応は。 |
 |
 ドクターカーは重篤傷病者等の救命率向上につながり、現在、日赤和歌山医療センター、県立医科大学附属病院、和歌山市消防局と検討を行っている。今後、引き続き関係機関と協議し、医師不足の中、病院の救急部門への影響等も考慮しながら取り組む。 ドクターカーは重篤傷病者等の救命率向上につながり、現在、日赤和歌山医療センター、県立医科大学附属病院、和歌山市消防局と検討を行っている。今後、引き続き関係機関と協議し、医師不足の中、病院の救急部門への影響等も考慮しながら取り組む。 |
|
 |
| 知的障害児通園施設の増設 |
 現在、知的障害児通園施設は県内に3カ所あるが、いずれも満杯の状況である。入園できない子供にどう対応しているか。 現在、知的障害児通園施設は県内に3カ所あるが、いずれも満杯の状況である。入園できない子供にどう対応しているか。 |
 児童デイサービス事業で障害児の個別・集団療育を実施しており、月平均約1000名が利用している。障害児(者)地域療育等支援事業では、医師や理学療法士等の専門家が定期的に家庭や地域の集会所を巡回し、療育支援の充実を図っている。今後も市町村と協議の上、社会福祉法人による施設設置を働きかける。 児童デイサービス事業で障害児の個別・集団療育を実施しており、月平均約1000名が利用している。障害児(者)地域療育等支援事業では、医師や理学療法士等の専門家が定期的に家庭や地域の集会所を巡回し、療育支援の充実を図っている。今後も市町村と協議の上、社会福祉法人による施設設置を働きかける。 |
|
 |
| 医大不適正支出金の返還 |
 県立医科大学の不適正経理問題について、不適正支出をした研究者の処分のみならず、そのお金を返還させるべきではないか。 県立医科大学の不適正経理問題について、不適正支出をした研究者の処分のみならず、そのお金を返還させるべきではないか。 |
 昨年末、国との協議が完了した。不適正支出額は約1億3000万円で、加算金を含めると最終返還額は約1億7000万円となる見込みである。国等へは大学が立てかえて返還しているが、今後、研究者から大学への返済について、支払い方法等の貸付契約を交わすことにしている。 昨年末、国との協議が完了した。不適正支出額は約1億3000万円で、加算金を含めると最終返還額は約1億7000万円となる見込みである。国等へは大学が立てかえて返還しているが、今後、研究者から大学への返済について、支払い方法等の貸付契約を交わすことにしている。 |
|
 |
| 紀南への回復期リハビリテーションセンター設置 |
 現在、田辺地域では回復期リハビリテーションセンターは手一杯と聞く。センターを設置すれば、患者を寝たきりにすることもなく、医療費削減の効果もあるのではないか。 現在、田辺地域では回復期リハビリテーションセンターは手一杯と聞く。センターを設置すれば、患者を寝たきりにすることもなく、医療費削減の効果もあるのではないか。 |
 |
 新たなリハビリテーションセンターの設置、既設の医療機関の強化や連携など、地域にとってより適切な医療体制のあり方について、地域の意見も十分聞き、保健所単位で設置する医療対策協議会で検討していく。 新たなリハビリテーションセンターの設置、既設の医療機関の強化や連携など、地域にとってより適切な医療体制のあり方について、地域の意見も十分聞き、保健所単位で設置する医療対策協議会で検討していく。 |
|
 |
| 携帯電話の有害サイト対策 |
 携帯電話サイトを通じて性犯罪被害等が増加している中、有害サイトとの接点を断ち切るため、効果的な対策を考えなければならないと思うが。 携帯電話サイトを通じて性犯罪被害等が増加している中、有害サイトとの接点を断ち切るため、効果的な対策を考えなければならないと思うが。 |
 各携帯電話事業者とフィルタリング促進のための検討会等を行っているが、フィルタリング解除には保護者に理由書の提出を求めるという事業者の自主的な動きも広まっている。今後も事業者にフィルタリング促進を働きかけるとともに、安易な解除に歯どめをかけ、有害サイトから青少年を守る有効な対策に取り組む。 各携帯電話事業者とフィルタリング促進のための検討会等を行っているが、フィルタリング解除には保護者に理由書の提出を求めるという事業者の自主的な動きも広まっている。今後も事業者にフィルタリング促進を働きかけるとともに、安易な解除に歯どめをかけ、有害サイトから青少年を守る有効な対策に取り組む。
| フィルタリング |
| インターネット上の青少年にとって望ましくない有害情報サイトへのアクセスを制限する機能。 |
|
 |

|
|
|
 |
| 市町村合併に対する所見 |
 「平成の合併」で30市町村となったが、合併のデメリットもあらわれてきている。知事の所見は。 「平成の合併」で30市町村となったが、合併のデメリットもあらわれてきている。知事の所見は。 |
 専門部署の新設等による行政基盤の強化や各種財政支援を活用した公共施設の耐震化の推進などの効果もあらわれている反面、旧庁舎周辺のにぎわい低下、水道料金等の住民負担の調整などの課題もある。県としても、そういった問題意識を持ち、課題解消に努めるべく、市町村の方々と議論しながら様々な施策を通じて支援していく。 専門部署の新設等による行政基盤の強化や各種財政支援を活用した公共施設の耐震化の推進などの効果もあらわれている反面、旧庁舎周辺のにぎわい低下、水道料金等の住民負担の調整などの課題もある。県としても、そういった問題意識を持ち、課題解消に努めるべく、市町村の方々と議論しながら様々な施策を通じて支援していく。 |
|
 |
| 高校の入学定員増 |
 定員増は予算がなく難しいと言うが、1クラス分の経費は約1600万円と聞いた。それで数十人の子供たちの未来が保証されるのなら高くないのでは。 定員増は予算がなく難しいと言うが、1クラス分の経費は約1600万円と聞いた。それで数十人の子供たちの未来が保証されるのなら高くないのでは。 |
 県立高校の募集定員は、教育委員会が生徒数の推移や地域の実態等を総合的に検討して決定しているが、「和歌山の子供は和歌山で育てる」ことを基本に置くよう求めている。予算を理由に子供の未来を狭めることは考えておらず、今後も本県教育の充実に取り組む。 県立高校の募集定員は、教育委員会が生徒数の推移や地域の実態等を総合的に検討して決定しているが、「和歌山の子供は和歌山で育てる」ことを基本に置くよう求めている。予算を理由に子供の未来を狭めることは考えておらず、今後も本県教育の充実に取り組む。 |
|
 |
| 生徒指導のあり方 |
 中学校でのいじめで、担任が見て見ぬふりをしていることもあると聞いた。聖職者である教師は毅然とした態度で指導してもらいたい。 中学校でのいじめで、担任が見て見ぬふりをしていることもあると聞いた。聖職者である教師は毅然とした態度で指導してもらいたい。 |
 |
 日ごろから児童生徒のことを一番に考え、実態把握に努めながら熱意を持って対応するとともに、いじめや暴力には毅然とした態度で臨み、規範意識をはじめ豊かな社会性を育てるよう引き続き指導していく。 日ごろから児童生徒のことを一番に考え、実態把握に努めながら熱意を持って対応するとともに、いじめや暴力には毅然とした態度で臨み、規範意識をはじめ豊かな社会性を育てるよう引き続き指導していく。 |
|
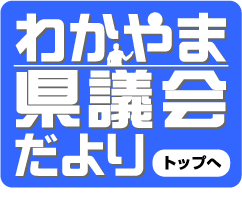
 平成23年度当初予算を可決
平成23年度当初予算を可決