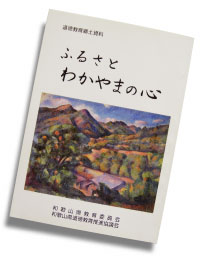平成20年度
和歌山県一般会計
補正予算などを可決
知事説明要旨
 今後発生が予想される地震や風水害等に対して、防災対策や教育・啓発活動をさらに積極的に実施するとともに、県境を越えた課題にも対応するため、近隣地方公共団体との協力を推進し、関西全体で取り組む広域連合の議論にも積極的に参画していきたい。
今後発生が予想される地震や風水害等に対して、防災対策や教育・啓発活動をさらに積極的に実施するとともに、県境を越えた課題にも対応するため、近隣地方公共団体との協力を推進し、関西全体で取り組む広域連合の議論にも積極的に参画していきたい。
また、世界遺産をはじめとした本県の優れた文化・歴史・自然を活かした様々な観光振興策を一層強化するとともに、県内の幅広い分野の優れた県産品を選定・推奨する制度「プレミア和歌山」を本年度からスタートし、和歌山県産のブランドイメージを確立していきたい。
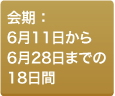
6月 |
11日(水) 本会議
12日(木) 議案調査
13日(金) 議案調査
16日(月) 議案調査
17日(火) 議案調査 |
|
18日(水) 本会議(一般質問)
19日(木) 本会議(一般質問)
20日(金) 本会議(一般質問)
23日(月) 本会議(一般質問)
24日(火) 常任委員会 |
|
26日(木) 本会議・常任委員会
27日(金) 本会議
28日(土) 本会議 |
会期中の主な動き
- 下記の特別委員会を開催しました。
防災・環境問題等対策特別委員会(6/18)、議員定数等検討特別委員会(6/19)、人権・少子高齢化問題等対策特別委員会(6/20)
- 議長・副議長の選挙が行われ、議長に大沢広太郎議員、副議長に山田正彦議員を選出しました。
- 常任委員会、予算特別委員会及び議会運営委員会の委員と委員長・副委員長を選任しました。
議決結果等
項目 |
件数 |
概要 |
結果 |
| 知事提出の予算案件 |
1件 |
平成20年度和歌山県一般会計補正予算 |
可決 |
| 知事提出の条例案件 |
6件 |
和歌山県子どもを虐待から守る条例 等 |
可決 |
| 知事提出のその他案件 |
6件 |
和歌山県土地開発公社の定款の一部変更について 等 |
可決 |
| 知事提出の人事案件 |
10件 |
和歌山県公安委員会の委員の任命につき同意を求めるについて 等 |
同意 |
| 知事専決処分報告 |
8件 |
平成19年度和歌山県一般会計補正予算 等 |
承認 |
| 請願 |
1件 |
紀の川市東山田地内の林地開発申請に伴う建設残土処分場建設に関する林地開発許可を与えない旨についての請願書 |
採択 |
2件 |
かつらぎ町道折登堀越線の県道昇格について 等 |
継続審査 |
| 意見書 |
5件 |
身体障害者に対する駐車規制及び駐車許可制度運用の見直しに関する意見書 等 |
可決 |
| 決議 |
1件 |
「権利の放棄について」に係る附帯決議 |
可決 |
一般質問議員(13名)
6月18日(水) 山田 正彦 原 日出夫 岸本 健 松坂 英樹
6月19日(木) 山下 直也 中 拓哉 奥村 規子
6月20日(金) 長坂 隆司 雑賀 光夫 井出 益弘
6月23日(月) 江上 柳助 山下 大輔 吉井 和視
主な質問とこれに対する知事や関係部局の答弁は次のとおりです(要約抜粋)
広域連合への取組
 県の発展のためには、公共ネットワークのインフラ整備や、防災・環境・観光・医療分野などの広域連携が必要である。関西広域機構で議論が進んでいる広域連合設立の意義など、県の考えはどうか。
県の発展のためには、公共ネットワークのインフラ整備や、防災・環境・観光・医療分野などの広域連携が必要である。関西広域機構で議論が進んでいる広域連合設立の意義など、県の考えはどうか。
 関西の各地域が連携してスケールを広げ、日本のもう一つの中心として発展していくことが本県発展のためにも不可欠なので、今後とも積極的に「関西広域連合」の議論に参画していきたい。
関西の各地域が連携してスケールを広げ、日本のもう一つの中心として発展していくことが本県発展のためにも不可欠なので、今後とも積極的に「関西広域連合」の議論に参画していきたい。
用語解説
関西広域機構(KU)
関西2府7県4政令市と7経済団体等をメンバーとして2007年7月に設立。国からの権限移譲の受け皿となる「関西広域連合」の設置などについて検討が重ねられている。
中小企業高度化資金融資審査の問題点
 経営破綻した貸付先の中には、不自然な土地の買い足しを行って無理やり県の融資審査を通過させたのではないかと考えられるものがあるが、県の審査に対する見解はどうか。
経営破綻した貸付先の中には、不自然な土地の買い足しを行って無理やり県の融資審査を通過させたのではないかと考えられるものがあるが、県の審査に対する見解はどうか。
 調査の結果、当時の融資審査については、不適切なものはなかったと認識している。また、中小企業事業団(当時)の厳しい審査もクリアしている。土地の買い足しは、工場建設に必要な構造物等に係る土地の所有権を取得したもので、管理責任及び所有権の帰属を一致させたものである。
調査の結果、当時の融資審査については、不適切なものはなかったと認識している。また、中小企業事業団(当時)の厳しい審査もクリアしている。土地の買い足しは、工場建設に必要な構造物等に係る土地の所有権を取得したもので、管理責任及び所有権の帰属を一致させたものである。
林地開発申請への対応
 紀の川市東山田地内の林地開発・建設残土処分場建設について、地元では、生活に悪影響を及ぼすとのことから反対している。県長期総合計画には「県民の命と暮らしを守る安全安心和歌山」とあるが、県の見解はどうか。
紀の川市東山田地内の林地開発・建設残土処分場建設について、地元では、生活に悪影響を及ぼすとのことから反対している。県長期総合計画には「県民の命と暮らしを守る安全安心和歌山」とあるが、県の見解はどうか。
 平成20年3月に開発申請がなされ、6月に紀の川市から意見書が提出されている。今後、その意見書の内容を十分吟味するとともに、森林法の許可基準、県の林地開発許可制度事務取扱要領等に基づいて厳正に審査し、対応していきたい。
平成20年3月に開発申請がなされ、6月に紀の川市から意見書が提出されている。今後、その意見書の内容を十分吟味するとともに、森林法の許可基準、県の林地開発許可制度事務取扱要領等に基づいて厳正に審査し、対応していきたい。
↑ページの先頭に戻る
藻場(もば)再生への取組

 藻場は、沿岸部の重要な一次産業の場であり、海の生き物の産卵・生育の場である。その藻場を再生する試みとして、ロープによる海藻の森魚礁をつくってはどうか。また、本県の海藻栽培の現状はどうか。
藻場は、沿岸部の重要な一次産業の場であり、海の生き物の産卵・生育の場である。その藻場を再生する試みとして、ロープによる海藻の森魚礁をつくってはどうか。また、本県の海藻栽培の現状はどうか。
 近年、県内の各地域で藻場が衰退する「磯焼け」の状況が見られており、県水産試験場では、カジメ類の高水温でも生育できる品種の育成など、実用化に向けた実証試験を行っている。ロープを用いた藻場造成について、過去にはよい結果を得られなかったが、今後、他府県の状況等を見ながらその可能性について検討していきたい。
近年、県内の各地域で藻場が衰退する「磯焼け」の状況が見られており、県水産試験場では、カジメ類の高水温でも生育できる品種の育成など、実用化に向けた実証試験を行っている。ロープを用いた藻場造成について、過去にはよい結果を得られなかったが、今後、他府県の状況等を見ながらその可能性について検討していきたい。
介護人材不足への対策
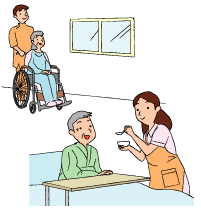
 県は、長期総合計画の「生涯現役で誰もが活躍できる和歌山」の中で高齢化対策の推進を挙げているが、介護現場では人材不足が大きな問題となっている。人材確保のため、今後どのような取組をしていくのか。
県は、長期総合計画の「生涯現役で誰もが活躍できる和歌山」の中で高齢化対策の推進を挙げているが、介護現場では人材不足が大きな問題となっている。人材確保のため、今後どのような取組をしていくのか。
 本県でも人材不足が生じていると認識しているが、既に国では介護従事者の処遇改善策の検討を始めている。その動向を注視しながら、資格を持っていても勤務していない人の掘り起こしや各種研修を通じた人材育成など、関係団体とも協力しながら人材確保に努めていきたい。
本県でも人材不足が生じていると認識しているが、既に国では介護従事者の処遇改善策の検討を始めている。その動向を注視しながら、資格を持っていても勤務していない人の掘り起こしや各種研修を通じた人材育成など、関係団体とも協力しながら人材確保に努めていきたい。
後期高齢者医療制度への対応
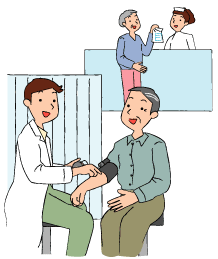
 後期高齢者医療制度が本年4月から始まったが、この制度については、多くの問題点が指摘されている。制度発足後の高齢者等からの声について、どのように受けとめているのか。
後期高齢者医療制度が本年4月から始まったが、この制度については、多くの問題点が指摘されている。制度発足後の高齢者等からの声について、どのように受けとめているのか。
 制度施行前から市町村などとも連携して広報を行い、地域住民や団体への説明会も数多く実施し、周知を十分行ってきたつもりだが、徹底できていなかった面もある。現在寄せられている制度への意見などについても、きちんとくみ取っていかなければならないと考えている。
制度施行前から市町村などとも連携して広報を行い、地域住民や団体への説明会も数多く実施し、周知を十分行ってきたつもりだが、徹底できていなかった面もある。現在寄せられている制度への意見などについても、きちんとくみ取っていかなければならないと考えている。
↑ページの先頭に戻る
着地型観光の振興

 和歌山県は、一次産業である農林水産業、食材・食づくり、文化・歴史など、地方の宝が満載である。これらを生かした「着地型観光」の振興について、県はどのようにサポートするのか。
和歌山県は、一次産業である農林水産業、食材・食づくり、文化・歴史など、地方の宝が満載である。これらを生かした「着地型観光」の振興について、県はどのようにサポートするのか。
 「着地型観光」は、地域の活性化を図るために大変有効なものである。本年度から「ほんまもん体験」のプログラムを使った旅行商品に助成を行うとともに、研修会の開催や販路開拓支援など、商品化へのサポートを積極的に行うことにしている。
「着地型観光」は、地域の活性化を図るために大変有効なものである。本年度から「ほんまもん体験」のプログラムを使った旅行商品に助成を行うとともに、研修会の開催や販路開拓支援など、商品化へのサポートを積極的に行うことにしている。
用語解説
着地型観光
観光の目的地(着地)側が、現地の観光資源や体験などを活用して企画する観光プラン。「地の利」を生かせるので観光客のニーズに合致したものを提供しやすい。
観光医療振興のための助成制度
 観光と予防医療、健康サービスを組み合わせた事業は大きな可能性があり、競争も激化しつつある。県では早くから観光と組み合わせた新産業の創造に取り組んできたが、その有利性を生かし、「観光医療」といった視点で地域の民間投資を一気に促進させ、ハード整備にも使える新たな助成制度の整備を検討願いたい。
観光と予防医療、健康サービスを組み合わせた事業は大きな可能性があり、競争も激化しつつある。県では早くから観光と組み合わせた新産業の創造に取り組んできたが、その有利性を生かし、「観光医療」といった視点で地域の民間投資を一気に促進させ、ハード整備にも使える新たな助成制度の整備を検討願いたい。
 「観光医療」は今後の大事なキーワードの一つなので、市町村や地域の観光協会等が進める健康増進や医療をテーマとした観光地づくりに対し、地域との連携事業の中でなお一層支援することとしている。支援に当たっては、地域の観光事業等のニーズや要望をよく聞き、どのような形で対応できるか検討していきたい。
「観光医療」は今後の大事なキーワードの一つなので、市町村や地域の観光協会等が進める健康増進や医療をテーマとした観光地づくりに対し、地域との連携事業の中でなお一層支援することとしている。支援に当たっては、地域の観光事業等のニーズや要望をよく聞き、どのような形で対応できるか検討していきたい。
県工事への単品スライド条項の適用
 現在、原材料価格の高騰もあり、建設業の経営は非常に厳しくなっている。国では28年ぶりに「単品スライド条項」を発動したが、本県工事でも早急にその条項を適用すべきではないか。
現在、原材料価格の高騰もあり、建設業の経営は非常に厳しくなっている。国では28年ぶりに「単品スライド条項」を発動したが、本県工事でも早急にその条項を適用すべきではないか。
 県では、昨年末からの原油高騰を受けて関係建設資材単価を毎月改定するなど、実勢単価での発注に努めているが、発注後の急激な物価高騰に対応するため、国土交通省から示された運用ルールに沿った形で、できるだけ速やかに導入を図りたい。
県では、昨年末からの原油高騰を受けて関係建設資材単価を毎月改定するなど、実勢単価での発注に努めているが、発注後の急激な物価高騰に対応するため、国土交通省から示された運用ルールに沿った形で、できるだけ速やかに導入を図りたい。
用語解説
単品スライド条項
工事の発注後、急激に主要材料などの単価が値上がりして請負代金額が不適当となった場合、その値上がり分を含んだ代金を請求できるという条項。
↑ページの先頭に戻る
紀の川河口大橋の無料化への社会実験
 本年の2月定例会で、紀の川河口大橋の通行料無料化の社会実験について質問し、「期間中の収入減に対する損失補てんも伴うが、今後その有効性等について検討したい」との答弁を得た。その後、社会実験について検討されたと思うが、その結果と、今後の早期無料化に向けた取組はどうか。
本年の2月定例会で、紀の川河口大橋の通行料無料化の社会実験について質問し、「期間中の収入減に対する損失補てんも伴うが、今後その有効性等について検討したい」との答弁を得た。その後、社会実験について検討されたと思うが、その結果と、今後の早期無料化に向けた取組はどうか。
 社会実験については、期間及び時間帯を限定して、年内に実施することとしている。早期無料開放については、実験結果を踏まえ、渋滞緩和や経済効果、コストなど、種々の要素を総合的に勘案するとともに、県民や議会の意見も聞き、前向きに検討していきたい。
社会実験については、期間及び時間帯を限定して、年内に実施することとしている。早期無料開放については、実験結果を踏まえ、渋滞緩和や経済効果、コストなど、種々の要素を総合的に勘案するとともに、県民や議会の意見も聞き、前向きに検討していきたい。

渋滞する紀の川大橋

紀の川河口大橋
教育施設の耐震化

 南紀支援学校(上富田町)は肢体不自由児の特別支援学校で、いろいろな障害のある児童が学んでいる。最も災害に弱い立場の子どもたちが学ぶ学校の耐震対策はどうか。また、大きなハンディキャップのある子どもたちに最善の教育条件を保障する立場から、整備計画はどうなっているのか。
南紀支援学校(上富田町)は肢体不自由児の特別支援学校で、いろいろな障害のある児童が学んでいる。最も災害に弱い立場の子どもたちが学ぶ学校の耐震対策はどうか。また、大きなハンディキャップのある子どもたちに最善の教育条件を保障する立場から、整備計画はどうなっているのか。
 肢体不自由児には、その障害特性に応じた適切な教育環境の整備が重要だと考えている。南紀支援学校の教育環境整備については、耐震化はもちろん、特別支援教育の理念を踏まえ、現在策定を進めている特別支援学校再編整備構想の中で、県立学校全体の施設整備の状況を勘案しながら鋭意検討していきたい。
肢体不自由児には、その障害特性に応じた適切な教育環境の整備が重要だと考えている。南紀支援学校の教育環境整備については、耐震化はもちろん、特別支援教育の理念を踏まえ、現在策定を進めている特別支援学校再編整備構想の中で、県立学校全体の施設整備の状況を勘案しながら鋭意検討していきたい。
和歌山国体に向けた施設整備

 競技用施設の中には、クレー射撃場など、国体終了後に施設の利用収益で運営でき、大きな経済波及効果を期待できるものもある。国体開催に当たり、新設や改修が必要な施設の選定、市町村の施設整備への助成など、基本的な考えはどうか。
競技用施設の中には、クレー射撃場など、国体終了後に施設の利用収益で運営でき、大きな経済波及効果を期待できるものもある。国体開催に当たり、新設や改修が必要な施設の選定、市町村の施設整備への助成など、基本的な考えはどうか。
 国体に向けた施設整備については、可能な限り県内の既存施設や近畿各府県の施設の有効活用に努めることとしている。現在、競技団体と市町村の意向調査の結果を踏まえ、競技会場地の選定原案を検討している。施設整備費やランニングコストなど、国体開催に係る県や市町村の総合的な財政見通しを勘案しながら、競技会場地の選定を計画的に行っていきたい。
国体に向けた施設整備については、可能な限り県内の既存施設や近畿各府県の施設の有効活用に努めることとしている。現在、競技団体と市町村の意向調査の結果を踏まえ、競技会場地の選定原案を検討している。施設整備費やランニングコストなど、国体開催に係る県や市町村の総合的な財政見通しを勘案しながら、競技会場地の選定を計画的に行っていきたい。
道徳教育の充実
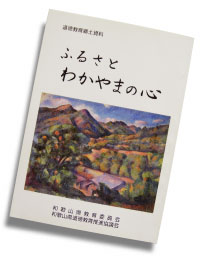
 学習指導要領が改訂され、道徳教育の目標の中に、国と郷土を愛することが明記された。それを踏まえ、教育委員会や学校は、充実した教育内容とするため、道徳の時間の指導を徹底する必要がある。教材の選定も含め、今回の改訂に伴う道徳教育の充実に対する方針はどうか。
学習指導要領が改訂され、道徳教育の目標の中に、国と郷土を愛することが明記された。それを踏まえ、教育委員会や学校は、充実した教育内容とするため、道徳の時間の指導を徹底する必要がある。教材の選定も含め、今回の改訂に伴う道徳教育の充実に対する方針はどうか。
 新学習指導要領に示されたとおり、道徳の時間をかなめに、学校における教育活動全体を通じて道徳教育の充実を図るとともに、各学校に新設する道徳教育推進教師を中心に全教師が協力して取り組むことが肝要である。地域教材を活用した道徳教育は郷土に対する理解と愛情につながることから、和歌山県の先人の伝記や逸話などを収録した道徳教育郷土資料「ふるさと わかやまの心」を活用するとともに、魅力ある教材の開発にも努めていきたい。
新学習指導要領に示されたとおり、道徳の時間をかなめに、学校における教育活動全体を通じて道徳教育の充実を図るとともに、各学校に新設する道徳教育推進教師を中心に全教師が協力して取り組むことが肝要である。地域教材を活用した道徳教育は郷土に対する理解と愛情につながることから、和歌山県の先人の伝記や逸話などを収録した道徳教育郷土資料「ふるさと わかやまの心」を活用するとともに、魅力ある教材の開発にも努めていきたい。
↑ページの先頭に戻る

 今後発生が予想される地震や風水害等に対して、防災対策や教育・啓発活動をさらに積極的に実施するとともに、県境を越えた課題にも対応するため、近隣地方公共団体との協力を推進し、関西全体で取り組む広域連合の議論にも積極的に参画していきたい。
今後発生が予想される地震や風水害等に対して、防災対策や教育・啓発活動をさらに積極的に実施するとともに、県境を越えた課題にも対応するため、近隣地方公共団体との協力を推進し、関西全体で取り組む広域連合の議論にも積極的に参画していきたい。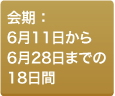
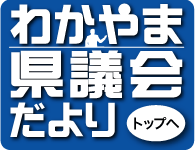

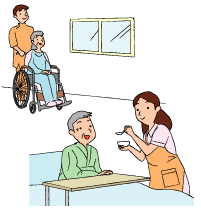
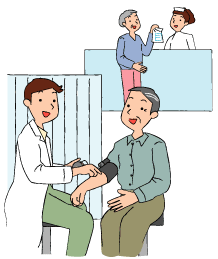

 渋滞する紀の川大橋
渋滞する紀の川大橋 紀の川河口大橋
紀の川河口大橋