

▼ 一般質問議員 16人
|
6月18日(水)
佐藤 武治
林 隆一 鈴木 德久 小川 浩樹 |
6月19日(木)
坂本 佳隆
片桐 章浩 奥村 規子 川畑 哲哉 |
6月20日(金)
長坂 隆司
三栖 拓也 高田 英亮 濱口 太史 |
6月23日(月)
谷口 和樹
浦平 美博 藤山 将材 山田 正彦 |
会期中の主な動き
▼ 特別委員会の開催
人権・少子高齢化問題等対策特別委員会…6月20日議決結果・意見書等
| 項目 | 件数 | 概要 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予算案件 (知事提出) |
2件 | 令和7年度和歌山県一般会計補正予算 等 | 可決 |
| 条例案件 ( 〃 ) |
9件 | 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 等 | 可決 |
| 人事案件 ( 〃 ) |
5件 | 和歌山県監査委員の選任につき同意を求めるについて 等 | 同意 |
| その他案件 ( 〃 ) |
2件 | 令和7年度建設事業施行に伴う市町村負担金について 等 | 可決 |
| 請願 | 1件 | 加太漁業協同組合の共同漁業権の区域内での小型機船底びき網漁業の操業禁止を求める請願 | 継続 審査 |
| 意見書 | 1件 | 地方財政の確保と充実を求める意見書 | 可決 |
主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、次のとおりです。(要約)
| 知事が目指す「わかやまの将来像」 | |
問 |
知事が目指す「わかやまの将来像」とは、どのようなものか。 |
答 |
県民が将来に希望を持てるビジョンを描き実現していくことが、知事としての使命だと思っています。 現在策定作業中の県政の新たな指針「新総合計画」で展望する2040年に向け、人口減少が避けられない中で、少ない人口でも多様性に富んだ豊かな社会を構築していくため、「人口減少や気候変動に適応した持続可能で心豊かな和歌山」、「個人が尊重され、あらゆる分野で個性輝く和歌山」という2つの将来像を掲げ、その実現に向けて全力で取り組みます。 |
| 米づくりに対する支援 | |
問 |
米づくりへの支援について、知事の考えを伺う。 |
答 |
 水田農業については、農家一戸あたりの経営面積が小さく、水稲だけでは経営の維持が困難なことから、米づくりと収益性の高い野菜や花きを組み合わせた複合経営を推進してきました。一方、閣議決定された、いわゆる「骨太の方針2025」では、水田政策の見直しの具体化を進める旨が明記されており、今後、米づくり支援の具体的な検討が進められると思われるため、国の動きを注視しながら適切に対応していきます。 水田農業については、農家一戸あたりの経営面積が小さく、水稲だけでは経営の維持が困難なことから、米づくりと収益性の高い野菜や花きを組み合わせた複合経営を推進してきました。一方、閣議決定された、いわゆる「骨太の方針2025」では、水田政策の見直しの具体化を進める旨が明記されており、今後、米づくり支援の具体的な検討が進められると思われるため、国の動きを注視しながら適切に対応していきます。
|
| 県立高校の募集定員枠 | |
問 |
県立高校の再編整備を進める中、各学科の募集定員のバランスをどうとっていくのか。 |
答 |
県立高校の学科は大きく分けて、普通科、総合学科、専門学科の3つがあります。各学科の募集定員のバランスは、各地域の状況等を踏まえつつ、全県的な視野に立って設定しています。 どの学科においても、地域を支えるための人材を育成することが重要であり、今後も、それぞれの学科の特性を生かして、地元和歌山に貢献しようと考える生徒を育てていきます。
どの学科においても、地域を支えるための人材を育成することが重要であり、今後も、それぞれの学科の特性を生かして、地元和歌山に貢献しようと考える生徒を育てていきます。
|
| 産婦人科医の確保 | |
問 |
産婦人科医確保に向けた県独自の施策について、今後の方向性はどうか。 |
答 |
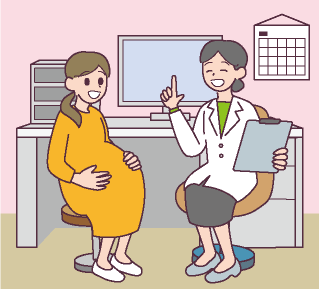 県立医科大学における産科指定の入学枠の設置のほか、地域医療枠を卒業した医師を地域の公立・公的病院に産科医として派遣するなど、県では様々な対策を講じており、県内の若手産科医は徐々に増えつつあります。 県立医科大学における産科指定の入学枠の設置のほか、地域医療枠を卒業した医師を地域の公立・公的病院に産科医として派遣するなど、県では様々な対策を講じており、県内の若手産科医は徐々に増えつつあります。また、分娩取扱医師の処遇改善のため、手当を支給する医療機関に対して補助を行っています。 引き続き、こうした対策により産科医の総数を確保するとともに、地域の診療体制の強化を図っていきます。 |
| 災害時の応急仮設住宅 | |
問 |
被災者のための応急仮設住宅に関し、建設候補地の現状と供給計画について伺う。 |
答 |
応急仮設住宅の建設候補地については、現時点で合計約1万6000戸建設可能な用地を確保しています。また、供給計画については、被災者の応急的な住まいを早期に確保するため、既存の公営住宅や民間賃貸住宅の空室を一定期間借り上げる「賃貸型」の住宅をまず提供し、必要戸数の確保が困難な場合などは、「建設型」の住宅を速やかに設置します。 |
| 教職員へのカスタマーハラスメント対策 | |
問 |
教職員をカスタマーハラスメントから守るための取組や仕組みについて伺う。 |
答 |
課題解決が困難な事案について、一人で抱え込まず組織として対応する仕組みづくりに取り組んでいますが、近年、教職員を追い詰めるような過剰な発言が増加しています。 県教育委員会ではマニュアルを作成し、対応における留意点等を示すなど、今年度から対策を進めています。また、第三者の立場による法的な視点からの助言が得られるスクールロイヤー制度も導入しています。 用語解説
スクールロイヤー制度
…学校で発生する様々な問題に対して法的な助言を行う弁護士を配置する制度
|
| 消費税の減税 | |
問 |
消費税を5パーセントに減税し、さらに廃止を目指すことについて、知事の所見を伺う。 |
答 |
消費税は、全世代共通の社会保障制度の基盤として、極めて重要な財源となっており、減収になれば、本県の財政運営に大きな打撃を与えるため、恒久的な財源を確保していくことが重要です。 地方財政が社会保障関係費の増大や物価高などで極めて厳しい状況にある中、地方団体は、行政サービスを維持しつつ、様々な重要課題に対応する必要があるため、国において丁寧な議論がなされることを期待します。 |
| 和歌山県観光戦略の継承と発展 | |
問 |
岸本前知事の観光戦略をどう継承、発展させるか、知事の所見を伺う。 |
答 |
 熊野古道中辺路 |
| 避難者の健康状態を把握するシステムづくり | |
問 |
災害関連死防止のため、避難者の健康状態を把握するシステムづくりが必要ではないか。 |
答 |
災害時においては、保健医療活動チームが避難所等を巡回し、医師が避難者の診察を行った上で災害診療記録を作成しています。 この情報を「J-SPEED+」というシステムに入力することで、避難者の診療内容を、関係機関で情報共有することができます。 さらにこのシステムにより、被災地外の専門チームから支援を受けることができるので、災害時にはこれを十分活用して、避難者の健康管理に努めます。 |
| 学びの多様化学校 | |
問 |
不登校児童生徒への公的な支援や「学びの多様化学校」の設置について伺う。 |
答 |
不登校児童生徒に対する学習支援や教育相談、登校支援を行う施設として教育支援センターがあります。 また、登校できても教室に入れない児童生徒に対して、不登校児童生徒支援員等が別室や校内教育支援センターで個々の不安な気持ちを取り除いたり、学習支援を行ったりしています。 「学びの多様化学校」は、不登校児童生徒の実態に配慮し、特別の教育課程で教育を実施する学校で、他府県では柔軟な教育課程が児童生徒の登校意欲につながることが報告されており、今後、設置に向けての課題を整理します。 |
| 犯罪被害者等支援 | |
問 |
犯罪被害者等支援に関する現在の県の取組について伺う。 |
答 |
相談やカウンセリングなどによる精神的被害等の回復を図る取組のほか、弁護士による無料法律相談の実施、国の犯罪被害者等給付金が支給されるまでの間に必要な医療費等を支援する生活資金の貸付けなどを行っています。 さらに、加害者から損害賠償金が支払われず消滅時効が迫っている場合、時効を更新するため、再度、損害賠償請求訴訟を提起する費用の助成を、今年度から新たに始めています。 |
| 看護師の確保対策 | |
問 |
地域医療存続のためには、ナースセンターが担う看護師の復職支援の取組が重要と考えるが、県としてどのように取り組んでいるのか。 |
答 |
 看護師の復職支援については、離職中の看護師が知識や技術の学び直しをするための研修や、ハローワークとの連携による就職先とのマッチングなどの事業を実施しています。さらに今年度から、インターネットを活用した相談支援を開始し、ナースセンターの利用促進を図っているところです。 看護師の復職支援については、離職中の看護師が知識や技術の学び直しをするための研修や、ハローワークとの連携による就職先とのマッチングなどの事業を実施しています。さらに今年度から、インターネットを活用した相談支援を開始し、ナースセンターの利用促進を図っているところです。
|
| 県立高校生の海外大学進学 | |
問 |
高校卒業から海外に進学する方が全国的に増えているが、本県の状況について伺う。 |
答 |
本県の県立高等学校から海外の大学への進学状況は、2022年度からの3年間で14名となっており、新型コロナウイルス感染症発生前の2017年度からの3年間の8名に比べて増加しています。 進学先については、大韓民国、マレーシア、中華人民共和国、アメリカ、エストニア、ノルウェー、オーストラリアの大学となっています。 |
| 教育行政のあり方 | |
問 |
教育行政のあり方について、どのような組織運営が望ましいと考えるか。 |
答 |
校長をはじめ管理職は、教職員の模範となり、教育活動をけん引し、学校運営を担っていると認識していますが、学校運営や様々な対応について課題が生じた場合は、県教育委員会事務局が学校に指導・支援を行い、伴走して課題に対応するよう努めます。 県教育委員会としては、教職員一人一人が自由に意見を言え、みんなで教育改革を進められるよう、風通しのよい教育行政を構築していきます。 |
| 県立自然博物館のリニューアルに向けて | |
問 |
リニューアルに向け、海南市の協力を得ながら進める必要があるが、県の考え、責務について知事に伺う。 |
答 |
 県立自然博物館 |
| 知事の危機管理体制 | |
問 |
知事の危機管理体制について、どのような対策を講じるか。 |
答 |
知事の危機管理体制については、従来からの非常時の連絡体制や警備体制に加えて、公務終了以降における体調の急変を把握する民間サービスを活用するなどの対策を講じ、一層強固な危機管理体制の整備を図っていきます。 また、連続勤務の制限や定期的な健康診断の受診など、知事の健康管理上の留意すべき点をルール化し、厳格に運用していきたいと考えています。 |

