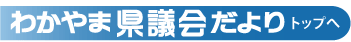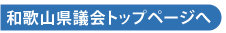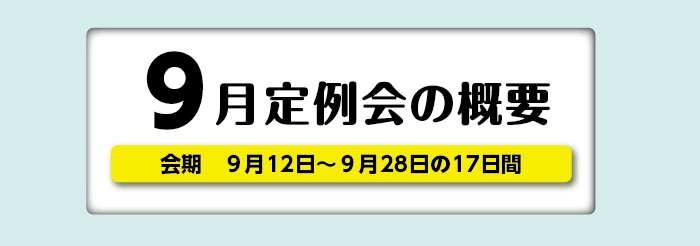
会期中の主な動き
特別委員会の開催
■人権・少子高齢化問題等対策特別委員会…9月20日
特別委員会の設置
■決算特別委員会を設置し、委員を選任…9月28日
【一般質問議員 16人】
|
9月19日(火)
堀 龍雄 |
9月20日(水)
坂本 登
佐藤 武治 中尾 友紀 森 礼子 |
9月21日(木)
玉木 久登
坂本 佳隆 山家 敏宏 中西 徹 |
9月22日(金)
三栖 拓也
林 隆一 藤本 眞利子 中村 裕一 |
議決結果・意見書等
| 項目 | 件数 | 概要 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予算案件 (知事提出) |
1件 | 令和5年度和歌山県一般会計補正予算 | 可決 |
| 条例案件 ( 〃 ) |
4件 | 旅館業法施行条例の一部を改正する条例 ほか | 可決 |
| 決算案件 ( 〃 ) |
2件 | 令和4年度和歌山県歳入歳出決算の認定について ほか | 継続 審査 |
| 人事案件 ( 〃 ) |
1件 | 和歌山県教育委員会の委員の任命につき同意を求めるについて | 同意 |
| その他案件 ( 〃 ) |
14件 | 令和5年度建設事業施行に伴う市町村負担金について ほか | 可決 |
| 知事専決処分報告 ( 〃 ) |
1件 | 訴訟の提起について | 承認 |
| 請 願 | 1件 | 現行の健康保険証を残すことを求める請願 | 不採択 |
| 意見書 | 5件 | 物価高騰対策の強化を求める意見書 | 可決 |
| ALPS処理水の海洋放出による影響に対する水産業支援の強化を求める意見書 | |||
| 防災・減災、国土強靱化等に資する社会資本整備の推進を求める意見書 | |||
| ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)に対する適正な診療上の評価等を求める意見書 | |||
| 下水サーベイランス事業の実施を求める意見書 |
主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、次のとおりです。(要約)
| 県独自の被災者生活再建支援制度 | |
問 |
6月の大雨による浸水被害において、隣接する市町で災害救助法の適用に違いが生じた。適用基準の見直しを要望するとともに、基準が見直されるまでの間、県独自の支援制度の導入などを検討してはどうか。 |
答 |
災害救助法の適用基準については、国に対して見直し要望を行ったところです。 一方で、国の基準の見直しには時間がかかることも想定され、同一災害で被害を受けた方に、同一の支援を行うために、県内市町村や他府県の状況などを踏まえながら、県独自の被災者生活再建支援制度の新設や、見舞金の見直しを検討します。 |
| 産科医の確保 | |
問 |
産科医不足が問題と考えるが、今後のさらなる取組について伺う。 |
答 |
 昨年度、県外の大学に依頼し、県内公立病院へ産科医を派遣してもらっています。さらに、県立医科大学では、即戦力となる産科医の確保を図るため、新たに講座を開設するとともに、中長期的な対応策として、新たに産科を指定した入学枠を設け、医師の偏在対策を強化しています。 昨年度、県外の大学に依頼し、県内公立病院へ産科医を派遣してもらっています。さらに、県立医科大学では、即戦力となる産科医の確保を図るため、新たに講座を開設するとともに、中長期的な対応策として、新たに産科を指定した入学枠を設け、医師の偏在対策を強化しています。産科医の確保に向けては、勤務環境の改善など、あらゆる対応策を検討しており、県立医科大学の協力の下、諦めることなく、やれることは全て対応していきます。 |
| スポーツを核とした地域振興 | |
問 |
「和歌山IR」に代わるビッグプロジェクトとして、Jリーグなどのスポーツを核とした地域振興等に取り組むべきと考えるがどうか。 |
答 |
県外からの人の流れを創出するとともに、地域に経済波及効果を与えるビッグプロジェクトは、地域活性化の起爆剤として、県で取り組むべきものと考えますが、一朝一夕に見つかるものではありません。 スポーツを核とした地域振興は、住民や企業など地域が一体となって盛り上がり、賑わいの創出につながる可能性があるため、こうした地域振興策を含め、様々な方面の案件について、機会を逃すことのないよう、しっかりと情報を収集していきます。 |
| 無形民俗文化財の現状と保存 | |
問 |
国・県指定の無形民俗文化財の現状と、保存に向けた対策について伺う。 |
答 |
 熊野本宮の湯登神事 県では、保護団体が行う道具類の修繕や新調、後継者養成のための講習会の開催等の事業に対し補助を行っているほか、休止した活動の再開時における活用や、普及啓発のため、民間の助成金等による記録映像の作成を働きかけています。 今後も国の動きや他府県の取組等も注視しながら、伝統行事や民俗芸能等を、次世代へと継承していけるよう取り組みます。 |
| 農業後継者の確保 | |
問 |
農業の後継者確保に対する県独自の取組について伺う。 |
答 |
農業後継者の確保のため、各産地に就農希望者を受け入れる協議会の設置を進めており、これまで8つの協議会において、協力農家の下での実践研修や農地の確保、販路の紹介などを行ってきました。加えて、本県に就農希望者を呼び込むため、国の給付金に年間30万円を県費で上乗せしているほか、中古機械の購入支援など、県独自の支援を行っています。 今後も、効果的な担い手確保策の強化を図り、新規就農者の確保に努めます。 |
| ドクターヘリについて | |
問 |
東牟婁郡からの要請の場合、どの程度で県立医大病院へ到着できるのか。要請重複時の応援体制はどのようになっているのか。 |
答 |

ドクターヘリ また、東牟婁郡は奈良県と三重県が、相互応援で対応することになっており、和歌山県のドクターヘリと比べて、多少時間はかかりますが、ほぼ同様の対応ができています。 |
| 子供医療費の無償化 | |
問 |
高校卒業までの、子供医療費の無償化について伺う。 |
答 |
現在、県内の全市町村が中学校卒業まで、そのうち22市町村が18歳まで対象年齢等を拡大して、医療費の自己負担分を、市町村独自に助成しています。 市町村への補助の対象年齢拡大は、多額の恒久財源が必要となります。 県としては、国に対して全国一律の子供医療費助成制度の創設を講ずるよう要望を行うとともに、現状の就学前の乳幼児を対象とした市町村への医療費助成制度を堅持しつつ、賢い予算のやりくりで、恒久財源の確保に努めます。 |
| 南紀白浜空港国際線ターミナルの利用促進 | |
問 |
南紀白浜空港の運営権者が掲げた搭乗者数の数値目標や、県としての今後の計画等について伺う。 |
答 |
運営権者である株式会社南紀白浜エアポートは、2028年度の総搭乗者数を約25万人、うち国際線の搭乗者数を約5000人とする目標を掲げています。 県としては、国際線ターミナルの利用を促進するため、関係者と連携して、国際チャーター便の受入体制に万全を期すとともに、アジア諸国を中心に、航空会社や旅行会社にアプローチするなど、引き続き、国際チャーター便を積極的に誘致していきます。 |
| ENEOS和歌山製油所事業再構築の現状 | |
問 |
「和歌山製油所エリアの今後の在り方に関する検討会」におけるとりまとめの進捗状況について伺う。 |
答 |
ENEOSと県、市、国による検討会が9月5日に中間とりまとめを公表し、和歌山製油所エリアが、今後、「未来環境供給基地」としてGXモデル地区を目指すことや、エリアのゾーニング、一定の雇用規模の見通しについて明示しました。 「未来環境供給基地」が実現すれば、地元の経済や雇用は持続可能なものとなり、脱炭素先進県として和歌山がカーボンニュートラル社会の実現に向けたモデルとなることから、県としても、関係者と協議をしながら、全力で取り組んでいきます。 |
| 災害への対応 | |
問 |
6月の梅雨前線による大雨及び台風第2号による被害の検証について伺う。 |
答 |
6月の豪雨では、本県に線状降水帯が発生し、多くの家屋で浸水被害等が発生しました。現在、線状降水帯予報に対応した職員の防災体制や、被災市町村からの情報収集、児童生徒の安全な登下校の判断などの課題を選び出し、検証を行っています。 その結果、8月の台風第7号における災害対応では、6月の経験を生かし、市町村へのリエゾン(現地情報連絡員)派遣や、市町村と振興局間のホットライン開設といった、体制強化を図りました。 |
| 災害情報の周知 | |
問 |
ホームページによる災害情報の周知について伺う。 |
答 |
 防災わかやまホームページは、各種の災害情報を、リアルタイムで確認することができるポータルサイトで、避難情報や道路の規制状況などが確認できます。 防災わかやまホームページは、各種の災害情報を、リアルタイムで確認することができるポータルサイトで、避難情報や道路の規制状況などが確認できます。災害時においては、情報伝達が非常に重要であるため、今後もあらゆる機会を捉え、防災わかやまホームページと、和歌山県防災ナビアプリの周知に努めるとともに、アプリでも、防災わかやまホームページによるリアルタイムの災害情報を確認できるよう、機能追加を進めます。 |
| 県証紙の廃止 | |
問 |
キャッシュレス決済が進む中、県証紙の段階的廃止に向けた取組について伺う。 |
答 |
パスポートセンターでは、2019年4月に、県証紙の取扱いを廃止しており、本年度は運転免許関連の主要窓口3か所において、キャッシュレス決済が可能なシステムを導入予定です。 キャッシュレス決済の導入は、県民の利便性向上に資する一方、システムの構築・維持に一定の費用を要するため、手数料受領窓口における件数、収入額、業務の増減等を勘案しながら、段階的廃止に取り組みます。 |
| ICT教育の推進 | |
問 |
ICT教育の推進に必要なインフラ整備に、どう取り組むのか。 |
答 |
ICT教育を進める中で、学校現場では、ハード、ソフト面で様々な課題があります。 中でも、通信環境の改善は最重要課題と考えており、学校内の通信回線の遅延原因を調査するアセスメント(通信ネットワーク環境の評価)の実施を促進し、早急に通信環境の改善に取り組みます。 また、教員のICT活用指導力の向上や、授業等におけるICT活用をサポートする支援員の配置など、市町村と連携しながらソフト面の改善にも取り組みます。 |
| 通信制高校の現状 | |
問 |
県内の通信制高校の現状と、積極的な周知について伺う。 |
答 |
県立高校通信制課程は3校あり、本年5月現在、1375名の生徒が在籍しています。 また、昨年3月に中学校を卒業し、県立高校通信制課程に進学した生徒は74名で、私立の広域通信制高校で学ぶ生徒を含め、157名が通信制課程に進学し、その数は年々増加しています。 進路選択に関しては、将来を展望し、自らの意志と責任で進路を決定する力をつけていくことが重要です。そのために、通信制課程のみならず、各学校・課程が、その特性を全ての中学生が理解できる広報に努めるよう指導していきます。 |
| 部落差別解消への取組 | |
問 |
部落差別解消のため、外部の専門家で組織する機関を設置し、意見を聴く仕組みをつくり、条例に規定すべきではないか。 |
答 |
部落差別事件が発生した場合の意見を聴く機関の設置については、仕組みとしては、既に附属機関として存在しており、事件の調査で疑義が生じた場合は意見を聴くこととなっていますが、さらにどういうことができるかを、現在の仕組みも踏まえながら検討していきます。 また、部落差別解消に向けて、できることは何でもやる、という考えのもと、条例改正を検討しており、少しでも現状を改善できるよう、部落差別の解消に取り組みます。 |
| 路線バスの支援 | |
問 |
他府県より顕著な高齢化や人口減少、また、地理的要因も考慮して、県独自の支援を行うべきではないか。 |
答 |
路線バス事業者は、人口減少やドライバー不足の深刻化など厳しい経営環境にあり、これまでの支援策だけでは、地域住民や観光客等の貴重な移動手段を守ることが困難になる と考えています。 と考えています。県では、市町村、交通事業者、関係団体などと議論しながら、「地域公共交通計画」の策定を進めており、バスの利便性向上や利用促進に向けた改善策を計画に位置付け、着実に取り組みます。 |