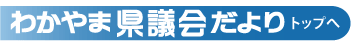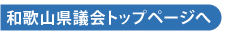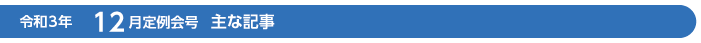

会期 11月29日〜12月17日の19日間
質問議員 16人 |
||||||
12月8日(水)
中本 浩精
中 拓哉 玄素 彰人 高田 由一 |
12月9日(木)
玉木 久登
奥村 規子 片桐 章浩 濱口 太史 |
12月10日(金)
長坂 隆司
北山 慎一 山家 敏宏 中西 徹 |
12月13日(月)
佐藤 武治
楠本 文郎 林 隆一 尾﨑 太郎 |
|||
議案等の議決結果
| 項目 | 件数 | 概要 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予算案件(知事提出) | 4件 | 令和3年度和歌山県一般会計補正予算 等 | 可決 |
| 条例案件( 〃 ) | 11件 | 知事及び副知事の給与その他の給与条例の一部を改正する条例 等 | 可決 |
| 決算案件( 〃 ) | 2件 | 令和2年度和歌山県歳入歳出決算の認定について 等 | 認定 |
| その他案件( 〃 ) | 26件 | 令和3年度建設事業施行に伴う市町村負担金について 等 | 可決 |
| 意見書・決議 | 12件 | 介護職種における外国人技能実習制度の見直しを求める意見書 | 可決 |
| 「こども家庭庁」の早期設置を求める意見書 | |||
| ヤングケアラーへの支援強化を求める意見書 | |||
| 定期接種の機会を逸した女性に対するヒトパピローマウイルスワクチン接種機会の確保及びより効果の高いがん予防対策を求める意見書 | |||
| 地域公共交通への支援の強化を求める意見書 | |||
| シルバー人材センターに対する支援を求める意見書 | |||
| 参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書 | |||
| 衆議院議員選挙制度の抜本的な改革を求める意見書 | |||
| 北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組を推進する決議 | |||
| 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書 | 否決 | ||
| 「土地利用規制法」に基づく注視区域の指定に当たり地元自治体の意見聴取を求める意見書 | |||
| 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書 |
主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、次のとおりです。(要約)
| ライフラインの点検 | |
問 |
和歌山市六十谷の水管橋の一部が崩落し、大規模な断水が発生したが、それを受けたライフラインの点検内容と今後の取組について伺う。 |
答 |
崩落事故を契機として、県、国機関、市町村、民間事業者が連携し、道路や水道など11項目のライフラインについて、地震や津波等に対する「強靭性」と、道路等が複線化されているかという「ネットワーク」を点検しています。それぞれが点検結果を受けて、緊急対策が必要なもの、中長期計画で取り組むものなど、予算措置も含めて必要な対策をとっていくものと考えます。 
六十谷水管橋 
給水の様子 |
| 南海本線紀ノ川橋梁への対策 | |
問 |
六十谷水管橋崩落事故を受けて、南海本線紀ノ川橋梁の定期点検や今後の対策をどう考えるか。 |
答 |
南海電鉄によると、定期的な全般検査等の結果、橋梁の健全性を確認しており、また、通常の検査に加えてドローンでの点検も試験的に実施し、その有用性を検討していくとのことです。 |
| スーパーシティ構想 | |
問 |
スーパーシティ構想のこれまでの経緯や県の取組姿勢について伺う。 |
答 |
県とすさみ町では、「南紀熊野スーパーシティ構想」をとりまとめ、令和3年4月、国に提案しました。しかし、大胆な規制改革の提案が乏しいとされ、本県を含む全ての団体に対し再提案が求められました。
スーパーシティ
これを受け、県とすさみ町では、住民による来訪者への食事提供を可能とする食品衛生法の施設基準の緩和などの規制改革をとりまとめ、10月に再提案を行ったところです。大胆な規制緩和と生活全般にまたがる先端的サービスの社会実装により、住民が抱える社会的課題を解決し、未来社会の先行実現を目指す都市のこと。 今後、国から区域指定を受け、この構想を実現できるようすさみ町とともに全力を挙げて取り組んでいきます。 |
| 住宅耐震化促進事業 | |
問 |
住宅耐震化促進事業は現地建て替えも補助対象となっているが、当該事業における耐震改修と現地建て替えの割合と、今後の制度の進め方について伺う。 |
答 |
耐震性能が極めて低く、改修に多額の費用を要する住宅を対象に現地建て替えを支援しています。平成26年度の事業導入時は、建て替えを行った住宅は24件で全体の約2割でしたが、令和2年度には121件と約4割まで増加しています。 |
| 県営住宅の浸水対策 | |
問 |
公営住宅の浸水対策は避難訓練等のソフト面での対策が目立つと聞くが、本県の県営住宅ではどう取り組んでいるか。 |
答 |
ソフト対策としては、入居者への洪水・津波の浸水想定による水深の周知、早期避難の働きかけ、上層階に避難が可能な団地については、垂直避難の啓発などを行っています。 |
| 県営住宅の入居者資格 | |
問 |
県営住宅の入居者資格について、一人暮らしの高齢者同士の入居を認めるなどさらに緩和する意向はあるか。 |
答 |
入居者の募集は、同居親族を前提としており、現状においても、2倍程度の競争倍率があることから、当面、その前提を変更することは難しい状況です。 |
| 地域おこし協力隊の受入拡大 | |
問 |
地域おこし協力隊の積極的導入に向けた市町村への働きかけについてどう考えるか。 |
答 |
県内において活動している隊員数は令和2年度で52人と、全国的に見ると少ない状況です。この要因について、市町村に対するヒアリングや全国状況を調査したところ、市町村単独では応募者が集まりにくいことや、市町村の受入態勢が十分ではない等の課題が明らかとなりました。 |
| ユニバーサルツーリズムの推進 | |
問 |
ユニバーサルツーリズム(バリアフリー観光)に係る県の取組について伺う。 |
答 |
事業者へのバリアフリー観光に対する意識の向上を図るとともに、公衆トイレの整備や宿泊施設のバリアフリー改修の補助、観光地のバリアフリー情報の発信などに取り組んでいます。 |
| 矢羽根型路面表示 | |
問 |
矢羽根型路面表示をよく見かけるが、設置の目的は何か。 |
答 |
道路交通法上、自転車は車道の左側を通行することが原則です。表示は、自転車利用者に走行する車道の空間と向きを、自動車運転手に自転車が走行する空間であることを示す目的があります。 |
| 産業部門の省エネ化 | |
問 |
産業部門の省エネ化を進めるために支援策の充実が必要と考えるが、県の考えはどうか。 |
答 |
企業の省エネ推進の支援については、平成29年度から令和元年度まで省エネ設備の導入支援を県単独事業として実施するとともに、今年度から、ものづくり企業における生産性向上のための県単独補助制度を設けており、その中で、省エネ設備も補助の対象としています。 |
| 新型コロナウイルス感染症への今後の対応 | |
問 |
新型コロナウイルス感染症に係る支援として、病床確保料について県独自で上乗せ補助を行っているが、今後も継続するのか。 |
答 |
入院医療機関における新型コロナウイルス感染症患者の受入病床の確保に係る財政支援については、次の感染拡大に備え、あらかじめ病床を確保しておく必要があることから、引き続き県独自の上乗せ補助を行い、患者の全員入院を堅持していきます。 |
| 県内の医師偏在 | |
問 |
県内の医師偏在の解消と、緊急性の高い新宮市立医療センターの産婦人科医確保にどう取り組むか。 |
答 |
将来にわたり地域医療を担う医師を確保するため、県立医科大学地域医療枠等の医師の県内中山間地域等への適正な配置、特定診療科での勤務を条件とする返還免除つき資金貸与制度の積極的な運用、県立医科大学医学部の定員確保等に取り組んでいます。 |
| 医療的ケア児への支援 | |
問 |
医療的ケア児支援センターの設置と対応できる人材の育成をどう考えるか。 |
答 |
医療的ケア児
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他の医療行為を受けることが不可欠である児童のこと。 医療的ケア児とその家族を支援できる各地域での体制整備を優先すべきと考え、そのためには、対応できる人材(医療的ケア児コーディネーター)の育成が重要と考えています。 |
| 潜在看護師の活動状況 | |
問 |
潜在看護師の状況と、新型コロナウイルス感染症対策にどのような役割を担っていたのかについて伺う。 |
答 |
感染対策に従事する医療人材を確保するため、令和2年11月には全国に先駆けて、県看護協会と契約を締結し、潜在看護師を派遣する体制を整備しました。県ナースセンターを通じて、潜在看護師に協力の呼びかけを行ったところ、これまで延べ1139人の潜在看護師が県内各保健所で疫学調査と健康観察に従事しました。また、宿泊療養施設での健康管理業務に45人が、ワクチンの集団接種や職域接種の業務に41人が従事したところです。 |
| 紀州材の利用推進 | |
問 |
公共土木工事における紀州材の利用状況、課題、今後の方向性について伺う。 |
答 |
主に木製ガードレールや道路法面(のりめん)の法裾(のりすそ)を覆う丸太伏工(まるたふせこう)などに利用しています。  木製ガードレール(県道南紀白浜空港線) 今後の方向性については、課題解決のため、県発注工事における優遇措置等を通じて、県内企業に技術開発を促すとともに、各種マニュアル等の早期整備や河川や砂防等の現場に利用範囲を拡大できるよう調査研究を進めていきます。 |
| 脱炭素社会の実現に向けて | |
問 |
エネルギー新分野の研究を行う企業等の誘致についてどう考えるか。 |
答 |
エネルギーに関する新分野の企業誘致については、弊害がある場合を除き、あらゆる分野でチャンスがあれば取り組まなければならないと考えています。 |