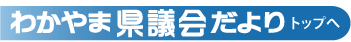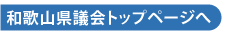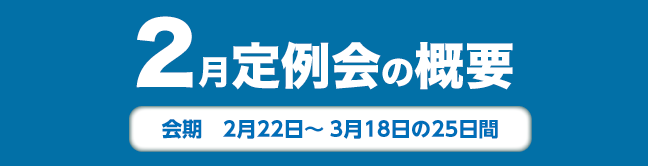

特別委員会の開催
●防災・国土強靭化対策特別委員会…3月5日
●半島振興・地方創生対策特別委員会…3月9日
選挙の実施
●和歌山県選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙…3月18日
質問議員 18人 |
||||||||
3月4日(木)
藤山 将材
多田 純一 |
3月5日(金)
秋月 史成
浦口 高典 鈴木 德久 佐藤 武治 |
3月8日(月)
中西 徹
山家 敏宏 奥村 規子 藤本 眞利子 |
3月9日(火)
川畑 哲哉
片桐 章浩 杉山 俊雄 尾﨑 太郎 |
3月10日(水)
谷口 和樹
北山 慎一 楠本 文郎 井出 益弘 |
||||

| 項目 | 件数 | 概要 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予算案件(知事提出) | 33件 | 令和3年度和歌山県一般会計予算 等 | 可決 |
| 条例案件( 〃 ) | 28件 | 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例 等 | |
| 条例案件( 〃 ) | 2件 | 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 等 | 継続審査 |
| 人事案件( 〃 ) | 17件 | 和歌山県教育委員会の教育長の任命につき同意を求めるについて 等 | 同意 |
| その他案件(議員提出) | 1件 | 和歌山県議会会議規則の一部を改正する規則 | 可決 |
| その他案件(知事提出) | 22件 | 令和3年度建設事業施行に伴う市町村負担金について 等 | |
| 請願 | 1件 | 後期高齢者の医療費窓口自己負担2割化方針の撤回を国に求める意見書の提出を求める請願 | 不採択 |
| 意見書 | 6件 | 大学等における新年度の授業の実施に関する意見書 | 可決 |
| 「新型コロナウイルス」ワクチン接種に関する意見書 | |||
| 緊急事態宣言により影響を受けた全国の事業者への支援及び雇用対策についての意見書 | |||
| 「GoToトラべル事業」に係る意見書 | |||
| 核兵器禁止条約の批准を求める意見書 | 否決 | ||
| 核廃絶に向けた取り組みを求める意見書 |
主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、次のとおりです。(要約)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、保健医療行政を強化するとともに、苦境に立たされている地域経済や雇用等を守り抜くことが必要です。
一方で、コロナ後の新しい世界の流れをうまく取り入れ、新たな取組に挑戦していくことも重要です。
新政策では「コロナ禍から経済とくらしを守り抜く」「新しい世界への対応と挑戦」の2つの政策を柱として積極果敢に施策を展開して、コロナ危機からの難局を乗り越えていくとともに、和歌山を元気にし、力強い再生・発展を実現するため、全力で取り組んでいきます。
県では第3波の状況を踏まえ、県環境衛生研究センターに遺伝子解析機器を新たに導入するなど、さらなる検査体制の充実に取り組んでいます。
また、高齢者等が入所する施設では、施設内での感染拡大を防止するため、簡易に検査ができる抗原検査キットを配付し、新規入所者を対象としたスクリーニング検査を行っていきます。
県では、誹謗中傷等が発生した場合、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例に基づき、誹謗中傷等をやめるよう指導します。
また、誹謗中傷等は刑事罰や被害者からの損害賠償請求のおそれがあり、行った人自身の人生も変えてしまいます。県民に対して、誹謗中傷等を決して行わないよう、県の広報媒体やチラシ配布等により、強く訴えかけていきます。
電話:073-441‐2563
ファックス:073‐433‐4540
今後も、県の広報媒体や市町村の広報誌等により、専用の相談窓口「コロナ差別相談ダイヤル」を周知し、誹謗中傷等に悩まれている人が一人で悩まずに相談いただけるよう取り組みます。また、新たに啓発チラシを作製し、各家庭へ配布すること等により、広く県民に対して誹謗中傷等を行わないよう訴えかけていきます。
PCR検査は、医師が新型コロナウイルスの感染を疑う者に対し、診断を行うために実施する病原体検査で、感染の可能性を考慮せず、やみくもに検査を実施すればいいというものではありません。
県では、PCR検査の重要性を認識し、感染者の早期発見に不可欠となる検査体制の強化・拡充に努めてきました。適切に対象者を選定し、広く迅速に徹底した検査を実施する本県のスタイルにより、引き続き、感染拡大防止に取り組んでいきます。
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供のこと。
ヤングケアラーの実態を把握するため、厚生労働省と文部科学省が連携し、中学校2年生及び高校2年生を対象に無作為抽出の全国調査が実施されています。
県としては、国の調査・分析結果の動向を注視しながら、県独自の調査の必要性について検討していきます。
高性能マイクで集音し、小型スピーカーからクリアな音を発することにより、聴こえをよくするための支援機器のこと。
聴覚障害のある方や加齢により聞こえづらい高齢の方などと円滑にコミュニケーションを図ることは重要であり、筆談やコミュニケーションカードの活用を進めています。
対話支援スピーカーも、有効な手段の1つと考えられるため、県の関係課室に対し、周知していきます。
京奈和自動車道の延伸は、和歌山市北部地域の利便性の向上や、中心部の渋滞緩和などの課題解消、地域経済の活性化、そして関西大環状道路の一部を形成することにつながります。
この道路の実現は、最重要課題であり、早期に事業が実施されるよう、引き続き、国に対して働きかけていきたいと考えています。
令和2年12月11日に防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策が閣議決定され、初年度予算を含む国の第3次補正予算が本年1月28日に成立しました。
これは通常予算と別枠で防災関係に重点を置いた15兆円の予算が確保されたということで、この予算を最大限に活用して、この機を逃すことなく治水事業を加速化させていきたいと考えています。
新型コロナウイルス感染症の影響で定期便の航空需要が減少する一方で、不特定多数の人と同席せず安全に移動できる手段としてビジネスジェットが注目されており、今後、利用者も増加するものと想定していることから、この好機を逃すことなく新しい時代の挑戦を体現する取組の一つとして、令和4年度の完成を目指して、令和3年度中に着手します。
クレジットカードや電子マネーを利用したキャッシュレス決済は、証紙に代わる納付方法として、有効な手段だと考えます。
県民の利便性を高めるため、多様な納付方法としてキャッシュレス決済の実現は必要であり、電子申請など行政手続のオンライン化の推進に合わせ、収納システムの構築や運営にかかるコストを勘案の上、段階的な導入を検討していきます。
二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いて、全体として排出ゼロを達成する取組。
第5次和歌山県環境基本計画では、2050年カーボンニュートラルを目指すことを示したいと考えており、これを達成するために、あらゆる場面での省エネ、再生可能エネルギー導入、イノベーションが不可欠であり、本県が実行可能な対策を積極的に取り入れ、脱炭素社会の推進に取り組んでいきます。
ヘルスケアに係る課題解決や健康寿命延伸につながる産業の創出・振興のために、地域のヘルスケア関係者(自治体、医療・介護関係者団体、民間事業者など)が連携する協議会のこと。
ヘルスケアに関連する産業創出及び振興を図るため、東京医療保健大学和歌山看護学部、和歌山県立医科大学薬学部などに、わかやまへルスケア産業革新プラットフォームへの参画を働きかけるなど、健康・医療・福祉分野のニーズと産業界のシーズのマッチングによる新産業の創出・発展に向けた取組を進めていきます。
洋上に風力発電を設置するには、和歌山県周辺の海は、黒潮の流れが速く、気象、海象が荒々しい上、海そのものが観光資源であり、景観や騒音など様々な環境上の問題も考慮しなければなりません。また、船舶の往来や漁業者の活動など経済的な問題もあります。
それらの問題をクリアする必要があるため、慎重かつ賢明にこの問題に対処していきます。
県では新過疎法の制定及び現行過疎法における「みなし過疎」の継続指定、また過疎対策予算の確保などについて、国等に強く要望してきました。
過疎対策を継続するため、法による国の支援もうまく使いながら、県としても過疎地域に暮らす人々が夢や希望をもって元気に暮らせるように引き続き全力で取り組んでいきます。
偏差値等の一面的な指標による高校選びから脱却するためには、県教育委員会が長期的展望を明確に示し、生徒が夢や希望をもって人生を切り拓くことや、教師が前向きに取り組む中で資質能力を向上させることを促し、結果として、各校の魅力化・特色化につなげていくことが重要です。今回の再編整備は、まさにその具体化であり、鋭意取り組んでいます。
発生農場の経営再開に当たっては、鶏舎側面の金網等の破損や小型の野生動物が進入可能な壁の穴の修繕を行い、国が定める飼養衛生管理基準を満たす必要があります。
県では、衛生管理の強化等を推進するため、新政策として「畜産施設衛生管理強化支援事業」を推進し、養鶏農場での衛生管理の強化を図っていきます。
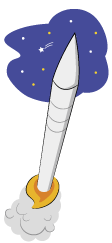
国道42号を走行する車両を円滑に流すための信号時間の調整や、見学場周辺の駐停車禁止規制を考えており、今後、通行禁止規制による生活ゾーンへの流入車両の抑制等についても検討していきます。
また、治安・防犯面については、関係機関等と連携し、予想される状況等を把握した上で、パトロールの強化等必要な対策を講じることとしています。