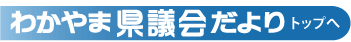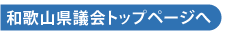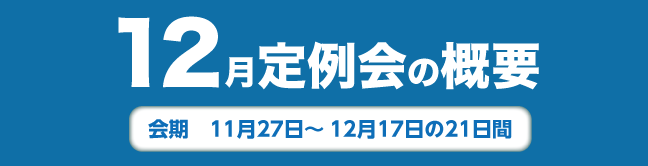

特別委員会の開催
●行政改革・基本計画等に関する特別委員会…12月10日
●人権・少子高齢化問題等対策特別委員会…12月11日
質問議員 16人 |
||||||
12月8日(火)
中本 浩精
坂本登 岩井 弘次 林隆一 |
12月9日(水)
鈴木 德久
高田 由一 谷口 和樹 玄素 彰人 |
12月10日(木)
長坂 隆司
川畑 哲哉 杉山 俊雄 玉木 久登 |
12月11日(金)
片桐 章浩
奥村 規子 北山 慎一 森礼子 |
|||

| 項目 | 件数 | 概要 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予算案件(知事提出) | 2件 | 令和2年度和歌山県一般会計補正予算 等 | 可決 |
| 条例案件( 〃 ) | 13件 | 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例 等 | |
| 決算案件( 〃 ) | 2件 | 令和元年度和歌山県歳入歳出決算の認定について 等 | 認定 |
| 人事案件( 〃 ) | 1件 | 和歌山県監査委員の選任につき同意を求めるについて | 同意 |
| その他案件( 〃 ) | 17件 | 令和2年度建設事業施行に伴う市町村負担金について 等 | 可決 |
| 請願 | 2件 | 和歌山、奈良、三重の三県をまたがった景観を重視する道路への木製ガードレールの積極的採用を求める請願 | 採択 |
| 国に対して「消費税率5パーセントへの引き下げを求める意見書」を提出することを求める請願 | 不採択 | ||
| 意見書・決議 | 10件 | 天皇陛下に差し上げる賀詞 | 可決 |
| 皇嗣殿下に差し上げる賀詞 | |||
| 公共事業における木材の活用を求める意見書(関西広域連合長宛) | |||
| 公共事業における木材の活用を求める意見書(奈良県知事、三重県知事宛) | |||
| 台湾の世界保健機構(WHO)への参加を求める意見書 | |||
| 義務標準法の改正による30人以下学級の実現を求める意見書 | |||
| 新たな過疎対策法の制定を求める意見書 | |||
| 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書 | |||
| 犯罪被害者支援の充実を求める意見書 | |||
| 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 |
主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、次のとおりです。(要約)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、感染防止対策と経済活動の両立に取り組むとともに、和歌山の力強い再生・発展を実現していくことが重要です。
このため、令和3年度新政策については、「コロナ禍から経済とくらしを守り切る」と「新しい世界への対応と挑戦」の2つの政策を柱として施策を展開していきたいと考えており、議員や市町村の意見等も踏まえ、来年度予算案を作成し、2月定例会に提案します。
若者が社会問題に関心を持ち、問題の改善や解決に向けて熟議し、社会に向けて提言することは、社会参加に積極的な若者が育つことにつながり、有意義と考えます。さらに、若者のグループや団体が互いに交流や提携することで大きな力となり、社会をよりよい方向に動かしていくことも期待できます。県教育委員会では、若い世代に期待して、若者のグループや団体との関わりを大事にしていきます。
近年、男子の部活動しかなかった競技にも女子が取り組むようになる中で、女子競技者のための環境整備が必要になってきていると認識しています。
今後、再編整備の状況も勘案して、女子スポーツだけでなく、生徒が部活動に打ち込める環境づくりに努めていきたいと考えています。
県教育委員会では、今年度、修学旅行を実施した学校を対象にアンケート調査を計画しています。本年度内に調査結果をまとめ、来年度以降の修学旅行の行き先を検討する際の参考として、市町村教育委員会に情報を提供することで、今後も修学旅行が教育的意義を果たし、より充実したものとなるよう取り組んでいきます。
今後進める県立高等学校の再編整備においては、各地域に活力と魅力を備えた高校、自己実現が十分に果たせる高校を整備し、県内どの地域においても、格差なく質の高い教育が受けられるようにすることが重要であると考えます。
県教育委員会は、令和元年10月、 第6期きのくに教育審議会に対して、「これからの県立高等学校の在り方について~高等学校が地域とともに持続可能な存在であるために~」について諮問し、令和2年8月、同審議会により答申がとりまとめられました。
再編整備の目的は、単に学校を減らすことではなく、少子化が進んでも活力があり、地域の核となる学校を創造していくことです。
多くの県立高校が、従前の適正規模の基準を満たせなくなっていく中、6学級というのは、地域で魅力や活力、特色ある高校を整備していく上での目標値であり、決して学校数を減らすための基準ではありません。

県内外から多くの方が参加される中で、来県される方には、文化祭はもちろんのこと、自然や歴史、食のほか地域のおもてなし等を通して、和歌山県の魅力を堪能(たんのう)していただきたいと考えています。
また、県民の皆様には県内の様々な文化団体等の活躍を観て、聴いて、体験していただき、県内の文化芸術活動の輪が大きく広がることで心豊かな和歌山県を創造していきたいと考えています。
今般、同対策として、事業規模15兆円程度の予算措置がなされたことは本県における国土強靭化を一気に進めるチャンスであり、この機会を逃すことなく、安全・安心な社会基盤を確実に次の世代に継承するために、本県の国土強靱化を加速させていきたいと考えています。
旧南紀白浜空港跡地の利活用については、白浜町と連携して、観光地としての価値をより高めることを第一に考えてきました。
その上で、地域の観光産業との相乗効果が図れ、できるだけ高い集客力を持ち、地元雇用への貢献が見込まれる施設を誘致することが最もよいと考えており、それまでの間は、イベントでの活用など、いろいろな用途を引き続き考えていきます。
令和2年3月末時点では、超高速ブロードバンドと携帯電話の居住地域における整備率は、共に世帯カバー率で99.9パーセントとなっています。携帯電話は、令和5年度末までに、携帯キャリアによる居住地域の整備が完了すると聞いています。
今後は、居住地域で超高速ブロードバンドが未整備の地域や、居住地域以外でも利用が見込まれかつ通信事業者にもメリットのある地域では、引き続き整備を促していきます。
県では、共益費に関するアンケート結果等について、8月と9月に各団地の自治会を個別に訪問し、役員から意見を聞くとともに、10月に県が共益費を徴収することに関してのパブリックコメントを実施し、県民から意見を聞きました。
今後は、これらの意見を踏まえ、検討を行い、県が共益費を徴収できるように早ければ令和3年2月定例会での条例改正案の提出に向けて準備を進めていきます。
IRにおけるリスクは、実施協定等に特段の定めのない限り、IR事業者が負います。不可抗力事象が発生した場合も、原則として、IR事業者に生じた損害は事業者自らが負担します。また、IR事業者に何ら瑕疵(かし)がないにも関わらず、県が一方的にIR事業を継続できないような条例を制定すること等により、IR事業者に損失が生じた場合には、県が一定の財政負担を行うこととなります。
電子申請を既に導入している手続も含め、全庁調査に着手しているところです。
国においては、地方公共団体の情報システムの標準化などデジタル基盤の整備に向けた取組が進められており、引き続き、国の動向や他府県の状況を注視するとともに、情報格差にも配慮しつつ、各部局と協力しながら、行政手続のデジタル化・簡素化を推進していきます。
これまでも新たな産業の創出による地域経済の振興と雇用の創出を目指して企業誘致を推進してきた中、串本町にロケット発射場ができることを契機として、宇宙関連産業等の集積に向けた気運が高まるものと考えています。
県としては、既存の企業用地の活用はもちろん、東京一極集中の衰えや製造業の国内回帰がある程度進むといった新しい世界の動きを今はチャンスと捉え、宇宙関連産業等をはじめとするハイテク企業の誘致に全力を挙げて頑張ります。
24時間の電話相談やSNSの活用など、対面することなく相談できる体制の周知に努めています。
さらに、保健所においては、感染の不安から訪問を躊躇(ちゅうちょ)される方に対し、電話相談に切り替えるなど、相談者に寄り添った対応を行っています。
自殺未遂者の再企図の防止を図るため、地域の救急病院の協力のもと、昨年度から開始した自殺未遂者に対する相談支援についても、退院後速やかに相談が始められるよう取り組んでいます。
感染防止のためには県民一人一人の自覚ある行動や取組が重要です。
条例は県民の権利を制限したり、義務を課すときに必要なものであると考えており、感染防止の取組は、状況の変化に応じて時宜(じぎ)にかなった取組を機動的に県民に呼び掛けていくことが、最も効果的な方法であると考えています。
決算特別委員会では、令和元年度一般会計決算(歳入額:5563億余円、歳出額:5468億余円)のほか12特別会計の決算、及び公営企業決算(県立こころの医療センター事業会計など4事業会計)について、令和2年10月19日から21日まで審査を行い、決算議案を認定すべきものと決しました。
12月16日の本会議において、藤山将材委員長が、決算特別委員会における審査の経過・結果について報告を行い、採決の結果、決算議案が認定されました。