現在の位置:トップページ > 県議会からのお知らせ > 県議会だより >2月定例会号>平成31年2月定例会概要

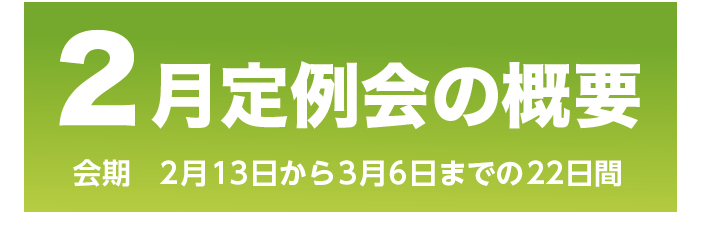
質問議員(17人) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
会期中の主な動き
議案等の議決結果
|
天皇陛下の御即位30年に慶祝の意を表し、 |
||
賀詞 |
||
主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は次のとおりです。(要約)
水産物の高付加価値化
生産者や県内の各種研究機関等が連携し、水産物由来の機能性に着目した高付加価値化を行ってはどうか。 |
様々な機能性成分を有する水産物や水産加工品の付加価値を高める取組は、重要であると認識しています。専門的知見を持つ県立医科大学などと連携し、また、県の試験研究機関の設備や機能を活用して、本県で水揚げが多い魚類や海藻類に含まれる機能性成分の研究を行うとともに、未利用資源の活用についても取り組んでいきます。 |
本県教育の方向性
第3期和歌山県教育振興基本計画が平成30年度スタートしたが、本県教育が進むべき方向性はどうか。 |
教育振興基本計画を着実に実現し、特に学校教育では、「知・徳・体」を基盤とした人間としての総合力の育成をめざしています。全ての人の「和」の力が結集したとき、本県の教育はよりよいものになると確信を持って取り組んでいます。 |
内水面漁業振興計画の策定
国は、平成26年に内水面漁業振興法を制定した。県では法の規定する計画が策定されていないが今後どうするのか。 |
法律では、都道府県は内水面漁業振興計画の策定に努めることになっており、既に14県で策定されています。本県においても今後速やかな計画の策定に向け、取り組んでいきます。 |
「内水面漁業」…河川・湖沼における漁業、養殖業 |
 |
児童虐待問題
児童相談所への児童福祉司などの人員配置や、県内市町村との連携は、どうなっているのか。 |
平成26年度から30年度までの5年間で、家庭支援などで中核的役割を果たす児童福祉司4名を含む、相談員業務担当職員7名と常勤弁護士1名の計8名の増員を行いました。また、市町村職員に対しては、虐待の兆候を決して見逃さず、早期発見に確実につなぐことのできるノウハウや児童相談業務に必要となる支援会議の運営方法等を学ぶための研修を行い、知識・技術の向上や均質化に努めています。 |
性同一性障害
性同一性障害の児童生徒に対してどのような配慮や対策が行われているのか。 |
平成27年に文部科学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」の通知が出されています。県教育委員会では、県内全ての学校に対し、その趣旨を周知するとともに、児童生徒の心情等に配慮しながら個々の状況に応じて対応するよう指導しました。各学校においては、児童生徒や保護者と相談しながら、制服やトイレ、更衣室の利用等、学校生活の各場面でそれぞれの児童生徒に応じた配慮を行っています。 |
暫定2車線の高速道路の安全対策
暫定2車線区間の対向車線へのはみ出し事故防止策はどうなっているのか。 |
|
南紀白浜空港の民営化
民営化に向けた現状と今後の取組はどうか。 |
本年4月1日から運営を行う(株)南紀白浜エアポートでは、羽田線の機材の大型化、成田線の新規就航、チャーター便誘致などの取組が行われる予定です。県では、既に新国際線ターミナルビルの設計に着手しており、2021年6月までの完成を目標に整備を進めていきます。 |
企業誘致と紀州材の利用促進
事務所等に紀州材を利用する県内進出企業に対し、奨励金制度の導入を検討してはどうか。 |
企業誘致に係る奨励金制度は、企業ニーズに対応しており、紀州材を利用した場合も交付の対象となっています。本県に進出する企業に対しても、強度や色合いに優れた紀州材の素晴らしさをPRし、需要拡大につながるよう取り組んでいきます。 |
放射性廃棄物処分場
原子力発電所の使用済み核燃料を再処理した際に出る高レベル放射性廃棄物いわゆる「核のごみ」処分の問題で、平成29年9月議会において、知事から「県内での調査を受け入れる考えはない」との答弁があったが、現在でも、考えに変わりはないのか。 |
本県は、巨大地震や津波の被害のおそれがあり、山間部にも結構人が住んでいるので、最終処分場や中間貯蔵地として最もふさわしくない場所ということは、理論的に明らかであり、調査を受け入れる考えはありません。 |
考古博物館建設計画
紀伊風土記の丘資料館を考古博物館に再編するための取組はどうか。 |
紀伊風土記の丘は、開館以来、約50年経過し、施設の老朽化や収蔵スペース不足などの課題を抱えています。このため、紀伊風土記の丘資料館を再編し、古墳文化や考古学、民俗学の研究拠点として展示や保存、研究の各機能を有する考古学民俗博物館に整備することとしており、平成31年度当初予算には、建設用地の取得経費を計上しています。 |
日本一の果樹産地づくり事業
| 産地と苗木組合との連携について県の役割はどうか。 |
県では、平成31年度、戦略品種推進協議会を新たに設置し、苗木組合と産地側の調整を行い、苗木の安定供給を図っていきたいと考えています。マーケットや苗木組合等と連携を密にしながら、戦略品種の早期産地化等を通じ、農家の所得向上に努めていきます。 |
スマホ依存
スマホ依存から児童生徒を守るための取組についてどうか。 |
|
県都和歌山市の人口減少
県都和歌山市の人口減少に対する現状認識と今後の取組はどうか。 |
自然増減に関しては、2003年に減少に転じ、2017年では1732人のマイナスとなっています。また、社会増減に関しては、1987年の2501人をピークとして転出超過数は縮減し、2017年では322人の超過となっています。人口減少に歯止めをかけていくため、長期的視点に立ち、自然減と社会減の両面から戦略的に施策を展開していきます。 |
和歌山市和泉山脈のメガソーラー計画
和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例において、事業計画に対する住民の意見はどのように取り扱われるのか。また、調査審議会はどのような専門家で構成され、どのような場合に意見を求めるのか。 |
意見書の提出があった場合、発電事業者に対し見解を求め、それらを踏まえ、事業計画が認定基準に適合しているかを科学的に審査します。調査審議会は、防災、安全、環境、景観分野の専門家で構成され、事業計画の審査において、環境保全上や災害発生防止上の見地から、必要な場合に意見を求めることとしています。 |
災害への備え
災害時に高齢者が徒歩でも避難できる身近な施設を増やすべきと考えるがどうか。 |
県では、平成23年の紀伊半島大水害の教訓を踏まえ、安全レベルを設定するなど避難場所の見直しを行い、また、市町村に対してはより多くの避難場所を確保するよう働きかけています。現在、県内では学校や公民館などの公共施設を中心に約1500カ所の避難場所が指定されています。県としては、引き続き避難場所の確保について働きかけていきます。 |
婚活支援事業の充実
婚活の支援には丁寧かつ大胆な「おせっかい」を行うことが重要であるが、事業充実への取組はどうか。 |
|
一時保護所の人員
一時保護所の絶対的な人員不足、特に夜間について、認識と改善はどうか。 |
夜間は、児童指導員と宿直業務員の各1名が、幼児の食事介助や情緒不安定児への添い寝などの生活支援を行っています。県としては、宿直業務員の充実など、適切な人員配置を図っていきます。 |
「一時保護所」…児童相談所に附設し、保護が必要な児童を一時的に保護する施設 |

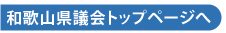
 京奈和自動車道など県内の暫定2車線区間は、大部分がラバーポールにより車線を区分する構造となっています。こうした構造では、対面交通による重大事故の発生につながることが懸念されるため、昨年5月、国に対し、車線逸脱防止機能を有するワイヤーロープの設置を要望し、昨年6月には、国から「暫定2車線の高速道路のワイヤーロープ設置方針について」の発表がありました。そして、本年1月の「平成31年度予算概要」には、高速道路の安全性等を向上させるため、ワイヤーロープを緊急対策として実施すると明記されています。県では、引き続き事故防止対策としてワイヤーロープの早期設置を働きかけていきます。
京奈和自動車道など県内の暫定2車線区間は、大部分がラバーポールにより車線を区分する構造となっています。こうした構造では、対面交通による重大事故の発生につながることが懸念されるため、昨年5月、国に対し、車線逸脱防止機能を有するワイヤーロープの設置を要望し、昨年6月には、国から「暫定2車線の高速道路のワイヤーロープ設置方針について」の発表がありました。そして、本年1月の「平成31年度予算概要」には、高速道路の安全性等を向上させるため、ワイヤーロープを緊急対策として実施すると明記されています。県では、引き続き事故防止対策としてワイヤーロープの早期設置を働きかけていきます。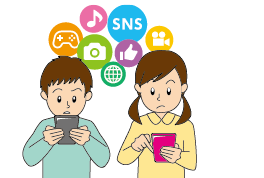 スマホ依存の内容や予防策等を示した児童生徒及び保護者向けのリーフレットを作成し、学校と家庭が協力して指導できるようにしていきます。また、ネット依存度をはかるチェックシートを作成し、各学校における児童生徒の個別指導に生かします。
スマホ依存の内容や予防策等を示した児童生徒及び保護者向けのリーフレットを作成し、学校と家庭が協力して指導できるようにしていきます。また、ネット依存度をはかるチェックシートを作成し、各学校における児童生徒の個別指導に生かします。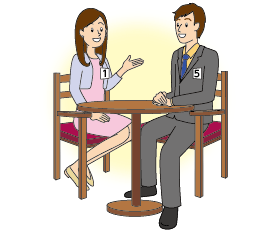 県の婚活イベント参加者には、事前に結婚カウンセラーによるコミュニケーション研修の受講を必須とする試みや、イベントでの結婚サポーターによる会話のきっかけづくりなど、カップリングへの後押しを行っています。婚活イベントを効果的な出会いの場とするため、参加者自身が積極的に行動できるよう、引き続き意識啓発に取り組んでいきます。
県の婚活イベント参加者には、事前に結婚カウンセラーによるコミュニケーション研修の受講を必須とする試みや、イベントでの結婚サポーターによる会話のきっかけづくりなど、カップリングへの後押しを行っています。婚活イベントを効果的な出会いの場とするため、参加者自身が積極的に行動できるよう、引き続き意識啓発に取り組んでいきます。