現在の位置:トップページ > 県議会からのお知らせ > 県議会だより > 9月定例会号>平成23年9月定例会概要

| 会期中の主な動き |
![]() 特別委員会の開催
特別委員会の開催
東南海・南海地震等対策特別委員会(9/8、27)
![]() 条例案検討会の開催
条例案検討会の開催
歯科保健推進に係る条例案検討会(9/9、26)
![]() 特別委員会の設置
特別委員会の設置
決算特別委員会を設置し、13人の委員を選任(9/28)
| 決算特別委員会(定数13人) |
平成23年9月28日選任・就任
◎委員長 ○副委員長
| ◎ | 向 井 嘉久藏 | ○ | 山 田 正 彦 |
| 森 礼 子 | 立 谷 誠 一 | ||
| 尾 﨑 太 郎 | 山 下 直 也 | ||
| 濱 口 太 史 | 鈴 木 太 雄 | ||
| 谷 洋 一 | 長 坂 隆 司 | ||
| 奥 村 規 子 | 多 田 純 一 | ||
| 岩 田 弘 彦 |

対面式演壇から質問
9月定例会から、新たに執行部と向かい合った位置に演壇(対面式演壇)を設置し、従来から行っている一括質問方式に加え試行的に導入した一問一答方式、分割質問方式を活用して10人の議員が一般質問を行いました。
議案等の議決結果
| 項 目 | 件数 | 件 名 | 結 果 |
| 予算案件(知事提出) | 4件 | 平成23年度和歌山県一般会計補正予算 等 | 可 決 |
| 条例案件( 〃 ) | 9件 | 和歌山県税条例の一部を改正する条例 等 | |
| 決算案件( 〃 ) | 2件 | 平成22年度和歌山県歳入歳出決算の認定について 等 | 継続審査 |
| 人事案件( 〃 ) | 1件 | 和歌山県教育委員会の委員の任命につき同意を求めるについて | 同 意 |
| その他案件( 〃 ) | 5件 | 平成23年度建設事業施行に伴う市町村負担金について 等 | 可 決 |
| 請 願 | 2件 | 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書についての請願 | 採 択 |
| 漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置に関する国への意見書の提出を求める請願 | |||
| 意見書・決議 | 23件 | 台風災害対策に関する意見書 | 可 決 |
| 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書 | |||
| 反捕鯨団体の活動に対して毅然たる取締りを求める意見書 | |||
| 農林漁業用軽油に係る軽油引取税の免除措置等に関する意見書 | |||
| 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書 | |||
| 受診時定額負担制度導入の撤回等を求める意見書 | |||
| 万全の領域警備を求める意見書 | |||
| 南極海における鯨類捕獲調査事業の継続を求める意見書 | |||
| 地元漁業者が主体となった法人の漁業権取得について制限を求める意見書 | |||
| 医療に係る事業税の特例措置の存続を求める意見書 | |||
| 一般用医薬品のインターネット等販売規制緩和に反対する意見書 | |||
| 調剤基本料の一元化に係る意見書 | |||
| 戦没者等の遺族に対する特別給付金等に係る意見書 | |||
| 消費税に係る措置を求める意見書 | |||
| 地下タンク漏えい防止規制対応推進事業に関する意見書 | |||
| 円高・産業空洞化等に係る緊急経済対策を求める意見書 | |||
| 雇用の再生・創出のための基金事業の延長等を求める意見書 | |||
| 小規模事業者経営改善資金融資制度の充実を求める意見書 | |||
| 介護保険制度に関する意見書 | |||
| 35人以下学級早期実現、義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書 | |||
| 「防災集団移転促進事業」適用条件緩和を求める意見書 | |||
| 災害復旧における農地傾斜角度等に関する意見書 | |||
| 本県の農地の災害復旧に関する決議 |
一般質問議員(10人)
9月20日(火)谷 洋一 雑賀 光夫 藤本眞利子 平木 哲朗 立谷 誠一
9月21日(水)角田 秀樹 高田 由一 谷口 和樹 中村 裕一 服部 一
6月定例会の主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、下記のとおりです。(要約抜粋)
| 台風12号の災害復旧対策 |
台風12号は過去に例を見ない甚大な被害をもたらしたが、災害復旧支援に対する国への早急な働きかけ、また、県独自の対策をどう考えているか。
9月13日に国に対し、激甚災害の早期指定や被災者の生活再建に向けた支援等、8項目の緊急要望を行った。また、危機状態の市町村に多くの人員を派遣し、被災者の確認やニーズ調査、ボランティアやごみ処理等の支援を行っている。今後、応急復旧に全力を挙げ、仮復旧、本復旧に取りかかり、本県の機能を一日も早く取り戻したい。
| ため池の防災対策 |
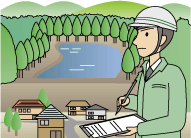
県内には約5500のため池があり、地震・台風が続く中、地域住民の生命・財産を守るために早急な対策が必要であるが、現状の取組と今後の対策はどうか。
県では、地域防災計画に位置づけられたため池など、420カ所で第1次耐震診断を行い、そのうち特に危険度の高い82カ所では第2次診断を実施し、62カ所が要対策となっている。市町村の要望を受け、要件の整ったため池から県営ため池等整備事業を実施するとともに、平成20年度から管理者に点検マニュアルを配布し、日常点検の充実強化を指導している。
| 災害発生時の市町村との連携 |
災害発生時の行動指針や初動マニュアル等は地元市町村で十分検討しておく必要があるが、市町村の体制づくりへの県の支援も大切である。現在の連携状況と今後の対応は。
今回の予想を上回る豪雨では避難指示等の発令判断が難しかったと考えるが、国でも発令判断基準の見直しに取り組むと聞いており、県でも専門家の意見を聞きながら検討していく。安否確認に係る市町村との連携については、平成21年度に、東南海・南海地震に備え、孤立化の予測される地域への市町村防災行政無線等の整備を支援したところである。
| 土砂ダムの現状と復旧 |
台風12号の土砂崩れにより出現した田辺市熊野(いや)の土砂ダム、熊野川に流れ込む奈良県の土砂ダムの現状と復旧の見通しは。
同様のダムは今までにも全国各地で発生しており、その都度、国土交通省が知見を蓄えており、制度もあるため、直轄で対処してくれるよう求めている。既に水を抜いて水路をつくる工事を直轄で始めていたが、別の台風が来て中断している。その工事が完成すると地域に戻れる可能性が高くなるので、早急な実施をお願いしている。
| 通学困難な高校生への支援 |
自宅が被災していなくても、道路事情で学校に行けず、入寮手続をしたりアパートを借りて対応している家庭もある。経済的な負担も大きいが、これまでどのような手だてをしてきたか。
災害直後から教員が家庭訪問して生徒の安否を確認し、生徒や保護者からの相談に乗るなど、きめ細かな支援を行っている。JR等の運休に対応してバスをチャーターし通学手段を確保するとともに、通学路の復旧に時間がかかりそうな生徒には寄宿舎等、県保有施設の活用を働きかけるなど、学校と連携をとりながら鋭意対応している。
| 脱原発に対する知事の考え方 |
福島原発事故を引き起こした危険性から、改めて原発撤退の必要性を痛感したが、知事は脱原発をどう考えるか。
全体として、我々が生きていく、雇用を守っていくためにエネルギーの総量を確保しなければならないこと、また、太陽光発電など再生可能エネルギーの導入を積極的に行って多種多様なエネルギー源のバランスミックスを図っていくこと、という2つの視点が重要である。
| 食物の放射能検査 |
福島原発事故により牛肉から基準値を超えるセシウムが検出されたが、安心して食べられるよう、牛肉に限らず食品の放射能検査をどのように行っているか。
9月から各保健所にサーベイメータを配備して検査を行い、一定値を超えた場合、環境衛生研究センターに設置した検出器で分析する体制を整えた。今後、基準値を超える食品を流通から排除するため、また、県産農水産物に放射性物質がないことを確認するため、モニタリング検査を実施する。
【サーベイメータ】
放射線の量を測定する携帯型の器械。
| 介護疲れ対策 |
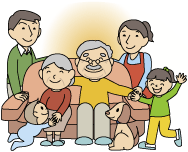
新聞で介護の母親を蹴って死なすという報道があった。その罪は重いが、社会全体の責任がないとも言い切れないだろう。介護疲れからくる事故・事件対策をどう考えるか。
県では、民生委員・児童委員等と連携し、あいさつや声かけなど、地域で困っている高齢者やその家族を早く見つけ、相談や支援につなげる環境づくりに取り組んでいる。今後も引き続き、地域住民による助け合い活動の支援や福祉関係機関とのネットワーク強化など、地域で支え合う体制づくりの充実強化を図っていく。
| 過疎対策 |
県内30市町村のうち14市町村は過疎地域の指定を受けていない。それら地域への対策についてどう考え、どう取り組むか。
昨年から、地域住民や市町村と地域固有の課題を洗い出して活性化につなげる過疎集落支援総合対策を実施している。過疎地域に準じるところも対象にしており、県内10市町村14生活圏で対策を講じているが、過疎地域指定を受けていない「みなべ町清川地区」も含まれている。今後、よりきめ細かな対策を講じていきたい。
| 紀の国森づくり税の効果と実績 |
平成19年4月に施行された紀の国森づくり税は、花粉症研究や森林環境の重要性の普及啓発などに大いに効果を上げた。来春の適用期限を控え、その効果や実績をどう考えているか。
4年間で県民提案の事業等228件を採択し、都市部での森林整備、荒廃森林の間伐・植樹等を実施した。納税とこれらの活動により税条例の基本理念が浸透し、森林の役割と保全・活用の重要性が県民に理解された。全国植樹祭を契機とした新条例の制定とともに、紀の国森づくり税条例を延長すべく、次期議会に向けて作業を進めている。
| 常任委員会活動リポート |
建設委員会

建設委員会では、8月24日・25日に近畿自動車道紀勢線(田辺~すさみ)、国道371号橋本バイパス、国道169号竹原拡幅及び奥瀞道路 期、県道井ノ口秋月線、県道井関御坊線の道路整備事業並びに河川整備事業1カ所、下水処理場事業1カ所、ダム整備事業1カ所、海岸整備及び津波対策事業1カ所について、進捗状況及び現状について調査を行いました。
近畿自動車道紀勢線(田辺~すさみ)
白浜町・平間トンネル工事現場
| (注)国 道: (都道府県管理) |
全国 91.6% 県 60.3% |
県 道: |
全国 67.9% 県 42.7% (H21.4.1現在) |
今回の調査では、高速道路と合わせて県内の一体的発展に寄与する府県間道路、川筋ネットワーク道路等の幹線道路整備と津波や洪水等の災害対策としての河川整備や港湾整備の地域住民に及ぼす効果を確認するとともに、早期完成に向けた取組の必要性について意見交換を行いました。
和歌山県の国道・県道の改良率(注)は、全国ワースト3位と大きく立ち後れていることから、県民の命とくらしを守る重要な道路である各幹線道路の一日も早い完成を強く要望しました。

巡視船「きい」

経済警察委員会は、8月30日に和歌山税関支署、和歌山海上保安部、関西電力(株)御坊発電所、翌31日に太地町、警察航空隊、10月5日に和歌山アイコム(株)において、所管事務の調査を行いました。
税関では水際での犯罪防止と県貿易の現況等を、関電では発電所の概要と電力需給等を、航空隊ではヘリコプターに新装備されたカメラの効果等を、和歌山アイコムでは紀の川工場の概要を、それぞれ調査し、今後の対応強化を要望しました。
和歌山海上保安部では、業務概要とともに海上テロを想定した厳しい訓練が重ねられていることを確認し、関係機関との連携を強化してより一層適切な取締りを行うよう要望しました。
反捕鯨団体の活動が問題となっている太地町では、町当局や漁業関係者から経緯と現況を聴取し、県警察や串本海上保安署からの出席も得て、取締りの現状や今後の対応、畠尻湾に新設予定の臨時交番の位置などを確認しました。
住民の「普通の生活をしたいだけ」との切なる願いを委員全員がしっかり受けとめ、委員会としての対応を約束し、9月定例会では、委員会から意見書案を提案して、全会一致で可決されました。
今後もタイムリーかつ有意義な所管事務調査を行い、委員会活動の充実に努めてまいります。