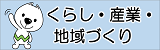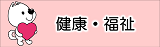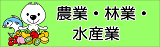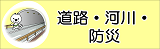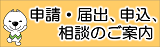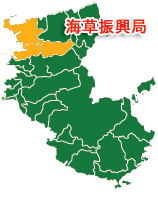快想(用語解説)
用語解説
世界人権宣言
昭和23年(1948年)12月、国連総会において採択された国際的な人権宣言を指します。市民的・政治的自由のほか経済的・社会的な権利について、各国が達成すべき基準を定めています。
世界人権宣言のページへ
人権について
世界人権デー
世界人権宣言が採択された12月10日を指します。
なお、わが国では世界人権デーである12月10日までの1週間を「人権週間」と定め、人権思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に展開しています。
「人権」ってなんだろう?のページへ
女性の人権について
女子差別撤廃条約
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
すべての人間は、そもそも生まれながらにして自由かつ平等であることから、男子も女子も等しく尊重されるべきであるとした条約です。わが国は昭和60年(1985年)に批准しました。
和歌山県男女共同参画推進条例
男女の人権が尊重され、性別を問わず男女が個人のもつ能力を十分に発揮できる社会を目指して制定された条例で、男女共同参画を進めるうえでの理念や、県・県民・事業者の責任と義務、県の基本的な施策などを定めています。
主な内容
- 男女の人権の尊重など、6つの基本理念
- 県、県民、事業者の責務(責任と義務)
- 県の基本的施策
- 男女の人権を損なうような行為の禁止
- 相談及び県の施策についての苦情への適切な対応
- 男女共同参画審議会
ドメスティック・バイオレンス(DV)
夫婦や恋人など親密な間柄にある男女間において、主として男性から女性に加えられる身体的、精神的・性的・経済的な暴力をいいます。殴る、蹴るといった物理的な暴力だけでなく、脅し、ののしり、無視、行動の制限・強制、苦痛を与えられることなども含まれた概念をいいます。
デートDV
DVが、夫婦や同居している恋人等親密な間柄にある男女間の暴力をいうのに対し、結婚していない男女間における身体的、精神的・性的・経済的な暴力をいいます。
ストーカー行為
同一の者に対して、恋愛感情等その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨念の感情を充足する目的でつきまとう等、身体の安全、住居等の平穏や名誉を害し、不安を覚えさせるような行為を反復することをいいます。
セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)
相手の意に反した、性的な言動を行い、それに対する対応によって、不利益を与えたり、またはそれを繰り返すことによって相手の生活環境を著しく悪化させることをいいます。
女性の人権について考えてみようのページへ
子どもの人権について
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
平成元年(1989年)11月に国連総会で採択されました。子どもの人権や自由を尊重し、子どもに対する保護と援助を進めることを目指した条約です。わが国は、平成6年(1994年)に批准しました。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える児童虐待について、虐待の禁止、予防や早期発見及び児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の措置などを定めています。
虐待による子どもの心身への影響は大きく、虐待が発見された場合、まず子どもを心身の危険から守ることが最優先されます。以下のような場合は、特に早急な対応が必要となります。
- 生命に危険があるとき
- 身体的な後遺症を残すおそれのあるとき
- 身体的虐待が繰り返されるとき
- 子どもの家出が繰り返されるとき
- 性的虐待の疑いがあるとき
子どもへの虐待を発見したり、疑わしいと思われるときは、児童相談所や福祉事務所等に通告または相談をしてください。(匿名でもかまいません。また、相談や通告をした人が特定されないような配慮がなされます。)
なお、子どもの虐待には次のようなことがらがあげられます。
- 身体的虐待
身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような暴行を加える。 - ネグレクト(不適切な養育、保護の怠慢)
食事を十分与えない、入浴させない、汚れた衣服を着続けさせる、病気にかかっても医者に診せない等の不適切な養育。
登校や外出を禁止する、乳幼児を自動車の中に放置する、捨て子、置き去り等。
児童の目の前でのドメスティックバイオレンス。 - 心理的虐待
ことばによる脅しや拒否的態度などで、子どもの心を傷つける。 - 性的虐待
子どもと性交をしたり、身体に触る、子どもに性器を見せるなど。
子どもを虐待から守る条例
子どもの人権が尊重され、子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指し、県民一人ひとりが協力し合い、様々な関係機関の連携の下、社会全体で児童虐待の問題に取り組む体制を整備するとともに児童虐待を許さないまちづくりを推進するため制定された条例で、下記のようなことを定めています。
主な内容
- 子どもの人権の尊重など、3つの基本理念
- 県、県民、保護者、市町村等の責務
- 県の基本的施策 (啓発活動、早期発見・早期対応、指導・援助など)
- 子どもを虐待から守る審議会
子どもの人権について考えてみようのページへ
高齢者の人権について
高齢者虐待防止法(高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)
高齢者の尊厳を守るため、高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であることから、虐待を禁止するとともに、高齢者を養護する人(養護者)に対する支援措置などを定めています。
高齢者虐待とは、65歳以上の高齢者に対する次のような者による虐待行為に分けられます。
- 養護者による虐待
高齢者の世話をしている家族や親族、同居する人による虐待 - 養介護施設従事者による虐待
介護サービス事業や介護施設の職員による虐待
なお、虐待行為は例えば次のようなことがあげられます。
- 身体的虐待
殴る、蹴る、つねる、意図的に過剰な投薬をする、ベッドに縛り付けたり、無理やり食べ物や飲み物を口に入れるなど。 - 介護・世話の放棄・放任
劣悪な住環境で生活をさせる、食事や入浴、排せつなどの世話をしない、必要な介護・医療サービスを受けさせないなど。 - 心理的虐待
侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する、侮辱を込めて子どものように扱うなど。 - 性的虐待
わいせつな行為をする、させる、排せつの失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置するなど。 - 経済的虐待
日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の年金や預貯金を勝手に使うなど。
早期発見・早期対応が重要です。高齢者の安全を確保するとともに、養護者等に対する支援を行うためにも、虐待に気づいた時は、速やかに市町村に通報等をしてください。
和歌山県高齢者総合相談センター(シルバー110番)
高齢者やその家族等が抱える保健・福祉・医療等に関する様々な心配ごと、悩みごとについて、各種相談員が相談に応じます。また、地域に出向いて相談を行うこともあります。
- 和歌山県高齢者総合相談センター(シルバー110番)(外部リンク)
成年後見制度
認知症、知的・精神障害等により判断能力が不十分なため、家庭裁判所で選任された成年後見人等が、本人に代わって法律行為の代理等を行う制度です。
地域包括支援センター
高齢者やその家族に対する総合相談支援業務、権利擁護事業、包括的継続的なケアマネジメント支援業務及び介護予防ケアマネジメント業務を行うことを目的とした施設です。
高齢者の人権について考えてみようのページへ
障害者の人権について
障害者権利条約
障害のある人の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約で平成18年(2006年)12月に国連で採択されました。障害のある人の自立、非差別、社会への参加等を一般原則として規定するほか、教育、労働等、さまざまな分野で障害のある人の権利を保護・促進する規定を設けています。
障害者基本法
日本における障害のある人の自立や社会参加の支援などの施策に関する基本的な事項を定めた法律です。
平成16年に法律の目的や障害者の定義などが改正され、基本的理念として「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが明記されました。
障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律)
障害者の権利や尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を養護する人(養護者)に対して支援措置などを定めています。
虐待は、次のような種類に分けられます。
- 養護者による虐待
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待 - 障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待 - 使用者による虐待
障害者を雇っている事業主などによる虐待
なお、障害者への虐待は例えば次のようなことがらがあげられます。
- 身体的虐待
暴力や体罰で傷や痛みを与えたり、必要以上に過剰な投薬をしたり、不当に身体拘束をしたり、無理やり食べ物や飲み物を口に入れるなど。 - 心理的虐待
侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、意図的に無視するなど。 - 性的虐待
わいせつな行為をする、させる、わいせつな言葉を言うなど。 - 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、排せつなどの世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなど。 - 経済的虐待
本人の同意なしに年金や賃金などを使うこと、日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせないなど。
障害者への虐待に気づいた場合は、速やかに市町村(障害者虐待防止センター)へ通報してください。(匿名でもかまいません。また、通告をした人が特定されないような配慮がなされます。)
ノーマライゼーション
障害のある人もない人も、すべての人間が普通に生活を送るため、共に生活し、活動できる社会が本来あるべき姿であるという考え方です。
バリアフリー
障害のある人が社会生活をしていくうえで、物理的・心理的障壁(バリア)となるものを除去するという意味です。
もとは、建築用語として、建物内の段差解消等物理的障壁の除去という意味合いが強かったのですが、より広く障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも使用されています。
リハビリテーション
障害のある人の身体的、精神的、社会的な自立能力向上を目指す総合的なプログラムにとどまらず、ライフステージのすべての段階において全人間的復権に寄与し、障害のある人の自立と参加を目指すという考え方です。
合理的配慮
障害のある人とない人が同じように生活するために必要な、いろいろな配慮や工夫のことです。例えば、車いすが利用できるように建物の入り口のスロープやトイレを整備したり、目の不自由な人や耳の不自由な人が地域の集会や会社の会議に参加できるように点字の資料や手話の通訳を用意したりすることなどを指します。
「障害者権利条約」では、第2条で「障害のある人が他の人と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ均衡を失した又は過度な負担を課さないもの」と定義しており、合理的な配慮を行わないことは障害を理由とする差別であるとしています。
成年後見制度
認知症、知的・精神障害等により判断能力が不十分なため、家庭裁判所で選任された成年後見人等が、本人に代わって法律行為の代理等を行う制度です。
障害がある人の人権について考えてみようのページへ
同和問題について
えせ同和行為
同和問題は怖い問題であり避けた方がよいとの誤った意識に乗じて、あたかも同和問題の解決に努力しているかのように装い、同和の名のもとに、さまざまな不当な利益や義務のないことを要求する行為をいいます。
えせ同和行為は、これまで同和問題の解決に真摯に取り組んできた人々や関係者に対するイメージを損ねるばかりでなく、これまで培われてきた教育や啓発の効果を覆し、同和問題に対する誤った意識を植え付けるという悪影響を生じさせるなど、問題解決の大きな阻害要因となっています。毅然とした態度で、かつ組織全体で対処することが望まれます。
同和問題について考えてみようのページへ
インターネットを使った人権侵害について
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
この法律により、ホームページや掲示板において、名誉棄損・誹謗・中傷の書き込み・プリバシーの侵害等の人権侵害にあった時、プロバイダや管理者に対して、その書き込み等の記事を削除したり、書き込みをした者(発信者)の情報を開示するよう求めることができるようになりました。
削除依頼等については、プロバイダ等にメールや文書で連絡をします。掲示板上の議論に巻き込まれることがあるため、掲示板に削除依頼を書き込むことは避けましょう。
被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、地方法務局にご相談ください。
プロバイダ
インターネットに接続するためのサービスを提供する事業者です。電話回線や専用線などを通じて、顧客である企業や家庭のコンピューターをインターネットに接続します。
ネットパトロール
学校裏サイトやブログ、プロフなどから携帯電話等による探索を通じて、有害情報や誹謗中傷を含むサイトを抽出し、内容に応じて専門機関に連絡した上、プロバイダやサイト運営業者に対し削除要請等の対応を行う活動です。和歌山県では平成21年(2009年)6月からこのネットパトロールを推進する事業を開始しています。
ネットモラル
情報モラルの中でも、特にインターネットを使用する上でのモラルのことで、インターネットは誰もが利用でき情報交換の機能を有するため、日常生活におけるモラルと同様にルールやマナーを守ること、他人への配慮を心がけ、個人情報を流出させたり、プライバシーを侵害したりする行為をしないことが望まれます。ネットモラルとは、そういったインターネットを利用する際に求められるルールや最低限のマナーをいいます。
フィルタリング
インターネット上のウェブサイト等を一定基準に基づき選別し、有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービスです。
インターネットを使った人権侵害について考えてみようのページへ
職場における人権について
パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場の権限や地位などを悪用し、業務の範囲を逸脱して、継続的に相手の人格と尊厳を侵害する言動を行い、働く環境を悪化させたり雇用不安を与えること。つまり、「職場における立場や地位を悪用したイジメ」と言えます。
セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)
相手の意に反した、性的な言動を行い、それに対する対応によって、不利益を与えたり、またはそれを繰り返すことによって相手の生活環境を著しく悪化させることをいいます。
職場における人権について考えてみようのページへ