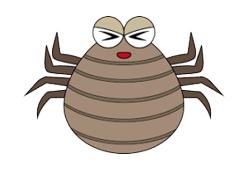準備するもの
澄み切った空気、木漏れ日が差し込む森、雄大な山々の造形美……。息を弾ませ、一歩一歩着実に高みへと足を運び、日常とは異なる充実したひとときを楽しむことができるのが、県立自然公園です。
たくさんの楽しみがある一方で、そこは街とは違う自然の中です。ゴツゴツした岩場やぬかるんだ道が現れ、強い日差しや雨風にさらされることもあり、初心者・熟練者に関係なく、服装や持ち物、対策などはとても大事なことです。
海岸沿いの県立自然公園であっても、服装等についてはしっかりとした注意が必要です。
登山に関する本やインターネット等で確認し、事前にしっかりと準備し、万全の対策を行った上で、大自然を楽しみましょう。
準備するもの
対策
準備するもの
服装
季節に合った服装を心掛けながら、以下のことに注意し、当日の服装を選びましょう。
暖かい時期でも防寒対策をしましょう
- 標高1,000mの山頂は、ふもとと比べて約6.5℃も低い気温になります。スタート地点は20℃で少し暑く感じても、上った頃には10℃前半になり、山頂はふもとよりも雨も風も強くなります。また、汗をかいた後になることもあり、体の震えが止まらなくなるほど寒さを感じることもあります。朝夕は冷えることも多いため、1枚多めの防寒対策を心掛けましょう。
植物の枝や葉でけがをしないよう、なるべく肌の露出は減らしましょう
- 登山中、枝の先や鋭利な葉先で肌を切ってしまうことがあります。特に、登山道があまり整備されていない山に登るときは、夏であっても長袖で行くことをおすすめします。
伸縮性の高い、動きやすい素材を選びましょう
- 当然なことですが、登山はとにかく動くことが多いです。ウォーキング的な動きはもちろんのこと、山腹の斜面を歩いたり、岩稜をよじ登ったりすることもあります。
必ずしも登山用のウェアで揃える必要はありませんが、基本的には専門店で、もしくはスポーツ用品店などで動きやすい服装を揃えましょう。
「靴」の重要性を覚えておきましょう
- 案外見落としがちですが、上下の服装などより、「靴」が一番重要となります。基本的には登山靴を用意しましょう。歩くときにサイズ等が合っていないと、足の痛みにより途中で断念したり、登山自体を楽しめないような事態になりかねません。
また、買うときは店頭に行き、実際に履いてみるなど、慎重に自分に合った登山靴を選びましょう。
季節ごとの服装チェックポイント
【春・秋】
上は、フリースなど、防寒性が高く、動きやすいものを選びましょう。また、山の天気は変わりやすいので、防水加工されたものを選びましょう。
日差しが強いこともあるので、被り物は用意するようにしましょう。
【夏】
夏の登山は、春夏に比べて暖かいとはいえ、標高により気温が下がることも考えられるので、脱ぎ着できる薄めの上着などを用意しましょう。半袖半ズボンでも構わないですが、けが防止や虫対策、標高差などを考慮し、服装選びは慎重に選びましょう。
また、日差しが強いので、被り物は必ず用意しましょう。
【冬】
冬は防寒対策を第一に考えましょう。一番大事なことは、脱ぎ着しやすいものをいくつか用意し、重ね着することで、調節ができることです。冬といっても登山をしていれば、体温が高くなりこともあるので、こまめな服装の調節ができるようにしなければなりません。
また、首回りや足先など特に冷えやすい箇所の防寒もしっかりとするようにしましょう。
とはいえ、冬の山の厳しさは、いくら対策をしても侮ることはできません。春や秋などの時期に行くようにしましょう。
持ち物
服装だけでなく、持っていくものも防寒や体調管理のためなどにとても重要です。すべて持っていく必要はありませんが、自分に必要なものは何かをしっかり考え、用意し、持っていくようにしましょう。
【季節共通】
| □ | 登山靴 | 自分に合ったものを用意しましょう。 |
|---|---|---|
| □ | ザック | 重要。日帰りの登山であれば、普段使いのものでも可能です。 |
| □ | アウター | 夏でも必要になります。 |
| □ | レインウェア | 山の天気は変わりやすいので必須です。 上下分かれの蒸れにくい素材、収納しやすいものがおすすめです。 |
| □ | ザックカバー | レインウェアと同様、用意しておきましょう。 |
| □ | 水分 | 特に夏は多めに、最低でも1リットル以上用意しましょう |
| □ | タオル | 汗拭き以外に救急用・日焼け防止としても重要です。 |
| □ | ティッシュ・トイレットペーパー | 芯を抜いたトイレットペーパーがおすすめです。 |
| □ | 薬類 | 絆創膏、消毒液、常備薬など |
| □ | 行動食 | 登山中のエネルギー補給にお菓子などを用意しましょう。 また、緊急用の非常食として、日持ちのする高カロリーのものも用意しておきましょう。 |
| □ | 日焼け止め | 日焼け止めはもちろん、UV入りのリップクリームも用意しよう。 |
| □ | 虫よけスプレー | 夏は特に虫が多いので、必須になります。 |
| □ | 登山用地図 | 最低何らかの地図は必要で、広範囲で細かく書かれたものがおすすめです。 |
| □ | ヘッドライト | 懐中電灯でもよいが、両手が使えるようヘッドライトがベストです。 交換用の電池も忘れないようにしましょう。 日帰りでも行程が長くなるときは、予定より遅れることや昼でも暗いところがあるので、用意しましょう。 |
| □ | 着替え | 汗をかいたら着替えることができるように用意しましょう。夜につれて冷えてきます。 |
| □ | 時計 | 防水機能があればベストです。 |
| □ | ライターまたはマッチ | 緊急用に用意しましょう。 |
| □ | ビニール袋 | ごみ入れや着替え入れに、あれば便利です。 |
| □ | モバイル充電器 | バッテリーの消耗が激しいGPSアプリを使用する場合に必須です。 |
| □ | 健康保険証のコピー | 万が一のためにコピーを用意しましょう。 |
【冬】
| □ | 防寒アイテム | 各部を防寒できるもの。首回りや足先など。 |
|---|---|---|
| □ | アウター | 脱ぎ着しやすいものを用意しましょう。 |
| □ | 使い捨てカイロ | 貼るタイプ、貼らないタイプ両方あれば良いでしょう。 |
| □ | サングラスまたはゴーグル | 雪面の反射日光や万が一の吹雪から目を守るために必要です。 |
対策
熱中症
脱水症に要注意!~ 夏は熱中症にも注意してください ~
山で脱水症が起こりやすいのはなぜ?
- 汗をたくさんかきやすい
- 運動により呼吸数が増え、呼気から失われる水分(不感蒸泄)が増える
- 途中にトイレに行かずに済むように水分摂取を控えてしまう
- 登山時の荷物を軽くするために、携行する水分を制限してしまう
- 集団での登山の際、全体のペース乱さないように、こまめな水分補給を怠ってしまう

山では、平地以上に予防を重視しよう!
山という環境では、脱水・熱中症になって救助要請しても、救助まで時間が掛かり、その間に症状が悪化する場合があります。
予防を十分に意識してください。
- 予防の基本「こまめに」を大切に、のどが渇く前に少しずつ飲みましょう
- 登山前に500mlほどの水分を飲んでおく
- 最低2リットルの水分を携行する
- 25分歩いたら5分休憩し、その際に水分補給をする
- 適度な塩分補給を行うこと (注)塩分過多には注意すること
- 25分歩いたら5分休憩し、その際に水分補給をする
- コース上の水場を事前に把握しておく
- 食事から必要な糖質をとる - 糖質を摂ることで、カラダの主要なエネルギー源である体脂肪を使いやすい体内環境となります。
- 余計な汗をかかないような服装を選ぶ
- 自分では気づきにくいので、集団であればお互いに気に掛ける
もし、脱水・熱中症が疑われるときの対応を知っておこう
(意識がある場合)
- 水分・塩分・糖質が入った飲み物を1リットル以上飲む
- 日差しを避け、涼しい場所へ移動する
- ザックなど少し高さのあるものに足を乗せ、横になって安静にする
- 手足に水をかけて扇ぐ
- 経過を観察する
(意識がない場合)
- 警察に救助を要請する
- 日差しを避け、涼しい場所へ移動する
- ザックなど少し高さのあるものに足を乗せ、横になって安静にする
マダニ対策
マダニに注意! ~ マダニQ&A ~
マダニは小さいですが、侮ってはいけません!
マダニを媒介とした(マダニがウイルスを持っているかどうかが重要)人獣共通感染症による疫病感染し、様々な病気を発症します。
その中には重篤な症状を引き起こし、時に人を死に至らしめたり、生涯残る後遺症で苦しめたりするケースもあります。さらに、有効な治療法・ワクチンがありません。
大切なことは、しっかりと予防をすること、早期発見・早期除去を行うことです。
「マダニ」に関する知識を身に付け、身を守り、登山を良い思い出にしましょう!
- マダニってどんなの?
- マダニとは、食品などに発生するコナダニや衣類や寝具に発生するヒョウダニなど、家庭内に生息するダニとは種類が異なります。体長は通常3~8mmで、肉眼で確認できます。さらにマダニは吸血し、飽血(満腹状態)になると、10~20mm程度の大きさになります。また、春から秋にかけて活動が活発になりますが、温暖な地域では冬でも活動しています。
- マダニはどこにいるの?
- 日本全国にに分布しています。特に野生動物が生息する自然環境が豊かな場所に生息し、市街地周辺でも自然が豊かであれば、畑やあぜ道などにも生息しています。また、一般的にマダニは、吸血するために地上1m位の植物の葉陰で野生動物や人を待ち伏せして、その体の比較的やわらかい部位に付着します。 ※野生動物の通り道は要注意です。
- マダニに咬まれたら痛い?気づく?
- マダニは咬みついた後、セメント物質を分泌して固着し、麻酔様物質の含まれた唾液を分泌し吸血します。麻酔様物質が含まれているため、咬まれた直後は気づかないことが多いです。2~3日するとかゆみ、灼熱感、軽度の痛みを感じる方もいれば、1週間しても気づかない方もいます。7~10日ほどでマダニは飽血(満腹状態)になり、自ら離れます。
- マダニに咬まれたらどうなる?
- もし、自分の体を咬んだマダニがウイルスを持っていた場合、ウイルス感染することになります。マダニが持つウイルスの種類により症状はいくつかありますが、代表的な感染症として、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱、ライム病、ダニ媒介性脳炎などがあります。その中でも、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は、6日~2週間後に、発熱、倦怠感、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)などが現れ、重症の場合 は死に至ることもあります。有効な治療法やワクチンはまだ確立していません。
- マダニに咬まれたら100%感染する?
- すべてのマダニがウイルスを持つわけではないので、必ず感染するということではありません。しかし、どのくらいのマダニがウイルスを持っているのか確認することは困難であり、また、感染しても症状が出ない人もいるので、実際の感染率は不明です。ですので、予防をすることがとても大切です。
- 今まさにマダニに咬まれている。どうすれば良いか?
- 無理に引き抜こうとしてはいけません。医療機関(皮膚科)で処置(マダニの除去、洗浄など)をしてもらってください。マダニはセメントのような物質によりしっかり固着しているので、無理に引き抜こうとすると、マダニの一部が皮膚内に残って化膿したり、マダニの体液を逆流させてしまったりする恐れがあります。
- マダニに咬まれたかもしれない。どうすれば良いか?
- 症状がない場合は、医療機関への受診は不要です。しかし、マダニに咬まれた可能性がある日から、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状が認められた場合は、医療機関を受診し、経緯なども含めて医師に相談してください。
- マダニに咬まれないようにするためには?
- マダニに咬まれないように肌の露出を避けましょう。また、マダニが服の中に入らないように以下の服装を心がけましょう。
- マダニに咬まれないようにするためには?
- マダニに咬まれないように肌の露出を避けましょう。また、マダニが服の中に入らないように以下の服装を心がけましょう。
- 長袖・長ズボンを着用し、帽子や手袋なども利用する。
- 半袖・半ズボンやサンダル履きなどは絶対にやめましょう。
- シャツの袖口を手袋の中に、シャツの裾はズボンの中に入れる
- ズボンの裾は靴下や靴に入れる
- 車に乗る前や家に入る前には、衣類にマダニがついていないかよく確認しながら、念のため払い落としましょう。
- 家に帰ったらすぐに服を洗濯し、服を長時間放置しないようにしましょう。
※すぐに服を洗濯できない場合は、袋に入れてしっかりと結んでおきましょう。 - 帰宅後、すぐにシャワーを浴び、体にマダニがついていないか確認しましょう。
- 虫よけスプレーは有効なのか?
- マダニ効果があると記載されている製品もあります。使用上の注意などをよく読み、用法用量を守り、正しく使用してください。
外部リンク集
- マダニ:国立感染症研究所