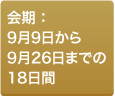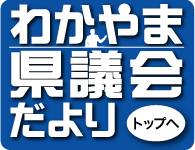知事説明要旨

産業の振興のためには、県内の事業者に地域資源を活用した事業展開を積極的に行っていただくことが最も重要であり、助成等による中小企業の育成や、優れた県産品等を県外に向けて積極的にプロモーションしていきます。
また、県民の安全・安心を守るため、引き続き環境生活、福祉政策には全力を挙げて取り組んでいくとともに、今後本県で開催予定の平成23年の第62回全国植樹祭や平成27年の第70回国民体育大会に向けて準備を進めていきます。
一方、県では、財政破綻を回避するため、施設や団体、補助金等の事業見直しを検討しており、その見直しは痛みを伴うものでありますが、県民の皆様のご理解をお願いします。
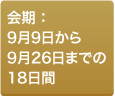
| 9月 |
9日(火)本会議
10日(水)議案調査
11日(木)議案調査
12日(金)議案調査 |
16日(火)本会議(一般質問)
17日(水)本会議(一般質問)
18日(木)本会議(一般質問)
19日(金)本会議(一般質問) |
22日(月)常任委員会
24日(水)常任委員会
25日(木)本会議
26日(金)本会議 |
会期中の主な動き
- 下記の特別委員会を開催しました。
●半島振興・交通・産業振興対策特別委員会(9/18)
●議員定数等検討特別委員会(9/19)
●行政改革・基本計画等に関する特別委員会(9/25)
- 決算特別委員会が設置され、14人の委員が選任されました。閉会後直ちに委員会を開催し、委員長に吉井和?議員、副委員長に泉正徳議員を選出しました。委員会の構成メンバーは次のとおりで、次回12月定例会までに決算の審査を終えることになっています。
決算特別委員会(定数14人)
平成20年9月26日選任
◎吉井 和視
山本 茂
町田 亘
谷 洋一
宇治田栄蔵 |
○泉 正徳
坂本 登
中村 裕一
片桐 章浩
服部 一 |
松本 貞次
奥村 規子
中 拓哉
岸本 健 |
◎委員長 ○副委員長
議案等の議決結果
項目 |
件数 |
概要 |
結果 |
| 知事提出の予算案件 |
2件 |
平成20年度和歌山県一般会計補正予算 等 |
可決 |
| 知事提出の条例案件 |
4件 |
和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 等 |
可決 |
| 知事提出のその他案件 |
10件 |
紀の川中流流域下水道の維持管理に要する費用の負担について 等 |
可決 |
| 2件 |
平成19年度和歌山県歳入歳出決算の認定について 等 |
継続審査 |
| 知事提出の人事案件 |
2件 |
和歌山県教育委員会の委員の任命につき同意を求めるについて 等 |
同意 |
| 議員提出の議案 |
2件 |
議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例 等 |
可決 |
| 請願 |
2件 |
トンネルじん肺根絶の抜本的な対策に関する請願書 等 |
採択 |
| 1件 |
後期高齢者医療制度の保険料の軽減を求める請願 |
不採択 |
| 1件 |
教育改革についての請願 |
継続審査 |
| 1件 |
かつらぎ町道折登堀越線の県道昇格について |
取り下げ |
| 意見書 |
8件 |
関西国際空港に係る平成21年度概算要求に対する意見書 等 |
可決 |
一般質問議員(15名)
9月16日(火)小川 武 藤本眞利子 奥村 規子 新島 雄
9月17日(水)泉 正徳 片桐 章浩 松坂 英樹 川口 文章
9月18日(木)中村 裕一 多田 純一 長坂 隆司 須川 倍行
9月19日(金)山下 大輔 藤井健太郎 向井嘉久藏
主な質問とこれに対する答弁は次のとおりです(要約抜粋)
関西国際空港の整備

 国の21年度予算の概算要求に2期事業の建設事業費が盛り込まれなかったので、県議会として予算化を求める意見書を議決し、関係省庁などに直接届けて強く要望してきた。知事も素早く行動したと聞くが、この件についての所見はどうか。
国の21年度予算の概算要求に2期事業の建設事業費が盛り込まれなかったので、県議会として予算化を求める意見書を議決し、関係省庁などに直接届けて強く要望してきた。知事も素早く行動したと聞くが、この件についての所見はどうか。
 8月28日に国土交通省航空局長を訪ね、関空2期事業の継続を強く要望してきた。大阪府、関空会社とも連携し、奮闘している。県議会の意見書議決・要望活動に意を強くしたところであり、今後とも、減便の回復や一日も早い2期工事の完成などに一層積極的に取り組みたい。
8月28日に国土交通省航空局長を訪ね、関空2期事業の継続を強く要望してきた。大阪府、関空会社とも連携し、奮闘している。県議会の意見書議決・要望活動に意を強くしたところであり、今後とも、減便の回復や一日も早い2期工事の完成などに一層積極的に取り組みたい。
紀中・紀南地域への企業誘致
 企業立地促進法に基づく南紀広域企業集積構想が国で同意された。有田以南の地域資源を活用した企業等を誘致するもので、地域発展の起爆剤になるものと期待している。紀中・紀南地域基本計画実現のための手法と意気込みはどうか。
企業立地促進法に基づく南紀広域企業集積構想が国で同意された。有田以南の地域資源を活用した企業等を誘致するもので、地域発展の起爆剤になるものと期待している。紀中・紀南地域基本計画実現のための手法と意気込みはどうか。
 企業誘致はデスクワークやかけ声だけで実績が上がるものではなく、企業の声を直接聞いて汗をかくことが大事で、この計画を旗印として活用していきたい。誘致活動の実効性を高めるため、中小零細企業が多い地域特性を考えて立地奨励制度の適用要件を緩和するなど、立地意欲が高まるような支援策の拡充を現在検討中である。
企業誘致はデスクワークやかけ声だけで実績が上がるものではなく、企業の声を直接聞いて汗をかくことが大事で、この計画を旗印として活用していきたい。誘致活動の実効性を高めるため、中小零細企業が多い地域特性を考えて立地奨励制度の適用要件を緩和するなど、立地意欲が高まるような支援策の拡充を現在検討中である。
旅行関連事業者のネットワーク構築
 近年、旅行形態の多様化は顕著になってきている。地域で企画した「和歌山産の着地型旅行」を取り扱う県内旅行関連事業者のネットワークを構築し、特色ある幾つかの地域を結んで滞在型観光に発展させていく必要があるが、現在の取組はどうか。
近年、旅行形態の多様化は顕著になってきている。地域で企画した「和歌山産の着地型旅行」を取り扱う県内旅行関連事業者のネットワークを構築し、特色ある幾つかの地域を結んで滞在型観光に発展させていく必要があるが、現在の取組はどうか。
 県では、これまでに、県内旅行業者に対する着地型観光推進に向けた支援を鋭意行っている。今後とも、本県が全国に誇る「ほんまもん体験」を取り入れた着地型観光の推進に向け、県内旅行関連事業者と一緒になって積極的に取り組んでいきたい。
県では、これまでに、県内旅行業者に対する着地型観光推進に向けた支援を鋭意行っている。今後とも、本県が全国に誇る「ほんまもん体験」を取り入れた着地型観光の推進に向け、県内旅行関連事業者と一緒になって積極的に取り組んでいきたい。
↑ページの先頭に戻る
学校における模擬選挙の取組
 イギリスなどでは、青少年への政治教育の取組が行われており、日本でも重要性が指摘されている。和歌山の学校においても模擬選挙に取り組んでもらいたいが、その意義と取り組むことの有効性はどうか。
イギリスなどでは、青少年への政治教育の取組が行われており、日本でも重要性が指摘されている。和歌山の学校においても模擬選挙に取り組んでもらいたいが、その意義と取り組むことの有効性はどうか。
 模擬選挙は、県内において既に実践している小中高校もあり、成果を上げているとの報告もあるので、今後も研究していきたい。また、県選挙管理委員会としても、市町村選挙管理委員会とも連携して積極的に協力するとともに、選挙への関心を高める取組をお願いしていきたい。
模擬選挙は、県内において既に実践している小中高校もあり、成果を上げているとの報告もあるので、今後も研究していきたい。また、県選挙管理委員会としても、市町村選挙管理委員会とも連携して積極的に協力するとともに、選挙への関心を高める取組をお願いしていきたい。
用語解説
模擬選挙
投票権を持たない人たちに投票を体験してもらう取組。子どもや若者が選挙を体験しながら政治について学ぶよい機会となる。
児童施設の防災対策

 阪神・淡路大震災において生命を失った原因の大部分は、室内対策が講じられていなかったことによる。大地震になると重量物・危険物ほど吹っ飛ぶが、児童施設の室内対策の現状、また今後の計画はどうか。
阪神・淡路大震災において生命を失った原因の大部分は、室内対策が講じられていなかったことによる。大地震になると重量物・危険物ほど吹っ飛ぶが、児童施設の室内対策の現状、また今後の計画はどうか。
 幼稚園は110施設のうち74施設で、保育園は227施設のうち142施設で室内対策を実施している。県では、ピアノの固定などの室内対策が重要であると認識し、市町村に対し補助を行っている。また、民間保育園には、補助施策として総合防災対策強化事業もある。今後とも幼稚園や保育園の室内対策をさらに進めるよう市町村に働きかけていく。
幼稚園は110施設のうち74施設で、保育園は227施設のうち142施設で室内対策を実施している。県では、ピアノの固定などの室内対策が重要であると認識し、市町村に対し補助を行っている。また、民間保育園には、補助施策として総合防災対策強化事業もある。今後とも幼稚園や保育園の室内対策をさらに進めるよう市町村に働きかけていく。
教員免許更新制度への考え
 教員に免許更新制を導入するのは、一般職公務員との不均衡、医師や弁護士など非更新制免許制度との不整合など、多くの問題がある。教員免許更新制についての基本的な考えはどうか。
教員に免許更新制を導入するのは、一般職公務員との不均衡、医師や弁護士など非更新制免許制度との不整合など、多くの問題がある。教員免許更新制についての基本的な考えはどうか。
 教員として、その時々で求められる資質能力を一定水準に保てるよう、定期的に最新の知識技能を身につけ、自信を持って教壇に立ち、社会の信頼を得ることを目指せるようにとの趣旨で法改正された。現在、21年4月実施に向けて努力をしている。
教員として、その時々で求められる資質能力を一定水準に保てるよう、定期的に最新の知識技能を身につけ、自信を持って教壇に立ち、社会の信頼を得ることを目指せるようにとの趣旨で法改正された。現在、21年4月実施に向けて努力をしている。
↑ページの先頭に戻る
小中学校耐震化への財政的支援
 小中学校の耐震化を進めるため、単年度負担を減らす制度等の財政的援助や支援が必要である。県民の安心・安全の確保という観点から、国、県、市町村、教育委員会など関係機関が連携して有効な手だてが講じられるよう働きかけるべきではないか。
小中学校の耐震化を進めるため、単年度負担を減らす制度等の財政的援助や支援が必要である。県民の安心・安全の確保という観点から、国、県、市町村、教育委員会など関係機関が連携して有効な手だてが講じられるよう働きかけるべきではないか。
 市町村が耐震化を実施する場合、国の補助制度を活用し、早期に100%の水準に達してもらいたい。単年度負担の問題が解消されないなら、県の貸し付け制度を使ってもらうことにより、実効的な措置ができるものと考えている。
市町村が耐震化を実施する場合、国の補助制度を活用し、早期に100%の水準に達してもらいたい。単年度負担の問題が解消されないなら、県の貸し付け制度を使ってもらうことにより、実効的な措置ができるものと考えている。
旧県会議事堂の修復保存

 明治31年に建築された旧県会議事堂「一乗閣」は、文化財的価値が高く、重要木造建築物である。修復保存については過去何年にもわたり要望してきたが、一日も早く実現してほしい。
明治31年に建築された旧県会議事堂「一乗閣」は、文化財的価値が高く、重要木造建築物である。修復保存については過去何年にもわたり要望してきたが、一日も早く実現してほしい。
 旧県会議事堂は、和歌山県議会の歴史を今に伝える貴重な建造物であり、現存する木造和風議事堂では最も古い歴史的建造物である。2度の移築を経て時間がたっており、建物の傷みが激しく閉鎖されているため、根来寺や岩出市の協力を得ながら修復保存し、紀北地域の観光面における拠点として、また県議会の歴史を伝える文化財として後世に残していきたい。
旧県会議事堂は、和歌山県議会の歴史を今に伝える貴重な建造物であり、現存する木造和風議事堂では最も古い歴史的建造物である。2度の移築を経て時間がたっており、建物の傷みが激しく閉鎖されているため、根来寺や岩出市の協力を得ながら修復保存し、紀北地域の観光面における拠点として、また県議会の歴史を伝える文化財として後世に残していきたい。
和歌山市東部地域の渋滞緩和策

 国道24号バイパスは、紀州大橋の4車線化など一定の改良がなされ、地域経済の活性化につながっているが、花山や田中町交差点などでは相変わらず市内中心部への交通渋滞が常態化している。交差点改良や誘導案内板の整備等も含めた渋滞緩和策はどうか。
国道24号バイパスは、紀州大橋の4車線化など一定の改良がなされ、地域経済の活性化につながっているが、花山や田中町交差点などでは相変わらず市内中心部への交通渋滞が常態化している。交差点改良や誘導案内板の整備等も含めた渋滞緩和策はどうか。
 和歌山市周辺地域から中心市街地への流入交通を分散するため、県と市が連携して都市計画道路の整備を進めている。和歌山北インターチェンジの整備や交差点への右左折レーン設置、交通を円滑に誘導するための案内標識や路面標示などを関係機関と十分調整しながら検討し、重点的、効率的な渋滞解消策に取り組んでいく。
和歌山市周辺地域から中心市街地への流入交通を分散するため、県と市が連携して都市計画道路の整備を進めている。和歌山北インターチェンジの整備や交差点への右左折レーン設置、交通を円滑に誘導するための案内標識や路面標示などを関係機関と十分調整しながら検討し、重点的、効率的な渋滞解消策に取り組んでいく。
↑ページの先頭に戻る
国道168号橋本交差点の課題解消
 以前より、右折レーンの設置など大型車がスムーズに走行できるよう改良が求められている。国道168号から国道42号への流入が難しい状況だが、解消策はどうか。
以前より、右折レーンの設置など大型車がスムーズに走行できるよう改良が求められている。国道168号から国道42号への流入が難しい状況だが、解消策はどうか。
 渋滞解消策として、国道168号に、右折レーン、隅切りの設置が考えられるが、住宅、商店などの用地買収が必要となる。事業実施には地元の協力が不可欠で、今後、新宮市とともに努力していきたい。
渋滞解消策として、国道168号に、右折レーン、隅切りの設置が考えられるが、住宅、商店などの用地買収が必要となる。事業実施には地元の協力が不可欠で、今後、新宮市とともに努力していきたい。
県営住宅の家賃見直し
 公営住宅法施行令の一部改正により、来年4月、入居収入基準が引き下げられることになっている。制度の見直しで家賃が引き上がる世帯、また引き上げ率はどれくらいか。さらに、家賃引き上げに対する緩和措置や軽減措置はあるのか。
公営住宅法施行令の一部改正により、来年4月、入居収入基準が引き下げられることになっている。制度の見直しで家賃が引き上がる世帯、また引き上げ率はどれくらいか。さらに、家賃引き上げに対する緩和措置や軽減措置はあるのか。
 現在の県営住宅入居者の認定収入額をもとに推計すると、比較的収入が多い世帯について家賃が上昇することになるが、その家賃が上昇する世帯は約2割、1000世帯、16%の上昇率となる。家賃の軽減措置はないが、急激な負担増を避けるため、5年間で新家賃に段階的に移行するよう緩和措置をとることになっている。
現在の県営住宅入居者の認定収入額をもとに推計すると、比較的収入が多い世帯について家賃が上昇することになるが、その家賃が上昇する世帯は約2割、1000世帯、16%の上昇率となる。家賃の軽減措置はないが、急激な負担増を避けるため、5年間で新家賃に段階的に移行するよう緩和措置をとることになっている。
「紀州うめどり」のブランド化

 「紀州うめどり」が2008食肉産業展「地鶏・銘柄鶏食味コンテスト」において最優秀賞を獲得したが、その価値と意義についてどう思うか。
「紀州うめどり」が2008食肉産業展「地鶏・銘柄鶏食味コンテスト」において最優秀賞を獲得したが、その価値と意義についてどう思うか。
 他県の地鶏、銘柄鶏に負けない品質であると証明されたことは、和歌山ブランドの創出という観点から大きな価値がある。今後、より一層積極的にPR活動を展開し、紀州うめどりを和歌山ブランドとして全国に向けて発信していきたい。
他県の地鶏、銘柄鶏に負けない品質であると証明されたことは、和歌山ブランドの創出という観点から大きな価値がある。今後、より一層積極的にPR活動を展開し、紀州うめどりを和歌山ブランドとして全国に向けて発信していきたい。
県産農産物の輸出促進
 農産物の販売は、国内では少子高齢化もあり市場が縮小していくと考えられるが、海外では、アジア諸国が大きな市場になってきている。農産物の海外輸出について他府県の情報をよく聞くが、本県はおくれをとっていないか。
農産物の販売は、国内では少子高齢化もあり市場が縮小していくと考えられるが、海外では、アジア諸国が大きな市場になってきている。農産物の海外輸出について他府県の情報をよく聞くが、本県はおくれをとっていないか。
 海外にも目を向けた販路開拓等は重要で、長期総合計画でも輸出を「攻めの農業」の1つの柱として位置づけている。昨年、県農水産物・加工食品輸出促進協議会を設立し、ABICからアドバイザーを迎え、商社ネットワークを活用したプロモーション活動を展開するなど、積極的に取り組んでおり、決しておくれをとっているとは考えていない。今後も、新たな市場開拓に積極的に取り組んでいきたい。
海外にも目を向けた販路開拓等は重要で、長期総合計画でも輸出を「攻めの農業」の1つの柱として位置づけている。昨年、県農水産物・加工食品輸出促進協議会を設立し、ABICからアドバイザーを迎え、商社ネットワークを活用したプロモーション活動を展開するなど、積極的に取り組んでおり、決しておくれをとっているとは考えていない。今後も、新たな市場開拓に積極的に取り組んでいきたい。
用語解説
ABIC(エイビック)
国際社会貢献センター。商社など貿易関係の企業・団体から成る(社)日本貿易会が設立したNPO法人。民間レベルでの支援・交流活動を通じ、国内外での社会貢献への寄与を目的とする。
救命救急センターの運用体制強化

 救命救急センターを中心に拠点病院への救急搬送が増加しているが、空きベッドがなく救急制限せざるを得ない状況もある。スムーズな受け入れと重篤な救急患者への適切な診療を行えるよう運用体制強化を図るとともに、後方支援ができる病院の連携・充実を含めた、時代のニーズに合った救急医療体制の構築が必要ではないか。
救命救急センターを中心に拠点病院への救急搬送が増加しているが、空きベッドがなく救急制限せざるを得ない状況もある。スムーズな受け入れと重篤な救急患者への適切な診療を行えるよう運用体制強化を図るとともに、後方支援ができる病院の連携・充実を含めた、時代のニーズに合った救急医療体制の構築が必要ではないか。
 県立医科大学附属病院では、高度な治療や全身管理を行う救急部門と一般病棟の連携促進など、院内体制づくりを検討している。救命救急センターの運用体制強化を支援し、地域医療機関との連携を推進するなど、重篤患者の病状推移に応じて円滑に受け入れられる医療連携体制の確保に努めていきたい。
県立医科大学附属病院では、高度な治療や全身管理を行う救急部門と一般病棟の連携促進など、院内体制づくりを検討している。救命救急センターの運用体制強化を支援し、地域医療機関との連携を推進するなど、重篤患者の病状推移に応じて円滑に受け入れられる医療連携体制の確保に努めていきたい。
高齢者世帯への支援
 生活必需品の値上げ、雇用の不安定化、保険料の引き上げ、増税など、県民の暮らしは大変だ。特に負担が増え続ける高齢者の暮らしをどう感じているか。また、生活保護や老人医療費助成の拡充が必要と考えるが、低所得者世帯への支援策はどうか。
生活必需品の値上げ、雇用の不安定化、保険料の引き上げ、増税など、県民の暮らしは大変だ。特に負担が増え続ける高齢者の暮らしをどう感じているか。また、生活保護や老人医療費助成の拡充が必要と考えるが、低所得者世帯への支援策はどうか。
 高齢者が元気に暮らせて、将来、医療や介護が必要になっても対応できる県づくりを長期総合計画の中でも重要な柱としているが、生活保護制度などのセーフティーネットも重要と考える。高齢者が生きがいを持ち、安全・安心に暮らせる社会を守っていきたいと考えている。
高齢者が元気に暮らせて、将来、医療や介護が必要になっても対応できる県づくりを長期総合計画の中でも重要な柱としているが、生活保護制度などのセーフティーネットも重要と考える。高齢者が生きがいを持ち、安全・安心に暮らせる社会を守っていきたいと考えている。
↑ページの先頭に戻る

 産業の振興のためには、県内の事業者に地域資源を活用した事業展開を積極的に行っていただくことが最も重要であり、助成等による中小企業の育成や、優れた県産品等を県外に向けて積極的にプロモーションしていきます。
産業の振興のためには、県内の事業者に地域資源を活用した事業展開を積極的に行っていただくことが最も重要であり、助成等による中小企業の育成や、優れた県産品等を県外に向けて積極的にプロモーションしていきます。