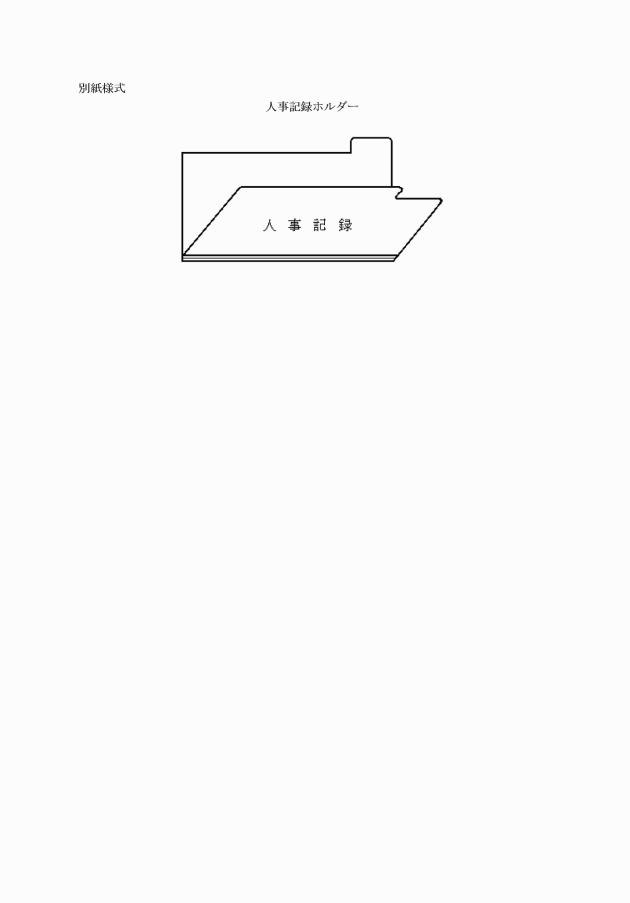○人事記録に関する規則の実施規程
昭和31年10月1日
人事委員会告示第5号
人事記録に関する規則の実施規程を次のように定める。
人事記録に関する規則の実施規程
第1条 人事記録に関する規則(昭和31年和歌山県人事委員会規則第10号。以下「規則」という。)第3条第14号に規定する人事委員会の指定する恩給に関する記録は、恩給給与規則(大正12年勅令第369号)第2条第2項第1号に規定する現認証明書又は事実証明書及び恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)第16条に規定する勤務日誌とする。
第2条 規則第4条に規定する勤務記録カード(以下「カード」という。)の記入要領は、別紙第1に定めるところによる。
2 カードの「勤務記録」欄に記入する人事異動事項の異動種目については、別紙第2に定めるところによる。
第3条 人事記録の保管要領は、別紙第3に定めるところによる。
付則
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和33年3月29日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月17日人事委員会告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、告示の日から施行する。
附則(令和7年5月30日人事委員会告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。ただし、別紙第1の改正規定(「禁こ」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)は、令和7年6月1日から施行する。
別紙第1
勤務記録カード記入要領
勤務記録カードの記入要領は、次の各号に定めるところによる。
1 「索引」の欄には、カードの整理保管のための分類符号を適宜記入する。
2 「性別」の欄には、それぞれ該当する□の中にレ印を記入する。
3 「生年月日」の欄には、生年月日を記入する。
4 「氏名」の欄には、氏名を記入し、点線の上に振り仮名を付ける。
5 「旧氏名」の欄には、旧氏名及び改姓年月日を記入する。
6 「本籍地」の欄には、本籍地を記入する。
7 「現住所」の欄には、現住所を記入する。
8 「学歴」の欄には、学歴を年代順に記入する。この場合、学校名、学部科名、修学期間、卒業、修業、中途退学又は在学中の別、学年、専攻科目及び当該学歴について適用される学歴免許等の資格区分をそれぞれの欄に記入するとともに、「卒、修業、中退、在学中」の欄の学年数を集計し、集計欄に記入する。
9 「資格」の欄には、免許、検定その他の資格で必要と認めるものについて、その取得年月日及びその名称をそれぞれの欄に記入する。
10 「研修」の欄には、職員の受けた研修で必要と認めるものについて、その名称、実施機関の名称、研修を受けた期間及び時間数をそれぞれの欄に記入する。
11 「扶養家族」の欄には、扶養手当の支給の対象となる家族について記入する。
12 「地域」の欄には、地域手当の支給地域の級を記入する。
13 「特地」の欄には、特地勤務手当の支給地域の級を記入する。
14 「前歴」の欄には、本県の職員に採用される以前の職歴(自営及び在家庭を含む。)を年代順に記入する。この場合、それぞれの欄に、勤務先の名称(自営及び在家庭については、その旨及び参考事項を付記し、以下の各事項についても、それぞれ準じて記入するものとする。)、勤務先において占めていた職の名称又は従事していた職務内容、勤務し、又は従事した期間、実際の勤務し、又は従事した年数並びに経験年数換算表による期間の区分、換算率及び換算年数を記入し、最右欄にその集計を行うとともに、決定した初任給の号給又は額を記入する。
15 「備考」の欄には、職員の有する特殊技能、身体上の故障その他特記すべき事項を記入する。
16 「勤務記録」の欄には、次に掲げる事項を年代順に記入する。この場合、当該事項に係る年月日、任命権者その他の発令者を長とする機関の名称その他説明事項をそれぞれの欄に記入するとともに、第1号に掲げる事項については、当該人事異動について、異動種目、職級名、給料、所属部課及び職名をそれぞれ該当する欄に記入し、任用の期間又は不利益処分の根拠法規及び処分内容等については、「職級名」、「給料」及び「所属部課・職名」欄に適宜記入し、かつ、必要があれば次の右欄を使用するものとし、第2号から第9号までに掲げる事項については、当該事項を「異動種目」、「職級名」、「給料」及び「所属部課・職名」の欄に、その区分にかかわりなしに記入するものとする。
1 人事異動事項(職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)その他の規定に係る人事異動通知書の「異動内容」欄に記入すべき事項をいう。)
2 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「恩給法一部改正法」という。)附則第4条の規定による加算の理由となる事実に関する事項
3 恩給を受けた事実及びその恩給が一時恩給の場合にはその金額
4 一時恩給を返還した事実及びその金額
5 恩給法一部改正法附則第7条の適用又は準用を受ける者が当該外国勤務(外国出張を含む。)をした場合の勤務地、出発及び着任の年月日並びに離任及び帰着の年月日
6 表彰に関する事項で必要と認めるもの
7 公務災害に関する事項で必要と認めるもの
8 拘禁刑以上の刑を受けた事実に関する事項で必要と認めるもの
9 その他必要と認めるもの
別紙第2
人事異動種目表
異動種目 | 意義 |
1 採用 | 昇任、降任及び転任以外の方法によって、現に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。 |
2 昇任 | 現に任用されている職員を法令その他の規定により公式の名称(警察官の階級、職務の等級、組織上の地位等をいう。以下同じ。)が与えられている上位の職に任命することをいう。 |
3 降任 | 現に任用されている職員を法令その他の規定により公式の名称が与えられている下位の職に任命することをいう。 |
4 転任 | 現に任用されている職員を任命権者を異にして昇任及び降任以外の方法により他の職に任命することをいう。 |
5 配置換 | 現に任用されている職員を同一任命権者のもとで昇任及び降任以外の方法により勤務場所を異にする職に任命することをいう。 |
6 転職 | 現に任用されている職員を同一任命権者のもとで昇任及び降任以外の方法により職名を異にする職に任命すること(当該職員について給料表の適用を異にする場合を含む。)をいう。 |
7 出向 | 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えることをいう。(ただし、併任に係る場合は、異動種目は、出向(併任)とする。) |
8 臨時的任用 | 法第22条の3第1項前段の規定により、現に職員でない者を臨時的任用することをいう。 |
9 臨時的任用の期間更新 | 法第22条の3第1項後段の規定により、臨時的任用を期間の更新することをいう。 |
10 併任 | 任命権者を異にして、職員をその職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。 |
11 兼職 | 同一任命権者のもとで、職員をその職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。 |
12 併任解除 | 併任中の職員の兼ねている職を解除することをいう。 |
13 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除することをいう。 |
14 併任終了 | 任期の満了等により、当然に併任の終了したことをいう。 |
15 兼職終了 | 任期の満了等により、当然に兼職の終了したことをいう。 |
16 職名変更 | 法令その他の規定により、組織の変更を伴わないで職員に付与されている公の名称の変更されることをいう。ただし、昇任、降任及び転任(配置換及び転職を含む。)による場合を除く。 |
17 組織変更 | 法令その他の規定により、機関又はその組織の名称が変更したため、職員に付与されている公の名称の変更されることをいう。 |
18 職名付加 | 職員に公の名称を付加すること及び法令その他の規定により当然に公の名称の付加されることをいう。ただし、併任(兼職を含む。以下同じ。)による場合を除く。 |
19 職名解除 | 職員に付加されていた公の名称をなくすこと及び法令その他の規定により当然になくなることをいう。ただし、併任の解除又は終了による場合を除く。 |
20 休職 | 法第28条第2項の規定により、職を保有したまま職員を職務に従事させないことをいう。 |
21 休職の期間更新 | 休職の期間を更新することをいう。 |
22 復職 | 休職中の職員を職務に復帰させること及び休職期間の満了により当然に職務に復帰することをいう。 |
23 失職 | 職員が法第16条に規定する欠格条項に該当することによって当然に離職することをいう。 |
24 辞職 | 職員がその意により退職することをいう。 |
25 退職 | 職員の任用等に関する規則第33条の規定により、職員が当然に離職することをいう。 |
26 免職 | 法第28条第1項の規定により、職員をその意に反して退職させることをいう。 |
27 戒告 | 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として戒告することをいう。 |
28 減給 | 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として一定期間給料を減ずることをいう。 |
29 停職 | 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として一定期間その職を保有するが職務に従事させないことをいう。 |
30 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として職員をその意に反して退職させることをいう。 |
別紙第3
人事記録保管要領
1 人事記録(勤務記録カードを除く。以下同じ。)は、別紙様式の人事記録ホルダー(職員別に作成した厚紙2つ折の書類ばさみをいう。以下「ホルダー」という。)に入れて保管する。
2 ホルダーの見出し部分には、職員の氏名を記入し、振り仮名をつける。
3 人事記録は、日付順に上に重ね、ホルダーの左を上辺にして入れ、クリップで留める。
4 人事記録ファイル(ホルダーに人事記録を綴り込んだものをいう。以下同じ。)は、人事担当課において、適当な整理保管容器に入れて保管する。
5 人事記録ファイルは、必要に応じ、所属部課別又は職名別若しくは職級別に分類し、アイウエオ順又はイロハ順に配列する。この場合、分類配列に応じ、適宜ガイドを使用する。
6 勤務記録カードは、一括して人事担当課において、人事記録ファイルとは別個に保管する。この場合、人事記録ファイルと同じ方法により分類配列するものとする。