今月の旬な味(だいこん)
和歌山県食育ひろば
今月の旬な味
今月紹介するのはだいこんです。
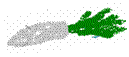
和歌山県のだいこんって
歌山県のだいこんの栽培面積は、129ヘクタール(平成25年産)で、その多くが和歌山市で作られています。 青首だいこんが多く作られていますが、和歌山県では伝統野菜として古くから栽培されている2種類のだいこんがあります。

青首だいこん


和歌山だいこん 青身だいこん
- 和歌山だいこん
食べる部分が純白で、くせがなくいろいろな料理に利用できますが、最近は漬け物用に利用されています。 - 青身だいこん
長さ25センチほどの大きさで首の部分が緑色です。主に正月の雑煮用として使われています。
だいこんができるまでを知ろう
(1)畑の準備
(春だいこん3月 夏だいこん5月中旬 秋冬だいこん9、10月)
種まきの2週間以上前に苦土石灰を散布して深く耕し、根の生育を妨げるような小石などは取りのぞきます。
種まきの7日前まで、化成肥料を全面に散布して、よく耕しておきます。
水はけのよい菜園は平畝に、耕土の深いところや水はけの悪い菜園では高畝にして、表面を平らにならしておきます。
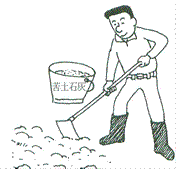
2週間以上前

7日前まで
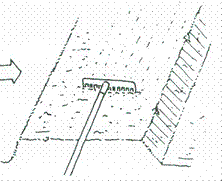
(2)種まき
牛乳びんの底などでまき穴をつくり、種を1ヶ所の穴に5粒から6粒ずつ入れて、点まきし、1センチ程度土をかぶせて軽く押さえます。乾燥を防ぐため、切りわらを薄く広げて、水やりを行い、寒冷紗でおおいます。

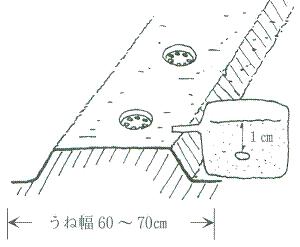
(3)間引き
1回目は、子葉が開いた時に子葉がハート形のものを1ヶ所に3本残します。丸形、長形のものを間引きましょう。
2回目は、本葉2枚から3枚の時に、1ヶ所に2本残します。
3回目は本葉5枚から6枚の時に、元気のよいものを1本にします。
春だいこんでは越冬前に1ヶ所に3本から4本残しておき、2月から3月になって、寒さがやわらいでから間引きします。
間引きは非常に大切な作業です。発芽後3回ぐらいに分けて間引きを行い、そのつど追肥と土寄せをしておきます。
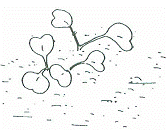
1回目

2回目

3回目
(4)土寄せ
化成肥料をうねの肩へ交互に施します。追肥後は軽く中耕して、根元がかくれるように株元へ土よせをしておきます。

(5)収穫
雨が降っておらず、土が乾いている時に、太ったものから収穫します。秋冬だいこんは、種まき後60日から90日、3月まきは90日、夏だいこんは50日から60日で収穫となります。
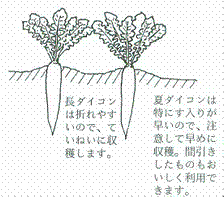
(6)防寒、かん水
春だいこんでは、うねの北側にワラや笹、木の枝などを立てて防寒します。
夏だいこんでは、ワラや刈り草をしいて、乾燥や強い雨から守ります。乾燥が激しい時のみ、畝間にかん水します。

防寒
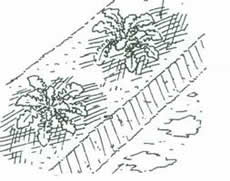
かん水
栄養いっぱい
- ジアスターゼ
消化酵素。でんぷんの分解を促進して消化を助けて、胃もたれを防ぐ効果が期待できます。 - メチルメルカプタン
辛味成分の1つ。血栓防止や解毒作用、がん予防に有効に働くとされています。 - ビタミンC
葉に多く含まれていて、免疫力を高めて感染症予防に効果があるとされています。
おいしく食べてね
のっぺ
(材料)

だいこん 320グラム
にんじん 80グラム
さといも 80グラム
油あげ 4グラム
ちくわ 15グラム
油 大さじ1
しょうゆ・砂糖・酒 各大さじ3
(作り方)
(1) だいこん、にんじんは皮をむき、いちょう切りにします。
(2) さといもは皮をむいて輪切りにし、塩でこすってぬめりをとり、さっとゆがきます。
(3) 油あげは千切り、ちくわは輪切りにします。
(4) なべに油を熱し、野菜を炒め、ひたひたのだし、油あげ、ちくわを加えて煮含めます。
(補足)のっぺは紀ノ川流域の郷土料理で、節分や大晦日などにはかかせません。
物知りコラム
だいこん王国日本

土に植わっている様子
私たちにとってとても身近なだいこんは、地中海が原産地です。
地中海からシルクロードを通って1250年前ぐらいに日本にやってきて、なんと日本各地の風土に合わせて150種類から200種類もの品種ができました。紹介した和歌山だいこんや青身だいこんもそのうちの1つです。
いまでは日本を代表する野菜の1つとなり、英語でもDAIKONで通用するほどになっています。
参考図書
「食材健康大辞典 」時事通信社発行
「そだててあそぼう だいこんの絵本」農文協発行
百科絵で見る家庭菜園」ひかりのくに株式会社発行


